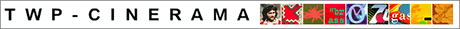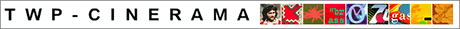『(ラヴ・ソングについて)人間関係、特に男女の関係っていうのは人間の一生の中で最も重要な事だよ。それは「僕は誰かに逢って、それから別れました」という事だけじゃない。その間にはいくつもの出来事がある。みんないつも議論の場を持ち、何度も恋に落ちる。結局、曲の重要なポイントは、僕らは皆人生の中で様々な問題に面し、そしてその解決方法は誰も知らないという事だ。』(1991年7月、Lime Lizard誌)
『(今まで男女の関係についての唄を書くのに飽きた事は無いの?) 無いね、本当に。僕はたぶんラヴソングを書くのが専門なのかもね。』(1996年8月、U.S.ツアー中に訪れたNew Yorkで)
『僕の書いたものにはいつだって僕自身の事が少しは投影されているけどね... まあ、曲というのはちょっとした映画の脚本みたいなものと考えているんでね...で、歌う事はたぶん声優の吹き替えのようだし。歌詞を書く時の最高のポリシーは自分の仕事に絶えず不満を抱かせる事だ。多くの作詞家は(逃げの意味で)よくある同じような言葉で韻を踏んで、それで古典を書いたと思っている。』(2000年3月、米Fallout Magazine)
『僕は少々シアトリカルなやり方で自らの思いと失望を祝福するアプローチを取る事に決めたんだ。僕のやり方で、それまでのポップ・ソングのリリシズムにありがちだった決まり文句(クリシェ)を用いずにユーモアのある観察眼を持って、意味のあるエモーショナルなシチュエーションを描きたかった。』(1997年)
『(インディ時代は、シーンを引っ張っていくトップの自覚はなかったのですか?)そんなこと全く考えなかったよ。そういった考えは身勝手なもんだと思うよ。自分達のためにのみ音楽を作り、レコードを作ってるんだからさ。僕らはみんなインディペンデント、自立した人間であることを心がけているんだ。お互い強い影響を与えられるようにね。有名になることも大切かもしれないけど、自分達の才能を磨いていくことの方がより重要だし、それがパワーにつながるんだと思う。単にソングライターやパフォーマーであるばかりでなく、僕らはマネージメントについてもやらなければならないんだ。責任を果たすにはまず自立した人間でなきゃね。』(1989年、アルバム『BIZARRO』の頃)
『僕の基本的な信条の1つとして、一度あるタイプの音楽作品を作ったのなら、それはもう置き去りにして次へ進まならければならない、というのがあるんだ。僕には多くのバンドがなぜ一度レコードを作ってから... 繰り返し繰り返しまた同じようなものを作っているのか理解出来ないよ。』(2000年3月、米Fallout Magazine)
『全てのウェディング・プレゼントのレコードは、僕らの変化の表れだと思う。 僕らが作ったアルバムは、特定のファンを失って新たなファンを引き入れる、その連続だった。ある人たちには“Bizarro”がウェディング・プレゼントの音なんだろう。また他の人にとっては“Seamonsters”だろうし。“Bizarro”が好きな人にとっては“Seamonsters”は暗過ぎて嫌われるし、“Seamonsters”が好きな人は“Watusi”はポップ過ぎて嫌いだっていう。レコードを売るって事に関してはそういうのは僕の人生に起こった不幸だろうけど、アーティストの見地では何度も同じ様なレコードを作らなかった事は誇りに思っているよ。』(2001年8月)
『(CINERAMAについて)なぜ唯一のオリジナル・メンバーである僕が今敢えてソロ・ユニットを、だって?The Wedding PresentはDavid Gedgeのプロジェクトじゃ無かったからね。僕にはグループ全体に僕個人の音楽的な好みまで押し付けられるような力は無かった。僕はいつだって誰かに予想も付かないような様々なジャンルやスタイルの音楽を楽しんできたんだ。僕はポップ・ミュージックの大ファンなんだよ。例えば、ボンド・ムーヴィー(=007シリーズ)のジョン・バリーのスコアに憧れているしね。問題なのは、The Wedding Presentがグループ内部のメンバーだけじゃなくそのファンからも含めてだけど、ハナっからギター・バンドとして認知されていたんだよね。』(2000年3月、米Fallout Magazine)
『僕は時間をかけてだんだんと変化しようとしてきたし、思うに1994年のWedding Presentのアルバム“Watusi”がCinerama発祥の地だったんだ。でも、グループ自体や全ての過程一つ一つが特定の視点からしか論じられなかったからいつも困難を伴ったものだったよ。』(2000年10月、英Designer Magazine)
『音楽って、なにかひとつのカテゴリーに押し込まないと、なかなか論評しにくいものがあるだろう?僕らは昔はSmithsと比べられたし、アメリカのグランジともよく比較される。ひとつの枠組に当てはめるのはすごく簡単なことだけど、音楽そのものとか音楽に向かう姿勢を評価するより、えてしてそういう表面的な判断をされがちなんだよね。』(1993年)
『ポップ・ミュージックはもっとスポンティニアス(自己発生的)であるべきで、なるようになるものだと思う。前なら「どうやれば自分の仕事に大好きなTVのテーマソングや映画音楽への愛情を注ぎ込む事が出来るか?」という事が課題だった。今じゃ答えは出てるけどね。 誰も次の課題が何かなんて、知る由はないね。』(2001年8月)
『CINERAMAを始めた大きな理由というのはそれがソロ・プロジェクトの様なものだったからで、TWPの様なレコードにする必要は無いと考えていたからだと思うね。実際「Va Va Voom」ではわざわざTWP的な要素は排除したんだけど、時を経るにつれそんな事は重要でもなくなって、またレコードを作る結果としてTWPの様なサウンドになろうとも構わなくなったんだ。ライヴではさらにノイジーなサウンドになっていったんだし。』(2001年7月)
『オーケストレーションの為にヘヴィーなギター・サウンドを取り入れるのを止めてみたり、CINERAMAでソフトタッチなギターを演奏してみたりというのは実に開放的な体験だったんだけど、でももう何年か続けてきてて、だんだんとWeddoesでやっていた様なサウンドが恋しくなってね。
リマスタリングの過程で「Bizarro」と「Seamonsters」をここ何年かで初めて聴いた事が確実にそういう思いにさせたんだろうね。またこういうぶっ飛んだギター・パートをラウドに鳴らせたらいいよな、って自分が思い始めている事に気が付いた。』(2001年8月)
『(なぜCINERAMAがTHE WEDDING PRESENTに改名を?)CINERAMAというのは僕にとっては何か別次元の事だったんだ。僕と僕のガールフレンド、Sally Murrellのものでね。それがギグをやり始めてから二人のユニットだったCINERAMAが特定のグループになって何年かを過ごす事になった。さらには、最近はCINERAMAではやってこなかった様なもっともっとロックっぽい音になって。で、彼女も離れて、ごく自然にTWPになるのが当たり前に思えてきてね。』(2004年11月foutraque.com、新生TWP正式始動後初インタビューで)
『3rdアルバムの『Torino』の後に彼女が離れて、代わりを入れずにずっと(かつてのTWPと同じ編成の)4人でライヴをやってきたし、それにここ数年当たり前の様にTWPの曲もステージでやってきたから、だんだんと作る曲もサウンドがTWPっぽくなってきた。だからギターバンドに戻って“じゃあそれはTHE WEDDING PRESENTって呼ぶしかないようだね”となった訳で。CINERAMA最後のJohn Peel Sessionでもエンジニアが“こりゃあもうThe Wedding Presentじゃないか!”って言ってたくらいだから(笑)。確かにアルバムには明らかにCINERAMA的なサウンドの要素が入ってるけど、何せ僕らはそれを8年間もやってきたんだからね。今はまるで2つのバンドが合併した様な感じだね。』(2005年2月ready steady jedi.com)
『ツアーで昔の曲を再び演奏する事にも興奮するかって?全然そんなことはないよ。だってこれは明らかに“再結成”でも無ければ“グレイテスト・ヒッツ・ツアー”でも無いからね。僕に関する限りではザ・ウェディング・プレゼントは活動を一旦休止した1997年からずっと続いてきたものだし、前がシネラマのツアーだったのと同じ様に今回はザ・ウェディング・プレゼントのツアーだっていう事。本当に、僕にとってはいつもと一緒なんだよ。このツアーに関しても特別な事は何も無い。みんなそうあって欲しいんだろうけどね。
でも変な話だよね。だってこのアルバム『TAKE FOUNTAIN』をザ・ウェディング・プレゼントのアルバムとして出そうと決めた時、ほとんど簡単な選択だったんだよね。“僕にはザ・ウェディング・プレゼントっぽく聞こえるから、これはザ・ウェディング・プレゼントって呼ばないか?”コインをトスして、“OK、じゃザ・ウェディング・プレゼントだな”という具合でね。別に重大な決定じゃなかったし、どういう風にそうしたかなんて忘れるくらいでね。そしたら、その名義の変更を決めた途端、みんながみんな“えっ!ザ・ウェディング・プレゼントだって!”みたいになってね。
確かに前のシネラマのツアーでは大規模の会場では演奏していなかった訳で、名前を変えた途端にこの状況…多少は悩ましかったよ。だってこれじゃシネラマがまるで悪いグループだったみたいじゃないか。たぶん僕は名前の持つ力の大きさをだいぶ過小評価していたんだろうね。』(2005年3月Sandman Magazine Issue019から)
『次にやる曲は僕の別のバンド、シネラマの曲なんだけど…というよりか、僕らの曲でもあるんだけどね…要するに、CINERAMAとTWPというのはクラーク・ケントとスーパーマンの関係みたいなものだな(笑)。』(2006年2月新生TWPの北米ツアー中のMCより)
『先の事がどうなるかなんて分からないよ。計画は立てないタチなんでね。まだCINERAMAのアイデアは暖めてるよ。次のアルバムはもしかしたらもっとCINERAMAっぽいサウンドになるかもよ(笑)。』(2005年2月ready steady jedi.com)
『(この音楽産業に長年身を置いてきて、何か心残りになっている実現しなかった野心などはありますか?それとも十分に成功したとか?)いや、全然満足はしてないよ。僕の創造的な道程の一部は「野心を完了させるストレッチング」であると思う・・・一度何かを満たされたら、また新たなものを発見したくなるんだ。』(2001年2月)
|