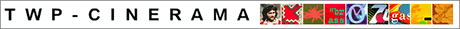
| BIOGRAPHY |
THE WEDDING PRESENTデビューからCINERAMA、さらにCINERAMAから改名する形で始動した新生THE WEDDING PRESENTまでの歴史を出来るだけ簡潔にまとめています。もっと細かく時系列で辿りたい方は当サイトのTIMELINEを、大まかなメンバーの流れについてはFAMILY TREEをご参考ください。また文中の「TWP」「Weddoes」はThe Wedding Presentの略称/愛称です。 THE WEDDING PRESENT結成まで 1960年4月23日、リーズ近郊のBramleyに生まれたDavid Lewis Gedge(デイヴィッド・ルイス・ゲッジ)はリーズ大学に進学するまでの10代の大半をマンチェスター近辺で過ごす。いくつかお遊びのアマチュアバンドを経て1980年頃、当時のガールフレンドのJanet Rigby、デイヴィッドが通っていたリーズ大学の掲示板に貼りだしたメンバー募集のチラシを見て参加したベースのKeith Gregoryの3人でThe Lost Pandasを結成。Joy DivisionやThe Cure、デイヴィッドとは中学~高校時代の親友だったDave FieldingがいたThe Chameleonsに影響を受けた音楽性だったというこのバンドがデイヴィッドにとって人生で初めてシリアスに音楽活動に打ち込んだバンドだった。 The Lost Pandasでは結局音源を残す事なく解散。同バンドから引き続きKeith Gregory、デイヴィッドとは幼なじみのギターリストPeter Solowka、何人かドラマーを試した上で音楽的趣向が似通っていた、特にThe Fall好きという点で意気投合したというShaun Charmanが最後に加わり、THE WEDDING PRESENTのオリジナル・メンバーが揃ったのは1985年に入った間もない頃である。このロマンチックな響きのあるバンド名の命名はデイヴィッド・ゲッジによるもの。名前の由来についてはデイヴィッドがアメリカン・コミック好きであることからバットマンに出てくるエピソード名「The Wedding Present」から取られたとか諸説あるが、単純に言葉の響きが気に入ったから、と発言している。 1985年~1987年:GEORGE BEST期 1985年3月1日、この4人が揃って初めてのライヴがヨークシャーにあるパブShiresで行われ、5月にはデビュー・シングル"Go Out And Get 'Em Boy!"を自主レーベルReceptionから発売。440英国ポンドを注ぎ込んで500枚という希少プレスで制作されたこのシングルが高名なBBC Radio 1のDJ、John Peelに気に入られ、頻繁にオンエアされる事となった。16歳の頃から彼の番組のヘヴィー・リスナーで、全放送のエアチェックを欠かさなかった程の大ファンだったデイヴィッド・ゲッジは最初にPeelの番組でデビュー曲がオンエアされた時、家の中を走り回る程大喜びしたという。以降、ウクレイニアン・フォーク・セッションの特別プロジェクトや発表前の新曲の初演、のちのCINERAMAや新生TWPの初お目見えとなる場を提供するなど度々重要な局面でJohn Peel Showでのセッションが行われ、2004年10月25日にJohn Peelが急逝するまでデイヴィッドとは公使に渡り強力な信頼関係が続いていく事となる。 1986年1月にはセカンド・シングル、"Once More"、同7月には両A面シングル"You Should Always Keep In Touch With Your Friends / This Boy Can Wait"と順調にリリースを重ねて行き、初のJohn Peel Showへの出演を含むBBCレディオ・セッション、英音楽誌のNew Musical Express(=N.M.E.)が編纂した新進気鋭のバンドばかりを集めたコンピレーション『N.M.E. C86』にもフィーチャーされた他、この年だけで150回のギグが行われ、めきめきと頭角を現していく事になる。 1987年2月には初期の代表曲となる"My Favorite Dress"を発表。同7月のシングル"Anyone Can Make A Mistake"を経て、10月には記念すべきデビュー・アルバム『George Best』(写真右)がリリースされる。マンチェスターで青春時代を過ごしたデイヴィッドにとってのヒーローだったというマンチェスター・ユナイテッドの天才サッカー選手、ジョージ・ベスト氏の名前を冠し、ジャケットにもデイヴィットたちが見つけてきたジョージのユニフォーム姿の写真を使用している。溌剌としたギター・リフにキラキラとしたメロディーライン、The Lost PandasのメンバーでもあったJanet Rigbyとの別れが大きく影響したというデイヴィッド言う所の「幾分か私小説的」という生々しすぎて笑えないリアリティーを帯びている恋愛模様を描いた歌詞。音楽的には習作の域を出ないものの、この後数多くのヴァリエーションを生んでいく独特な作風が既に表れている。 しかしこの年の暮れ、音楽的な意見の相違と個人的な人間関係の悪化からバンドを追放される形でドラマーのShaun Charmanが脱退。後釜に入ったのはかつてギタリストのPeter SolowkaとバンドThe Chorusを組んでいたSimon Smith。彼の強力無比なプレイがバンドの演奏力を飛躍的に高める結果となり、Weddoesサウンドの屋台骨として1997年の活動停止まで支えていく事になる。 1988年~1989年:初の編集盤TOMMY~ReceptionからRCAへ移籍 1988年2月、Shaun Charman在籍時最後の録音となった6枚目のシングル"Nobody's Twisting Your Arm"で初めて英国シングルズ・チャート上位にランクイン。 1988年7月、デビュー時から4枚のシングルとJohn Peel Showを含むBBC Radio 1でのレディオ・セッションから編纂された初のコンピレーション・アルバム『Tommy』発売。9月には自主レーベルReceptionからのラスト・リリースとなった"Why Are You Being So Reasonable Now?"がリリースされる(U.K.インディーズチャートでは初のNo.1)。 1989年初め、英音楽誌のNew Musical Express(=N.M.E.)で開かれたリーダーズ・ポール(読者の人気投票)でU2やR.E.M.といった世界的な人気バンドを抑えてTHE WEDDING PRESENTが堂々の1位に選出される。さらに自主レーベルReceptionから大手のメジャー会社RCAへの移籍も発表され、大きな話題を呼んだ。 1989年:ウクレイニアン・フォーク・セッション集のリリース~BIZARRO期 同年4月、1987年10月と'88年3月の2回、BBC Radio 1 "John Peel Show"の中で披露してきた特別プロジェクト、ウクレイニアン・フォーク・セッションをまとめた企画盤『Ukrainski Vistupi V Johna Peela』がRCAからリリース。紙製スリーヴとブックレットの凝った体裁も話題になった本作は旧ソ連領だった時代のウクライナ共和国で生まれた父を持つギターリストのPeter Solowkaの発案で、英国北部のウクレイニアン・コミュニティで愛されるウクライナやロシアのフォーク・ソングやイギリスのトラディショナル・ソングをバラライカやバンドリンなどウクライナの伝統的な楽器を交えてパンキッシュに演奏したもの。今聴くとWeddoesの本質からはかけ離れた風変わりなものであり、むしろこのセッションに参加したLen Ligginsなどのゲスト・メンバーたちと共にPeter Solowkaが結成するThe Ukrainiansのデビュー作と言った方がいい内容だが、折からのワールド・ミュージック・ブームや当時まだ独立前だったウクライナの文化復興運動の盛り上がりも受けてかこの試みは大歓迎され、全英アルバム・チャート最高位22位という好成績を収める。同セッションは未発表分も含めて、現在では2007年に発表されたCD 6枚組の大作ボックス『The Complete Peel Sessions 1986-2004』に録音時期毎にまとめられて収録されている。 同年9月、代表的なヒット曲"Kennedy"、そして同曲を収録したRCA移籍後初のフルアルバムとなるセカンド・アルバム『Bizarro』(写真左)リリース。初期からのスタイルを突き詰めた唯一無二のエレクトリック・ギター・サウンドはもちろんのこと、Simon Smithというどんな速いテンポの曲でも全くブレが無いだけではなく、独特な手数の多いドラミングによって強力なグルーヴを牽引していくドラマーの加入により、さらにリズムが強化された圧巻のバンド・グルーヴが融合。デイヴィッドが綴るミゼラブルなラヴ・ソングの集大成ともなった疾風怒濤の傑作である。このアルバムもやはり全英アルバム・チャート最高位22位を記録。 1990年~1991年:SEAMONSTERS期 1990年2月、アルバムからのリカットとなるシングル"Brassneck"リリース。このシングルの為にアメリカ・インディーズ界の大物エンジニアで自らもBig Black、Rapeman、現在はShellacなどで活躍するSteve Albiniを迎え、ロンドンで再レコーディングされた。 このコラボレーションはさらにシカゴへと場所を移し、9月に"3 Songs EP"として発表。この2作のEPや同時期のPeel Session、ライヴを通してWeddoesはバンドの本質はそのままに比類無きヘヴィネスを体現した新たな姿を聴衆に見せつける事になる。 翌1991年、先行シングル"Dalliance"に続き、5月には今もなお最高傑作と謳われるサード・アルバム『Seamonsters』(写真右)がついに発表される。Steve Albiniと共にミネソタ州Cannon Fallsという町にあるスタジオPachyderm Studiosで凍て付く寒波の訪れる中たった12日間でレコーディングされたセッションから抽出された全10曲。研ぎ澄まされたエレクトリック・ギターのウォール・オブ・サウンド、これぞアルビニ・エンジニアリングの極地とも言える異様にデットな隙間を残したアンビエント。前作にあった高揚感とスピード感は減退しているのに明らかにピークを振り切ったかの様なテンション。重厚ながらも全体を通しては透徹した印象をも残すその希有なサウンド・スケープの中で愛憎入り交じる狂おしいラヴソングが歌われる。語義通りの意味で唯一無二、比肩する存在のない20世紀のロック・マスターピースと呼んでも差し支えないだろう金字塔である。アルバム・チャート上でもバンド史上最高位の13位を記録した。 なお、本作を最後にPeter Solowkaは脱退、彼はかつてのウクレイニアン・フォーク・セッションにも参加していたメンバーたちと共に結成したThe Ukrainiansに専念し、現在も活動中である。後任にはA.C.TempleからPaul Dorringtonが加入、わりとシンプルなスタイルだったPeterには無かった新たなテキスチャをバンドに持ち込んだその柔軟なプレイはデイヴィッドのソングライティングの発展にも貢献していく。 1992年~1993年:THE HIT PARADE期~初のジャパン・ツアー 1991年暮れには驚愕のプランが発表される。何と1992年の1年間かけて月に1枚、第1月曜日に限定15,000枚のプレスでA面新曲、B面カヴァー曲というカップリングで7インチ・ヴァイナル盤のシングルを発売していくという“The Hit Parade”シリーズのプロジェクトである。 インディーズ・レーベルならまだしも大メジャーRCAからのリリース。果たして本当にそんな無謀な計画が貫徹できるのかどうか、またIan BroudieやJimmy Miller、Chris Nagle、 Brian Paulsonといった錚々たる面々をエンジニア、プロデューサーに迎えた本プロジェクトが果たして採算が取れるかどうか、バンド以外は誰もが半信半疑だったこのプロジェクトは誰も予想しえなかった成功を収める。限定プレスだった事も手伝って店頭に並んだ途端にソールド・アウトになる店が続出。結果的に全12枚が全英シングルズ・チャートのTOP30に食い込む(うち1曲"Come Play With Me"はバンド史上でも初となるTOP10ヒットになった)。これは当時Elvis Presleyが有していた年間のチャート・イン記録に35年ぶりに並んだギネス級の快挙となった。しかしElvisのは大半がリバイバル・ヒットだった事を考え合わせると、新曲のみで達成したこの記録は今もなお前人未踏の大記録と言っていいだろう。一方で発売日に在庫を隠し、程なくしてプレミアを付けて売り出す悪質な小売店が出現した事もあり、またRCA側の強い意向もあって当初予定になかった編集盤も早々とリリースされる事になった。まずシリーズ折り返し地点の1992年6月にリリースされた『Hit Parade 1』で前半の6枚が、全てが終了した翌1993年1月にリリースされた『Hit Parade 2』で後半の6枚がまとめられ、それぞれアルバム・チャートで22位/19位を記録している。現在は2003年にデイヴィット・ゲッジ監修の元リマスタリングされ、全12枚24曲がまとめられた新装2枚組『The Hit Parade』(写真左)でその全貌を辿る事が出来る。 この前代未聞の試みは何もそのある種マニアックなリリース形態だけが賞賛に値するものではなく、何しろ脂ののったバンドの絶好調さを反映したその新曲の素晴らしさ、原曲がどんなジャンルのもの(古いSF-TV番組のテーマ曲、当時流行のTwin Peaks、R&Bのアイザック・ヘイズにデイヴィッドのアイドルでもあったザ・モンキーズまで)であってもTWPカラーに染め上げるカヴァー曲の解釈の面白さにカッコ良さ、1枚1枚がシングルとして凄まじいクオリティとヴォルテージを有していたという作品の内容そのものが特筆すべきものである事は決して忘れてはならない。それにしても、神懸かり的な1年間の記録である。 兎にも角にも、この『The Hit Parade』シリーズによってバンドは広く世に知られる所となり、その活動は順風満帆に見えた。 1993年2月、当時としては異例だったフランス国内だけでの20日間にも及ぶツアーを敢行。同年3月には初のジャパン・ツアーが遂に実現したが、その年7月にThe Lost Pandas時代からのベーシスト、Keith Gregoryが脱退。ついにオリジナル・メンバーはデイヴィッド一人となってしまう。 さらにバンドの黄金時代を共に築いてきたRCAとの契約も終了。アメリカのIslandレーベルとの契約が発表され、後任のベーシストには元々は彼らの熱心な追っかけだったというDarren Belkを迎える。 1994年:WATUSI期 1994年9月、Island移籍第1弾アルバム、通算4作目となる『Watusi』(写真右)発表。米シアトルに赴いてSub PopレーベルやKレーベルのアーティストを数多く手がけていたプロデューサー、Steve Fiskと共に制作されたこのアルバムには多くの変化が顕れていた。 それまでのアーストーン調でアブストラクトなアートワークからカラフルでポップな具体的なモチーフを用いたものに、作曲者クレジットがDavid Gedge1人のものからメンバー全員の連名に(ただし、これは個々のメンバーの出版社契約の都合もあったようだが)、さらに初めてDavid以外のメンバーがリード・ヴォーカルを取るナンバーの登場、そしてSteve Fiskの貢献もあってそれまでのTWPの顕著なスタイルであったギター・オリエンテッドな作りから離れ、ホーンやパーカッション、キーボード類をさり気なく忍び込ませる様な多彩なアレンジが曲によっては為された。 音楽的には様々な挑戦が試みられて、一定の成果を上げたかに見えたが、残念ながらオーディエンスにはこの意欲的な変化が素直に受け止められる事なく逆に酷評され、全英アルバムチャート最高位47位とそれまでのRCA期の作品群に比べるとセールス的にもあまり芳しくは無かった。 さらに後年明らかになったのは、ここでバンドとしての発展と変化を望んだデイヴィッドと他のメンバー間での確執、具体的にはそれまでのTHE WEDDING PRESENT的なスタイルに固執するか否かでの意見の相違が生じ、結果的にデイヴィッドが譲歩して焦点が絞り切れていない散漫な出来になってしまった部分があったのも事実である。デイヴィッドが度々発言してきたように、THE WEDDING PRESENTは決してDavid Gedgeのリーダーシップに則って成立していたバンドではなく、あくまで民主的な合議制で全てを決めていた集合体だったのだ。デイヴィッドが自らを「リーダー」と称しなかったのも、またCINERAMA時に何度も再始動の意志を示しながらも彼の独断では実現出来なかったのもそこに理由がある。彼が当初CINERAMAとTHE WEDDING PRESENTを明確に区別する様にファンやプレス連中に諭していたのもこういうかつてのWeddoesの事情を念頭に置いていたからだと思う。 だがこの『Watusi』のお陰でデイヴィッドは後年のCINERAMAの構想を抱く事にもなった。そう、Davidは度々CINERAMA時のインタビューにおいてこの『Watusi』を“CINERAMA発祥の地”と称したのであった。もし仮にここでの試みが音楽的にも商業的にも成功を収めていたら、きっとCINERAMAも、そして同じSteve Fiskをプロデューサーに迎えた新生TWP名義の傑作『Take Fountain』も生まれなかったのではないだろうかと思う。 1995年~1997年:SATURNALIA期~THE WEDDING PRESENT活動休止 1995年に入って間もなく、Islandとの契約解除が発表される。IslandレーベルがPolygramグループに買収されたのがきっかけとなった突然のリストラ措置であった。3月には2代目ギターリストPaul Dorringtonが脱退。ギターのポジションが空席のまま自主制作でシングル"Sucker"を発表。このシングルにバックコーラスで参加していたTse Tse Flyの女性ベーシスト、Jayne Lockeyを新メンバーに迎え、それまでベースを担当していたDarren Belkがギターにスイッチする。 同年10月、イギリスの大手インディーズ・レーベル、Cooking Vinylとの契約が発表され、翌1996年1月、再出発となる6曲入りミニ・アルバム『Mini』(写真左上)発表(全英アルバム・チャート最高位40位を記録)。車と恋愛という明確なキーワードを盛り込んだバンド史上でも初となるコンセプト・アルバム的な1作で、清々しい印象と共に彼らにとって新しい時代の到来を宣言してみせたような感動がある。特に詞作面で新たな方向性を確立したと言ってもいい"Convertible"やバンド・アンサンブルの力量を感じさせる"Drive"、"Sports Car"といった名曲が生まれた事は特筆すべきものだ。しかし、またもや本作後のツアーでメンバーチェンジが生じる。Weddoesでの活動に嫌気が指したDarren Belkが4月に脱退し、後任にJayne Lockeyと同じTse Tse Flyで活動していたSimon Cleaveが加入する。彼は後にデイヴィッド・ゲッジのソロ・プロジェクト、CINERAMAにも合流し、ソングライティング・チームの一翼を担うなど、音楽的なパートナーとしても重要な鍵を握る事になる。 1996年9月、Cooking Vinyl移籍後初のフルアルバム『Saturnalia』(写真左下)発売。凝ったコード進行ながら独特な疾走感のある"Venus"を皮切りにシャープなリフが効いてる"Real Thing"、マリンバの軽快な音色が光る"Jet Girl"、ポップな方向性が開花した名曲"Montreal"など、バリエーションに富んだ本作は『Watusi』から始まったソング・オリエンテッドな作風とさらに進化を遂げた“Weddoes流”バンド・サウンドが融合。ここまでの紆余曲折や試行錯誤が実を結んだ会心の一作となったと同時に、早くも後のCINERAMA以降を予感させる柔和な雰囲気もある。本作も全英アルバム・チャート最高位36位を記録し、2作連続のTOP 40入りを果たした。 1997年1月、アルバムからのリカットとなる"Montreal"リリース。活動休止前最後のシングルであり、通算17回目の全英トップ40ヒットとなった。 同年1月18日、LiverpoolにあるLomaxでのギグ。このライヴを最後に、THE WEDDING PRESENTは長い長い活動休止期間に入った。なお、この時活動休止宣言はおろか解散宣言もしていないのに、なぜかこの時点であたかも解散したかのような認識があるのだが、当然事実誤認である。“結果として”活動休止期間に入った訳で、この7年と8ヶ月後、CINERAMAから改名する形で2004年9月に始動した新生TWPについても「再結成」「再編成」、ましてや「CINERAMAから復帰」「シーンに復活」などと表現するのは、この歴史を具に追っていけば大きな誤りである事がお分かり頂けるだろう。 1998年:CINERAMA始動~VA VA VOOM 1998年4月19日、David GedgeがCINERAMAの名の下にアルバムを完成させた事が公式声明として発表される。メンバーにはデイヴィッドの他にWeddoesのローディーやマーチャンダイジング部門を担当し、彼の長年の恋人であったSally Murrellが参加している事も明らかにされた。 6月にCINERAMAお披露目となるJohn Peel Sessionが放送され、THE WEDDING PRESENTとは趣の異なるポップなサウンドが大きな話題となる。 7月、記念すべきCINERAMAデビュー・シングル"Kerry Kerry"に続きファースト・アルバム『Va Va Voom』(写真右)がCooking Vinylからリリースされる。CINERAMAの語源であるシネラマ方式の映画に引っかけた“ワイド・スクリーン・ポップス”を標榜し、とにかくWedding Pressentっぽさから離れる事を課題にして制作したというこのアルバムは、デイヴィッドのソングライターとしての才能がシンプルでアクースティックなアレンジのサウンドの上で花開いた、まさしく“ワイド・スクリーン・ポップス”と呼ぶに相応しい色鮮やかで爽やかな1枚だった。相変わらず歌詞の世界は様々な恋愛模様を描いたショート・スケッチだったが、その語り口やストーリー展開の巧妙さはDavid Gedgeという人のユニークさを知らしめるには十分なものである。そして古くからのWeddoesファンはこの時点ではあくまでCINERAMAに対しては「THE WEDDING PRESENT休止中の間の腰掛け的なステージ」として用意された別個のソロ・ユニットとしての認識であり、これが終わればまたTHE WEDDING PRESENTが再開するものだろう…今となってはCINERAMA名義の作品中でも異色な明るさとリラックスした雰囲気があるこのポップ・アルバムは聴く者にそういう期待を抱かせたのだ。 1999年:“ソロ・プロジェクト”から“ロック・バンド”のCINERAMAへ しかし翌1999年1月、The Beautiful Southのサポートとしてヨーロッパを廻ったあたりからCINERAMAはステージ活動を精力的に再開。THE WEDDING PRESENT後期のギターリストだったSimon Cleaveも合流し、着々とライヴバンドとしての場数を増やしていく。また新生TWPにも参加する事になる米ミネアポリス出身の女性ベーシスト/バックコーラスのTerry de Castro、CINERAMAのセカンド・アルバム『Disco Volante』でのドラミングを担当し、その後一度は脱退するものの再び新生TWPのツアーに参加する事になるSimon Pearsonが相次いでGoya Dressから加わるのもこの年のツアーからの事。 一方でTHE WEDDING PRESENTの歴史を総括する様な2作のアンソロジー作品『Singles 1989-1991』『Singles 1995-'97』も発表になる。この頃、デイヴィッドはいくつかのインタビューで「TWPとしても活動したいのは山々だが、今はCINERAMAで新しい作品を作る事に重きを置いている。」という趣旨の発言を繰り返しており、このCINERAMAがどうやら一時的なものでは無さそうだ、という事に否が応でもファンは気付かされる事になる。 またこの年、Cooking VinylがTHE WEDDING PRESENTサイドに無断で制作時期の異なる過去カタログ4枚抱き合わせのボックス・セット『Registry』をアメリカのspinArt社を通じて発売するという背信行為が明らかになり、同レーベルとの契約解除に至った。 2000年:Steve Albiniとの再タッグ~CINERAMA 2nd "DISCO VOLANTE" 翌2000年1月、デイヴィッドがWeddoes初期のReception以来2度目の自主レーベルとなるScopitonesを設立した事が発表され、2月14日のヴァレンタイン・デーには第1弾シングルとして"Manhattan"をリリース。Simon Cleaveが正式メンバーとしてクレジットされたのもこのシングルからの話で、新生TWPまで続くGedge / Cleaveのソングライティング・コンビもここからスタートを切った。 同年3月、昔からのファンが色めき立つニュースが報じられる。あのWeddoesの傑作『Seamonsters』を手がけたSteve Albiniと共にシカゴでスタジオ入りした事が伝えられ、よもやあるとは予想だにしなかったセカンド・アルバムの制作もアナウンスされたからである。 しかしそのセッションからの初音源となった6月のシングル"Wow"は録音自体はアルビニ・エンジニアリングならではのエッヂがあったものの、明らかにCINERAMAならではのエロティックで艶めかしい世界観が同居している独自なものであった。言葉を換えるなら、デイヴィッドが最初の『Va Va Voom』ともWeddoes時代の何かのアルバムとも異なる次元を目指そうとしている事をここで明示したのだと思う。そのシングル発売2日後に行われたJohn Peel Showでのオーディエンスを前にした圧巻のスタジオライヴは語り草となり、多くのファンたちがCINERAMAの活動継続を支持する方向に動き始める。 8月、名曲"Lollobrigida"に続き、9月には待望のセカンド・アルバム『Disco Volante』(写真左)が発売。前作にあった「The Wedding Presentっぽくならないように」などという拘りを一切捨てた所から始まったこのアルバム。『Va Va Voom』がデイヴィッド・ゲッジというシンガーソングライターの“ソロ・プロジェクト”としてのアルバムだったとすれば、本作は幾多のステージでの経験を経てきた新たなロックバンドとしてのCINERAMAのデビュー作、といっていい。タイトなバンド・サウンドをベースに、デイヴィッドが敬愛する映画音楽家たち~アルバム・タイトル『Disco Volante』の由来にもなった007シリーズでおなじみのジョン・バリーにエンニオ・モリコーネからの影響も露わになったオーケストレーションとアレンジメントが絶妙にブレンドされている、そんな新しいCINERAMAの作風がここに確立された。シカゴのSteve Albiniの元でバンド・パートの録音、ロンドンに戻って前作も手がけたDare Masonの元ヴォーカルとストリングスの追加録音とミックス・ダウンを行った本作は性格の異なる対照的な両者の手腕が要所要所で発揮された他に類を見ないサウンド・デザインも見事な統一感に繋がっていて、そこへさらに磨きのかかったデイヴィッドのヴォーカリゼーションとともに隠微なラヴストーリーが綴られる不思議な魅力に溢れた名作である。本作からはさらにシングルが2枚、"Your Charms"、"Superman"がカットされ、結果的に4枚のシングルが生まれる事となった。 2001年~2002年:TWP時代のレパートリーをステージで解禁~3rd "Torino" その"Superman"発売後の2001年4月のツアーで、それまで散々リクエストされても「別のバンドだから」と執拗に演奏する事を拒んできたTHE WEDDING PRESENT時代のナンバーをステージのレパートリーに加える事が発表され、途端に全公演がソールド・アウトになるという大盛況を迎えた。しかしデイヴィッドが敢えて危険を冒してまでWeddoes時代のレパートリーをやる事にしたのか?その理由は自らが自信を持って作り上げたCINERAMAとしての楽曲をより多くのオーディエンスに届けたかったからだ、という意図(曰く「“CINERAMAを毛嫌いする”WEDDING PRESENTのファンたちを引きつける事になって、彼らがライブに足を運んで、これまで見失っていたものを気付く事になるんじゃないかと...。」)があったのは言うまでもないが、 実は同じ頃デイヴィッドが(信じがたい事に母国イギリスでは長年廃盤状態にあった)THE WEDDING PRESENT全盛期の2作『Bizarro』と『Seamonsters』の再発のためのリマスタリングに立ち会った事で、自らの過去の作品をいかに誇りに思えたか、また自らの人生がその作品たちにいかに支配されているか、という事を再認識したからだという。さらに後日明らかになった事だが、実はその2作のリイシューの際にレコード会社側の意向もあってTWP再始動が計画されたものの、1997年の活動停止時の残り2人(ドラマーのSimon SmithとベースのJayne Lockey)から断られて頓挫した、という事も決して無関係ではないだろう。そして『Disco Volante』後に参加したフィンランド出身の若手ドラマーKari PaavolaのパワフルなプレイがかつてのSimon Smithを彷彿とさせるもので、このメンバーでならかつてのレパートリーもステージで出来る、と確信したからではないだろうか、とも想像するのだが。 2001年10月、6分にも及ぶドラマティックな大曲"Health & Efficiency"リリース。翌2002年7月にはサード・アルバム『Torino』(写真右)リリース。シングルになった"Quick, Before It Melts"や"Careless"をはじめ、従来の持ち味はそのままにライヴサーキットの日々で鍛え上げられたギター・ロック・スタイルを巧みに結実させたキャッチーなナンバーを配しつつ、弦楽四重奏をバックに歌われる緊迫感溢れる"Airborne"やノイジーなギターとドライヴィング・ストリングスの対比が鮮やかな"And When She Was Bad"、"Cat Girl Tights"など、前作『Disco Volante』とほぼ同じプロセス(シカゴでSteve Albiniのバンド・パート録音、イギリスでDare Masonの追加録音とミックスダウン)を経ながらも、緩急付けた構成で聴かせるサウンド面での成長が著しい傑作となった。また今作ではギターのSimon Cleaveが大半の楽曲をデイヴィッドと共作したばかりでなくプロデューサー/アレンジャーとしても名を連ね、『Disco Volante』から活動を共にしている女性ベーシストのTerry de Castroがデイヴィッドと共作者としてクレジットされた楽曲も登場し、デイヴィッド以外のメンバーの存在がさらにクローズ・アップされる事にもなった。 その発売記念のツアーとなった2002年7月のイギリス・ツアーを最後にCINERAMA開始当初のパートナーSally Murrellがステージ活動を引退する事になり、ここから新生THE WEDDING PRESENT始動時の核となるメンバー4人~Daivd Gedge、Simon Cleaveの元Weddoesの2人にTerry de Castro、そしてKari Paavolaという布陣での活動が続く。David とSallyは後にプライベートでの関係も解消し、この別れが2004年9月のCINERAMAからTWPへと改名する大きな動機の1つとなり、同時に近作の詞作面に大きなインスピレーションを与える事になったようだ。 2003年~2004年9月:ライヴバンドCINERAMA充実期を経てTWPに改名 その後も最大規模となる北米ツアーも経てますますラウドにアグレッシヴに展開するCINERAMAのステージ・アクトは続き、DavidとSimon Cleaveのソングライティング・チームは次々と新境地を垣間見せる新曲(その多くは新生TWP名義で発表される事になる)をステージ上やレディオ・セッションで披露していく。 2003年7月にはWeddoes時代の問題作『Watusi』も手がけた知古のプロデューサーであるシアトルのSteve Fiskと共にスタジオ入り。ここからの音源がひとまず10月にシングル"Don't Touch That Dial"でリリース。CINERAMA史上最高の名曲の誉れ高いこのシングルはBBC Radio 1のJohn Peel Showで毎年末開催されるリスナーの人気投票"Festive Fifty"においてナンバー1に選出。THE WEDDING PRESENTのデビューシングル"Go Out And Get 'Em Boy!"が1985年に15位に選出されて以来、ほぼ毎年ランクインしてきたもののDavid Gedgeにとっては過去最高位で、実にキャリア18年目にして初の栄冠獲得となった。 翌2004年1月6日には同じくBBC Radio 1のJohn Peel ShowでCINERAMA名義では最後となったJohn Peel Sessionがオンエア。"Always the Quiet One" "Mars Sparkles Down on Me"など後のTWP名義でのフル・アルバム『Take Fountain』に登場する事になる新曲が披露されたこのセッションも同年のTWPへの改名を決意させる自信に繋がったのだという。このセッションは後に編集盤『John Peel Sessions : Season 3』にまとめられた。 引き続きSteve Fiskと共にシアトルで来る新作アルバムの制作を進める一方で大規模なユーロピアン・ツアーやレディオ・セッションも行われる。THE WEDDING PRESENT時代の名曲やCINERAMAで発表してきたナンバーに交え、驚嘆に値する新曲が次々とステージで演奏され、バンドとしてとてつもない充実期にいるCINERAMAの新作にファンの誰もが期待していた2004年9月、センセーショナルなニュースが飛び込んできた。 9月3日に英デジタルTV局Yorkshire TVにて放映されたドキュメンタリー番組「THE WEDDING PRESENT」において現行のCINERAMAのメンバーのままTHE WEDDING PRESENTとして活動していく事を公表。完成したアルバムもTHE WEDDING PRESENT名義で発表される事がDavid自らの口から明らかにされた。 ただしこの改名自体は急に決まったものではなく、同年4月にシアトルで行われたアルバムのための最初のレコーディングに臨むに当たってバンド内で議論の場が持たれ、CINERAMAではなくTHE WEDDING PRESENTの名の下に新作を作る事を既に決定していた。そう、秘密裏のうちに新生TWPは動き始めていたのだ。バンドの本質的な変化を感じ取っていた熱心なファンたちでさえも夢想だにしなかった改名/襲名劇であった。 2004年9月~2005年2月14日:新生TWP正式始動~スタジオ・アルバム『TAKE FOUNTAIN』発表 2004年9月21日、新生THE WEDDING PRESENTとしての初の公式活動となるJohn Peel Showでのレディオ・セッションのオンエア。しかし翌月10月25日、そのJohn Peelが休暇で訪れていたペルーで急逝。長年の友人でもあったデイヴィッド・ゲッジをはじめ、多くのミュージシャンと番組のリスナーたちが別れを惜しんだ。11月には(現時点での)CINERAMA最後のツアーで頻繁にオープニング曲として演奏されていた"Interstate 5"が。2005年1月にCINERAMAのレディオ・セッションやライヴでお馴染みとなっていた名曲"Edinburgh"から改題された"I'm from Further North Than You"がシングルとしてリリース。全英シングルズ・チャート34位初登場という好成績を収めた"I'm from Further North Than You"は1997年1月にリリースされたTWP活動休止前最後のシングルであった"Montreal"以来となる約8年ぶり、通算18回目の全英TOP40入りを果たした。そして2005年2月14日にはTWP名義では『Saturnalia』以来、約8年5ヶ月ぶりとなる待望のフル・アルバム『Take Fountain』(写真左)をついに発表。デイヴィッド・ゲッジがかつて“CINERAMA発祥の地”と呼び、新たな変化を求めた一大転機となった1994年の『Watusi』からほぼ10年。その『Watusi』を仕立て上げた最大の協力者であったSteve Fiskと共に米シアトルで制作された本作はこの10年間の様々な成果と経験を集約しながらも、音楽/詞作的には明らかにCINERAMAのサード・アルバム『Torino』、本アルバムにも再録テイクで収められる事になったシングル"Don't Touch That Dial"以降を示したもので、近年のライヴやレディオ・セッションで目の当たりにした"Always The Quiet One"、"Mars Sparkles Down On Me"、"Perfect Blue"、"Ringway to Seatac"といったGedge/Cleaveコンビ史上最高の部類に入る素晴らしい新曲群が過不足ないアレンジメントで収められている。Scopitonesレーベル通算20作品目のカタログ、そしてTWPの結成/デビュー20周年というあまりに大きい節目に発表されるのに相応しい傑作となった。 2005年2月16日~2006年11月:総公演数178回を数えるツアーに次ぐツアーの日々 『Take Fountain』発表後、2月16日から4月6日まで10カ国41公演にも及ぶ大規模なユーロピアン・ツアーを敢行。アルバム発表と長期間のツアーを目前に控えた中でCINERAMA2000年10月のツアーから正式メンバーとして参加してきたKari Paavolaからイギリス・ウースター出身の若手John Maidenへとドラマーが交代して初めてのツアーだったが、サイモン・クリーヴがデイヴィッド・ゲッジ20年間のキャリアから幅広くチョイスし、"Once More"や"My Favorite Dress"、"Anyone Can Make a Mistake"といったTWP初期のアッパーなレパートリーまでもが演奏されたセットリストと瑞々しいステージ・アクトにファンは狂喜乱舞した。欧州ツアーを終えた後もすぐに4月14日から5月中旬まで続く北米/カナダツアーへと突入。その後も6月から夏の間、歴史あるレディング&リーズ・フェスティヴァルをはじめイギリス、ヨーロッパで行われたいくつかのフェスティヴァルへの出演を果たした(中にはヘッドライナー級の扱いで出演したものもあった)。なおこのフェスツアーからまたもやドラマーが交代。CINERAMAのセカンド・アルバム『Disco Volante』時のドラマーであったSimon Pearsonが復帰している。 そして10月25日から11月26日まで再びフランス~スペイン~U.K.での秋のツアー。ここでもデビュー曲の"Go Out And Get 'Em Boy!"に"A Million Miles"、"Nobody's Twisting Your Arms"といった15年はライヴで演奏されていなかった初期レパートリーにカヴァー・ソングでは初となるレギュラー・セット入りを果たした"Falling"など、度肝を抜くセットリストでファンを魅了した。さらにツアーに合わせてアルバムからのシングル・カットとして"Ringway to Seatac"が発売されている。 実に111公演にも及ぶこの過酷なワールド・ツアーの終盤には過労の為ダウンするなど、体調を崩していたSimon Cleaveはこの年を最後に脱退。2006年はまたもや新たなラインアップ(ライヴのサウンド・エンジニアも担当していたChris McConvilleをギターに、2005年秋の欧州ツアー日程終盤で叩いていたCharles Laytonをドラマーに迎えた)で臨む事になる2月からの北米ツアー(19都市19公演)で幕を開け、4月から6月まで欧州~U.K.ツアー(11カ国34公演)。そのツアー日程に合わせ、5月には『Take Fountain』に関連するシングルとプロモ・クリップをまとめた新生TWP初のコンピレーション『Search For Paradise : Singles 2004-5』がリリースされた。なお、ツアー・ドラマーはChris McConvilleの友人であるGraeme Ramsayを迎え、Kari Paavola脱退以降のツアー・ドラマーとしては4人目となった。 以降、2006年後半はDavid Gedge、Terry de Castro、Christopher McConville、Graeme Ramsayのラインアップでさらに7月のU.Kショート・ツアー(4会場4公演)、11月のフランス~スペイン・ツアー(9会場9公演)を行い、結果この年の公演数は67回に達し、この1年9ヶ月間の総公演数は178回を数えた。11月のツアーではついに『Take Fountain』プロジェクト以降で初めて書かれた新曲も登場し、この長きに渡るライヴ・サーキットを経た次の展開が注目された。 2007年:2種のピール・セッション・ボックス~GEORGE BEST 20周年 しかし、2007年には結局、新作は発表される事は無かった。その代わり、このバンドの歴史上重要な音源がいくつかリリースされる事となった。3月にはBBC Radio 1「John Peel Show」のためにデビュー翌年の1986年から1995年までの9年間に収録された11回のセッション(3回のウクレイニアン特別セットも含む)に再生後の2004年唯一のセッション、さらに同番組で中継された4つのライヴ・セットまで網羅されたCD 6枚組の大作ボックス『The Complete Peel Sessions 1986-2004』が発売。デイヴィッド・ゲッジとジョン・ピールという、お互いがファンである事を公言し、特別な友人でもあったこの両者の信頼関係から生まれた歴史的な記録が惜しげも無く収められたこのボックスは、全ファンが所有しておくべき至宝の一品となった。さらに8月にはCINERAMA時代に残された全ピール・セッションを中心にまとめられた3枚組『The Complete Peel Sessions』、同ボックスから初CD化音源となったDisc 3のみの別売り『John Peel Sessions : Season 3』が同時発売。特に2002年以降、そのまま新生TWPへと生まれ変わる4ピースのギター・バンド編成となり、後にTWP名義で発表される当時の新曲が披露された『John Peel Sessions : Season 3』収録の3回のセッションはCD化が待ち望まれていた重要な音源であった。 10月には1987年の同じ10月に発表されたデビュ-・アルバム『George Best』の20周年を記念したツアーを敢行。当初はそのアルバム発売時にツアーで回った英国内の同じ街とライヴ会場を回る、というコンセプトだったが、最終的には9ヶ国35公演にも及ぶ大規模なツアーに展開。またこのツアーでは同作品をオリジナルLP通りの曲順で完全再現するパートも用意され、近年のツアーで全時代のレパートリーを難なくこなしてきたDavid Gedge、Terry de Castro、Christopher McConville、Graeme Ramsay 4人の絶妙なコンビネーションで嬉々として名曲の数々が演奏されるこのツアーは、サウンド的にはやや貧弱な印象もあった『George Best』を改めて現代にも有効なロック作品として再提示する事に成功したと同時に、当時のバンドの絶好調ぶりも伝えるもので、多くのオーディエンスに大歓迎された。そのツアー開始に合わせて『George Best』の20周年記念エディションが発売されるはずだったものの、権利関係で中止になるという残念なニュースもあったが、自主レーベルのScopitonesからはバンド初期に通信販売とライヴ会場限定で販売されていたオフィシャル・ライヴ・カセットの第1巻と2巻の初CD化となる『Live 1987』が予定通り発売。『George Best』発売前後のステージが2公演分まるまる収められたこの2枚組CDでオリジナルTWPの未完成な、初々しいライヴ演奏がよりクリアな音質で楽しめる事になった。 ツアー終了後、12月には誰しもが黄金時代と認める英RCAレーベル在籍時に残した音源からセレクトされたベスト盤『Ye Ye (The Best of the RCA Years)』が、さらにWEBサイト先行で再生後第一弾となった2005年作『Take Fountain』発売を受けた、長期にわたる過酷なツアーの終盤、2005年11月のロンドン公演のステージをほぼノーカットで収録したライヴ・アルバム『Shepherd's Bush Welcomes The Wedding Present』もリリースされ、2008年2月には同日の映像版となるDVDソフト『An Evening With The Wedding Present』もリリースされた。 2008~09年:『EL REY』~待望の16年ぶりのジャパン・ツアー 2008年、年が明けるとすぐに4人は米シカゴのスタジオElectrical Audioにて、デイヴィッド・ゲッジとテリー・ディ・カストロにとってはCINERAMAの傑作『Torino』以来ほぼ6年ぶりとなるスティーヴ・アルビニとのチームで新作の制作に入った。そのアルバム『El Rey』(写真左)はイギリスでは5月26日に、北米では5月20日にリリースされた。このアルバムを受けて夏以降、バンドは再び英国~北米/カナダ~欧州を回る長期ツアーに旅立つ。10月には同作品を録音したレコーディング・セッションからの未発表曲を含む1,000セット限定生産の4枚組EP BOX『How The West Was Won』を発表。そして2009年3月、日本のファンが16年間待ち続けた2度目となる悲願のジャパン・ツアーが敢行され、『El Rey』ツアーが終了した。そのジャパン・ツアーに先駆け、ギターリストのChristopher McConvilleが脱退し、Simon Cleaveが3年ぶりにバンドへの復帰を果たしている。 その後も4月にはDavid Gedge単独でのBBC Big Bandとの共演によるTWP/CINERAMA楽曲のビッグ・バンド・ジャズ・アレンジでのセルフ・カヴァー・ライヴ、6月にはテリー・ディ・カストロ初のソロ・アルバム『A Casa Verde 2010年:『BIZARRO』21周年記念ツアーで奇跡の2年連続日本公演実現 2009年暮れに、2010年に行う『Bizarro』発売21周年記念ツアーの日程が発表され、日本でも5/7に渋谷O-Westで行われることが決定。奇跡的に実現した2年連続の来日公演は大盛況のうちに幕を閉じた。この貴重なライヴの模様は2011年2月に日本独占リリース作品として『Bizarro : Live in Tokyo 2010』のタイトルで全編CD化されている。またツアーではそのアルバムにも収録された"Deer Caught in the Headlights"、"I Wake Up Screaming", "You're Dead"、後半の欧州、英国では"You Jane"、ダブルドラム編成を活かした"End Credits"など数々の強烈な印象を残す新曲が披露され、今後制作されるであろう新作への期待を抱かせる事になった。なお東京公演後、8月にはCineramaでの初ステージ以来、12年もの間活動を共にしてきたベース&ヴォーカルのテリー・ディ・カストロが自身の活動に専念する為に脱退。後任にはスイス出身のPepe Le Mokoが加入した。 2011~12年:『SEAMONSTERS』21周年記念ツアー、通算9作目『Valentina』発表 2011年は新作を準備する一方で断続的にツアーが行われるが、この年の暮れにはドラマー~ギターリストとして活躍してきたグラエム・ラムゼイが脱退することになった。そのグラエム在籍時最後のアルバムであり、前作から約3年10か月ぶりとなる新作アルバム『Valentina』(写真右)が2012年3月にリリース。AdeleやRed Hot Chilli Peppers、Metallicaの近作のエンジニアとしても有名なAndrew Schepsをミキサーに迎え制作陣と制作環境を一新したことも手伝って、全編新鮮なヴァイブレーションに包まれた、TWP史上最もヴァラエティー豊かな傑作となった。 同月から北米を皮切りに1991年のサード・アルバム『Seamonsters』発売21周年記念ツアーの開催が決定。バンド史上初となるオーストラリア、通算4回目となる日本公演、19年ぶりとなる香港公演も行われた。なお、グラエム・ラムゼイの後任として香港出身でポップ・グループThe Pippetsのサポートとしても活動していたパトリック・アレクサンダーを新しいギターリストに迎えている。一方で『Valentina』でも大きな存在感を示していたベース&バックコーラスのPepe Le Mokoは同年末にはバンドを脱退している。 2013年~2014年:『The Hit Parade』全A面曲再現ツアー~新曲リリース~再発プロジェクト 2013年もツアーサーキットは続く。北米、オーストラリア、バンド史上初のニュージランド公演を挟み、前回の来日から1年を待たずして通算5回目の来日公演が実現。今回のツアーは、2007年に実施した発売20周年記念ツアー以来となる自身2度目となる『George Best』LP全編再現、そしてシリーズ完結20年目となる1992年の月刊7インチ・ヴァイナル・シングルシリーズ『The Hit Parade』シリーズの全A面曲を発表順に再現するパートが用意されたツアーの一貫として行われた。この年の夏以降のツアーから、新たにKatharine Wallingerをベース&バックコーラスに迎え、9月からはその『The Hit Parade』全A面曲再現パートを核としたセットリストで欧州、英国をツアー。10月にはステージでも話題になっていた新曲"Two Bridges"を英ツアー会場限定販売の7インチ盤としてリリース。同月には『Bizarro : Live in Tokyo 2010』でライヴ・テイクが聴けた"I Wake Up Screaming"の新録スタジオ・テイクをCinerama名義の7インチ盤として発表。同名義では実に9年4ヶ月ぶりとなるシングルとなった。さらに2014年9月には同シングルを含む未アルバム化の6タイトルのシングルを含むコンピレーション『Seven Wonders of the World』をリリース。2014年10月には英Edselより、1996年までの旧TWP時代の全アルバム8カタログをボーナスDVDが付属した4枚組のエクスパンディッド・エディションとして再発(写真左)。かつては権利関係から自嘲的に“失われたアルバム”とまで紹介されていた1994年作『Watusi』は発売後20年を経て初のリマスタリングの上、遂に再発。初期TWPのキャリアを総括する一大プロジェクトとして大きな注目を集めることとなった。また11月にはその『Watusi』発売20周年記念ツアーをイングランド、アイルランド、フランス、ベルギーの4カ国で敢行した。 2015年~2016年:Cinerama版『Valentina』~David Gedgeキャリア史上最高傑作『Going, Going...』 TWPとしてのデビュー30周年を迎えた2015年はまた新たな転換点を迎えることになった。1つは2015年5月に発表されたCinerama版『Valentina』(写真右)。TWPとして2012年3月に発表した『Valentina』全編を、シネラマとして完全リアレンジの上再録音した作品である。その性格、背景からして企画色が濃い作品ではあるが、同作から派生した外国語詞版の別テイクの限定EPとは全く意図が異なる。実際に姿を現したのは、元来のグループ名が醸す映画音楽的なポップ・ミュージック。ストリングス、ホーン・サウンドも全面に押し出しながらも、このユニットの過去の作品にはないニュアンスに富んだアレンジメント、オーケストレーションが施され、まさしくデイヴィッド・ゲッジがこのユニット開始当初に掲げたキャッチフレーズ「ワイド・スクリーン・ポップス」が具現化されたかの様な会心の一作となった。共同プロデューサー、アレンジャーとしてスペイン・アストゥリアス在住のアーティストPedro Vigil(元PENELOPE TRIP、EDWIN MOSES)が知古のミュージシャンたちを配して全面的に作り上げた大胆なリアレンジ・トラックの上で、デイヴィッド・ゲッジがヴォーカリストに徹しているのも功を奏していて(元バンドメイトのTerry de Castroがバックコーラスで全面参加し、1曲でリード・ヴォーカルを務める)、単なるリメイクでもリミックスでもない、1つ作品を全く別の角度から楽しめる出来映えとなっている。いきなりボサノヴァ調から始まり、スタイル・カウンシルばりの80's ポップや、さらには50年代のショーロサウンドにも聴こえてくるSP盤の様な処理のインストまでの振り幅の広さと意外性に、時に思わずのけぞりながらも楽しめてしまうから不思議だ。このめくるめく音世界をストリングス、ホーン・セクションを含めた16名余の大編成でステージ上の実演でも再現してみせた同年のツアーからの『LIVE 2015』を合わせて聴くことで、ある意味ではデイヴィッド・ゲッジがこの名義で開始当初に志したものを、15年あまりの時を経てようやく実現できたのではないかと実感する。この名義でまだやり残したこと、様々な経験を経なくてはできなかった表現(本人も認めている通り、BBC Big Bandとの共演でTWP時代の代表曲をビック・バンド・ジャズ・アレンジで歌った2009年4月の英リーズFuseleedsフェスティヴァルのステージは実に大きいものだった)を、Pedro Vigilという音楽的な触媒の力も用いながら一度やり切ってみた結果を記録として残したかった。タイミング的にTWPとしての次作スタジオ作品に取りかかっていた時期に本作のリリースに踏み切ったのはそんな明確な意思があったはずだ。そう、これがエンドロールだとしても何の疑問の余地もない。それほどの特別な聴後感を覚える1枚である。 そしてキャリア31年目を迎えた2016年9月、『Going, Going...』(写真左)発表。デイヴィッド・ゲッジが妻でフォトグラファー、ローディーとしても長年サポートを続けているジェシカ・マクミランと共に、北米20州を股に掛けたロード・トリップで横断した際に訪れた街の名前を関した20曲を、旅のルートに沿って配置した全長78分にも及ぶバンド史上最長の大作。ジェシカ・マクミランが撮影、監督した楽曲に呼応した20編のショート・フィルムを収めたDVDもセットにした、コンセプト・アルバム的な構成の作品でありながら、デイヴィッド・ゲッジ31年間のキャリアの中で培ってきた音楽的な自己蓄積の賜物と呼びたい、稀代の傑作である。冒頭からインストゥルメンタル主体の4曲を配するなど、実験的なアプローチも取り入れつつも、ある種神懸かり的な整合性の高さが圧倒的。シングルとしても通用しそうな楽曲が目白押しで、あらゆる意味で全編一切の出し惜しみが無い。『Valentina』ではミックスダウンを担当したAndrew Schepsが本作では録音から全面的に共同プロデュースに携わっているのも大きなポイントで、TWP特有のポップネス、メロウネスを残しながら、ライヴでのTWPらしさを容易に思い出させるエネルギー溢れるバンドサウンドを際立たせた全体のサウンディングも見事すぎる1作となった。 2017年~2018年:Steve Albini再録音版『George Best 30』発表~『Tommy』30ツアー 2017年4月、『Going, Going...』で特に達成感があったというインストゥルメンタルへの取り組みを1枚のEPに拡大した初のインストゥルメンタル主体のEP『The Home Internationals EP』を発表。たとえインスト主体であってもなおTWPの意匠が感じられる楽曲とそれを支えるアンサンブルの屈強さは健在で、見事なまでに『Going, Going...』以降の新たな境地を見せることになった傑作となった。 またこの年、デビュー・アルバム『George Best』の発売30周年となり、自身3度目にして最後と称した同作の全曲再現ツアーを敢行。それに合わせて半ば都市伝説と化していた作品が発表されることになった。2018年1月にSteve Albiniの元『El Rey』に収録されるマテリアルを録音していた米シカゴのElectrical Audioで、全17曲が録音されたという『El Rey』のレコーディング・セッションが全て終了した後、空き時間を利用してあるスタジオ・ライヴ音源が記録されることになった。前年2017年10月に行なわれたデビュー作『George Best』発売20周年を記念した全曲再現ツアーさながらに、ほぼ一発録音で『George Best』全12曲を再録音したのである。 その録音から9年を経た2017年に『Valentina』『Going, Going...』でタッグを組んだAndrew Schepsが最終的なミックスダウンを手がけた作品が『George Best 30』(写真右)として遂に発表されることになったのだ。『El Rey』当時の若手メンバーの溌剌としたプレイも影響し、また原作と異なり生ドラムで演奏されている文字通りの意味でのライヴ感溢れる音像と共に鮮烈な印象を残す、単なる企画作と侮れない1作である。 翌年2018年には初期コンピレーション『Tommy』の発売30周年を記念したツアー日程も発表され、Terry de Castroがおよそ10年ぶりに一時的な形ではあったがステージに復帰。4月には5年ぶり6回目のジャパン・ツアー、初の台湾、フィリピン、タイ公演を含むエイジアン・ツアーも敢行された。特に東京TSUTAYA O-nestの4月11日・12日の連日公演は語り草となるレア選曲と強力な"Brassneck"、"Kennedy"、"Take Me!"の奇跡の三連打となった熱演と共に、多くのファン達の記憶に刻まれることになった。 2019年~2021年:Brit-Pop Super Group化~COVID-19のロックダウン中での活動 TWP/CINERAMA双方のステージでサポートしてきたMelanie Howardがベーシストとして正式メンバーとなり、2019年7月には通算7回目となる来日公演も大盛況のうちに終了。同時に会場では1988年のコンピレーションの再録版『Tommy 30』、ライヴでも好評を博していた新曲"Panama"を含むシングル「Jump In, The Water's Fine」も先行して発売された。その年の暮れに2005年から14年間在籍してきたドラマーCharles LaytonとギターリストDanielle Wadeyが産休に入り、そのまま脱退。SleeperのギターリストJon StewartとMy Life StoryのドラマーChris Hardwickが替わりに加入。90年代半ばの英国音楽シーンを賑わせたバンドからの加入ということもあり、メディアから"Brit-Pop Super Group"と評されることもあったこのラインアップでのライヴも大きな話題になったが、TWPに限らず、音楽産業に携わる全ての関係者に大打撃を与える出来事が起きたのはご存知の通り。2020年初頭から始まった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な大流行であった。TWPも他の多くのバンド同様に、その影響を被ることになり、予定されていたライヴやイベントは悉く延期または中止の憂き目に遭った。 そんなCOVID-19に伴うイングランド国内でのロックダウン中、活動もままならない苦境にあっても、ベース&バック・ヴォーカルのMelanie HowardはSuch Small Hands名義で初のソロ・アルバム『Carousel』を、007映画の主題歌、挿入曲をTWP/CINERAMAの現/元メンバーたちや、関連するバンド/アーティストたちがカヴァーしたThe Wedding Present & Friends名義の2枚組企画作『Not From Where I'm Standing』など、関連するスタジオ作の発表。オンライン上では初の有償ライヴやDavid Gedgeの英ブライトンの自宅から配信イベントなど、世界中のファン達に途切れることなく娯楽を提供し続けた。 その一連のロックダウン中の活動の中でも特に好評を得たのが公式YouTubeチャンネルWedding PresentTV内で続々公開された、"Locked Down & Stripped Back"と題されたシリーズ。この時点でのバンドメンバー4人と盟友Terry de Castroが、ロックダウン中だったそれぞれの自宅で録音・撮影したセミアクースティック編成によるヴァーチャル(リモート)・セッションを収めたもので、この時期多くのバンド、アーティストが同様の企画を行なっていたが、自宅録音ならではのリラックスした空気感もありながら、とてもバラバラに録られたものとは思えないくらい、TWPならではの絶品のバンド・グルーヴが感じられる雰囲気がとにかく素晴らしく、すぐに多くのファンからフィジカル化の要望が上がった。そんな大多数のリクエストに応えたカタログが2021年2月に『Locked Down And Stripped Back』(写真左)としてまとめられることになった。また本作の続編も『Locked Down And Stripped Back Volume Two』として翌年7月に発表。ここでもオリジナル盤のバック・コーラスとして参加していたAmelia Fletherとのデュエットとして再現された"Nobody's Twisting Your Arm"など、聴き所の多い1作となった 2022年~2023年:30年ぶりの月刊シングル・シリーズ『24 Songs』 そんなLocked Down And Stripped Backシリーズ中や、度重なるオンライン配信ライヴで積極的に新曲を披露して行く中、2021年10月14日、各公式SNSでまたもやファンが狂喜乱舞するニュースが発表される。『The Hit Parade』敢行から30周年となる2022年にキャリア2度目となる月刊シングル・シリーズ『24 Songs』を展開することを明かしたのだ。毎月第三金曜日に各2,400枚の限定プレスで発表されたこのシリーズ。前回の『The Hit Parade』がA面新曲/B面カヴァーというコンセプトだったのが、今回は特に縛りはなく、文字通り24曲の現在進行形のTWPを顕した楽曲が収められ、Sleeperと掛け持ちする形で正式加入したJon Stewart、自らメインヴォーカルを務める楽曲も提供したMelanie Howard、そしてDavid Gedgeという三者三様のソングライターの個性が融合しながら、新たなWeddoesグルーヴを完成させた様な趣がある。 そのシリーズ24曲は3枚組LP『24 Songs : The Album』(写真右)として5月19日ついにアルバム化され、コロナ禍以来の本格的なツアー活動も再開される。(last modified : 5th May, 2023) |
| △TOP |
TWP-CINERAMA[dbjp] is not responsible for the content of external sites.
© TWP-CINERAMA[dbjp] All rights reserved by Yoshiaki Nonaka except where noted.



















