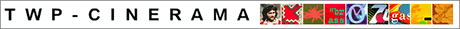24 Songs Tracks: *Full length version
Side A -- I Am Not Going To Fall In Love With You*
- Memento Mori
- That Would Only Happen In A Movie
- We Interrupt Our Programme*
Side-B- We Should Be Together
- Strike!
- Science Fiction*
- Summer
- Each Time You Open Your Eyes*
Side-C- We All Came From The Sea
- Monochrome*
- Kerplunk!
- Don't Give Up Without A Fight
- X Marks The Spot
Side-D- You're Just A Habit That I'm Trying To Break
- Plot Twist
- Whodunnit*
- A Song From Under The Floorboards
- Telemark*
Side-E- Astronomic
- Go Go Go
- Once Bitten
- La La La
- The Loneliest Time Of Year*
5 Songs (Bonus Tracks):Side-F- White Riot
- Panama
- Jump In, The Water's Fine (Japanese Edit)
- We All Came From The Sea (Utah Saints Remix)
- Teper My Hovorymo (Featuring Peter Solowka)
SAMPLES
作品概要/解説 アルバム『24 Songs』をコンパイルすることになったとき、トラックを時系列順に並べないことに決めたんだ。レコードが6面あれば、6つの「始まり」と6つの「終わり」を再生することになるわけで、ある種の音楽の旅を構築するこの機会を逃すのは惜しいと思ったんだよ!今回のコレクションを聴き返してみると、このプロジェクトのためにウェディング・プレゼントは自分たちの歴史の中で最高の曲を録音したと心から思える。シングルをリリースするのも好きだったけど、今回全部まとめてリリースできて満足しているよ。(David Gedge/本作のDeluxe CD版ブックレットから)
2022年、それはThe Wedding Present(以下TWPに省略)の古くからのファン達にとって永遠に忘れることができないあの『The Hit Parade』シリーズから記念すべき30周年という年であった。毎月15,000枚の限定プレスで、A面オリジナル、B面カヴァー曲の組み合わせの7インチ・シングル・シリーズをリリースしていくというそのプロジェクトは、創作的なピークと商業的なピークが同時に訪れたといっていい大成功を収め、そのシリーズで発表されたオリジナルの全12曲は後年のステージでも度々演奏されるクラシックになった。
これまでも他の『The Hit Parade』シリーズ以前の作品について、20周年や30周年など節目の年にリマスター版やデラックス版をリリースしてきた経緯があったので、おそらく似た様な企画はあるのだろうと2021年に入った段階で予測していたのだが、筆者はSNS上でDavid Gedgeのアカウントに対して「来年The Hit Paradeのシーズン2をやろうぜ!」なんて呼びかけたりしたのだった。まんざら冗談でもなく、タイミング的にコロナ禍がまだ終息していない時期でもあり、腰を据えてアルバムを作れるような状況でもなかっただろうし、とは言え繰り返し行なわれてきたオンライン配信イベントや無観客ライヴでは次々とバンドが新しい扉を開けたかの様な新曲を惜しみなく披露していたので、これらの楽曲をシングルの連続リリースのような企画で発表していくのであれば絶対に歓迎されるだろうとも思ったからだった(あの1992年をリアルタイムで過ごしたファンなら尚更だ)。
上記のメッセージを残してから半年ほど経った2021年10月のある日のこと。David Gedge本人から「来週ある企画を発表するけど、前もって調べてリークしないようにね!」とメッセージが届いて、まさか!と思っていたところに10月14日、公式発表されたのが30年ぶりの“シーズン2”となった月刊シングル・シリーズ『24 Songs』プロジェクトのこと。今回は毎月第3金曜日に、(タイトルにも引っ掛けて)2,400枚の限定プレスでのリリース。発表同日から全12枚の定期購入を含めた販売が開始されたのだった。余談だがこの情報の最速でのリークは、その公式発表の前日。この件に触れたDavidのインタビュー記事が載った10/14発売の英音楽誌UNCUTの2021年11月号で、同誌の定期購読者には1日早く届けられた結果、手にした他のファンによってスキャンされたページがSNS上で拡散されることになった。この時代、アーティスト側がどう警戒したって秘密は漏れてしまうようだ(そう言えば2023年に突如発表されたBlurの『The Ballad of Darren』の様な、公式発表のニュースまで一度たりとも情報が外部に漏れなかった稀有な例もあったが)。
それにしても、この発表に興奮しないわけには行かなかった。筆者も即決で(とは言え、当時のレートで収納カートン・ボックス付き送料込み34,000円はやや清水の舞台から何とやら、の心境にもなったが)年間定期購入版を注文。おそらく同じ様な行動に移しただろう世界中のファン達も、SNS上のコミュニティではこのプロジェクトのことに話題は持ち切りとなり、すでにライヴやオンライン配信ライヴでは演奏されてきた、スタジオ録音では未発表のどの曲が、何月号で発表されるのか?の予想合戦もスタートした。
第1弾の1曲は前もってプレスリリースの段階で明かされていた。毎夏8月に開催されていたDavid Gedge主催の音楽フェス『At the Edge of the Sea』がコロナ禍の影響で開催を中止した2020年、ロックダウン中の代替版イベントでオンライン・フェスとして開催された「At the Edge of the Sofa」の中でも披露された"We Should Be Together"。前年暮れから正式加入したJon Stewartのもう1つのバンド、Sleeperの未発表曲を、そのSleeperのLouise Wenerをフィーチャーしたデュエットとしてカヴァーしたもの。
そう、今回の『24 Songs』はそのスタート地点からして前回のシングル・シリーズとは違っていた。A面オリジナル、B面カヴァー曲の組み合わせ、という縛りもなく、そもそもどちらがA面、B面ということでもなかった。その段階での新しいレパートリーをスタジオ録音版で発表していく...名は体を表すかのようにシンプルに『24 Songs』と名付けられたのも象徴的だった。ただ本プロジェクト発表の段階ではそもそも全12枚の半分に収まるくらいのストックしか無かったはずで、シリーズの後半にかけてはコロナ禍に3回行なわれたオンライン配信ライヴでも演奏されていない、まっさらの新曲も登場していくことになった。
その12枚24曲に加え、このシリーズ以前に2018~19年にかけシングルとして発表されていた3曲、僅数プレスのチャリティー・シングルのみに収められたリミックス版やこのアルバムで初登場となった、オリジナル・メンバーである初代ギターリストPeter Solowkaをギターにフィーチャーしたカヴァーを含む5曲をボーナストラックとして収録したのが本作となる。英国版は同シングル・シリーズのリリース元であり、当時英EMIレコーズがイングランド北部を拠点とするレーベルとして新設したEMI Northのパートナー企業に選ばれたことで話題になった英リーズのClue Recordsから5/19にリリース。追って北米版もTWP/CINERAMA関連の近年の作品をリリースしているアセンズのインディーズHHBTM Recordsからリリースされた(余談だが公式な北米版の発売日は6/9となっているが、実際にはLPの生産工程の遅れにより、出荷自体はレーベルのBandcampページに公開された7/21からだったようだ)。
最初の月刊7インチ・シリーズであった1992年の『The Hit Parade』のコンピレーションはいろいろなヴァリエーションで発売されたが、どれも基本的には発表順で収録されていた。対して今回は単なるコンピレーションというよりは、新曲で構成されたアルバムとして聴けるように、発表順には拘らない形で曲順は構成されていて、さらにシングルでは非常にファン泣かせの、これから盛り上がるだろう肝心な場面でフェード・アウトで処理されていた楽曲(収録曲末尾*印)は全て、エンディングまで聴かせる全長版で収録されている。冒頭のDavid Gedgeのコメントにある通り、LPでの再生を意識して構成されていることは間違いなく、まさに「6つの始まりと終わりを旅する」音楽的な旅を味わえる作品になっていると思う。
一方で、これは2020年から2022年にかけての、全ての方が忘れられないだろう異様な時期を共に過ごし、育ってきた楽曲群であるような愛おしさを感じる。今のバンドメンバーが全て現在の拠点のブライトン在住である事により創作意欲が高まったこともあるだろうが、コロナ禍の予期せぬ事態に苛まれた中でもTWPはその歩みを止めなかったこと、そしてオンラインの形であっても次々に披露し続けてきたこと...まるで曲が生まれた瞬間に立ち会えたかの様な感覚がそこにはあり、またそれらの新曲や新しいレパートリーは、あの息が詰まりそうな閉塞感が続く日々の中で、少なくとも自分にとっては、大袈裟かもしれないが生きる希望となった。オンラインの公式動画や、この『24 Songs』に収められた楽曲がいち早く披露されたヴァーチャル・リモート・セッションのシリーズ『Locked Down And Stripped Back』などで繰り返し、繰り返し再生する中で、いつの日かこれらの楽曲が手元に届き、ターンテーブルで再生し、そしてまたライヴの場で体験することができるだろう。かつては当たり前だったことが現実となることをこれほど渇望したことはなかったと思う。ごく個人的には30年前の『The Hit Parade』シリーズの時とは、その過ごして来た日々の状況の違いも含め、同じシングル・シリーズでも全く違う意味を持つこととなった。
こうやってまとまった形で聴ける様になった今、客観的に聴いても、この新たな楽曲集がDavid本人が言う「TWP史上でも最高の楽曲」が聴けるアルバムの1つとなったことに異論は無い。かつてのTWPのレガシーと、David Gedgeのキャリア上の分岐点となった1998年のCinerama以降の様々な音楽的な成果が、現在のTWPにおけるキーパーソンとなった2人のミュージシャンを含む、三者三様のソングライターの個性と結びついて、どの曲も現在進行形のTWPとしか呼びようがないものに仕上がっていて、その完成度の高さには(毎度のことながら)圧倒される。プロデビュー前には『Bizarro』を愛聴し、その後デビューしてからはあのBrit Popの狂騒の時代を駆け抜け、イングランドではTWPより遥かに多くの売り上げを誇ったSleeperのJon Stewertはそのヒットメーカーとしての経験を活かした様々なアイディアと現代的なエッジを持ち込み、自らのユニットSuch Small Hands名義でも秀逸な作品を発表しているベース&ヴォーカルのMelanie Howardはその独特なメランコリックなテイストを残すメロディとハーモニーで彩りを添える。特にプロジェクトの進行と共に制作されたシリーズ後半の楽曲群は三人の個性が完全に融合したかのような、それまでのTWP名義の作品には無かった新たな方向性が示されているのは明らかで、今回のLPの曲順がアーティスト側の意向であることは理解するが、サブスクリプション・サービスのプレイリストでもいいので、発表順に並び替えて聴いていただけるとその進化の過程が味わえると思う。ぜひともお試しいただきたい。
曲目解説
本アルバムは4種類のフォーマットで発売されている。Super-Deluxe Limited-Edition Triple LPは透明グリーンの3枚組LPにCD2枚とボーナス DVDのセットで500セット限定生産(型番CLUE124LPD)。Deluxe Triple LPはグレーの3枚組LPにCD2枚とボーナス DVDのセット(型番CLUE124LPG)。CDも2種のフォーマットが用意されていて、Deluxe Double CD ‘Bookpack’は本型のパッケージでCD2枚とボーナス DVDのセット(型番CLUE124CDD)。最後がDVDが付属しない通常の2枚組CD盤(型番CLUE124CD)。
今回大変不親切だと思ったのが、歌詞やDavid GedgeのライナーノーツはBookpackのCLUE124CDDを購入しないと付いてこない。ただでさえ円安や原材料の高騰などにより、フィジカル版として気安く購入できない状況下(イングランド版かつアナログ盤に拘るのであれば1万円超えは覚悟しないとならない)ではあるが、それにしても一番高価な3枚組LP、2枚組CD、DVDのセットを入手しても本作を味わう上で欠かせない歌詞や、作品を理解する上でのサブテキストとなるDavidのコメントが入手できないのは呆れてしまう。メーカー側に猛省を促したい。このアルバムからTWPの世界に触れるファンがいること(ぜひそういうリスナーがいて欲しいが)を考慮すると、せめてDVDの付いていないCD版は安価な価格設定で、かつ歌詞やライナーノーツが付いた体裁でリリースして欲しかったものだが。いずれにしても、ここではアーティスト側が理想型として提示した3枚組LP版に準じて簡単に紹介していきたい。
A1. I Am Not Going To Fall In Love With You
2月号で発表。実は『24 Songs』の発売予告の動画でもバックグラウンドに流れていたもので、今回のシリーズではいち早く録音されていた楽曲だった。初披露は2021年5月20日に配信された3回目となるオンライン有償ライヴの終盤。その際にも「次のシングル候補」とコメントしており、聴いたその日から発売を切望してしまうほど強烈なインパクトを残した。あまりにもらしい初期楽曲っぽいタイトル、エンディングにかけての激しいインタープレイも含め「クラシックなWedding Presentが脈々と流れている」とのDavidのコメント通り「これぞ超王道のTWP」と思わせた1曲だった。メインパートはJon Stewartとの共作で、TWP初期作品の大ファンだったJon Stewart(ちなみにマンチェスター大学を1988年に卒業後、Sleeperを結成したのは1992年のこと)のアイディアが強く反映されているようで、「まるでBizarroとThe Hit Paradeのエッセンスを蒸留した瓶からこの曲を思いついたかのようだ!(笑)」とのDavidの評価にも頷けるものがある。個人的には今回のスタジオ録音で追加されたオープニングのエフェクトが、まるで映画館で本編上映前に流れるDolby Cinemaのクレジットの時に流れるSEのようで、これから旅が始まるワクワクする様な高揚感を煽ってくる。80年代には"My Favourite Dress"、"Brassneck"、90年代には"Corduroy"や"Come Play With Me"、2000年代には"Interstete 5"、"I'm From Further North Than You"、2010年代には"Deer Caught in the Headlights"や"Bear"が...各時代にキャリアを代表する楽曲を産み出して来たTWPだったが、この曲が2020年代の堂々の代表曲になることは疑いようがない。
A2. Memento Mori
12月号で発表。元々2022年4月の英国ツアーでは披露されていた1曲。タイトルは偶然にも本アルバムと同時期に発表されたDepeche Modeのアルバム・タイトルや、日本でも著名な写真家やバンドの作品、ゲームアプリに冠せられるほど、昔から表現のモチーフとしてはあまりにも使い古されたラテン語の警句(「人に必ず訪れる死を忘れるな」)。しかし「世界は君を待ってくれない/君は行動しなければならない/ここから山は見えるが/それほど高くない様に見える」といったどちらかというと希望に満ちた歌詞からは、このタイトルから連想される死の匂いや気配みたいなもは感じさせない。思わず胸に迫るコーダの展開も、本シリーズの文字通りのエンド・ロールの様でもあった。しかしアルバムの2曲目のポジションに置かれることで、上記とはまるで違った印象となった。全24曲が出揃った段階で、SNSのコミュニティ上で今度はアルバムでの収録順予想合戦が始まって、筆者も個人的に複数パターンのプレイリストを作成したりしたのだが、1曲目はどうしたって上記の本シリーズを代表する"I Am Not Going To Fall In Love With You"しかないだろうし、エンディングはクリスマス・ソングの"The The Lonelist Time Of Year"だろうと思った。それは予想通りだったのだが、今回曲の配置としては全く予想がつかなかったのがこの曲だった。しかし、このアルバムの流れの中ではこのポジションが大正解だと、繰り返し聴く中で確信するに至った。アルバム冒頭のテンポ作りの中で重要な鍵を握る1曲になったと思う。なお、歌詞に歌われた山とはワシントン州の雪をかぶったカスケード山脈とのことで、クリスマス・ソングだったカップリングの"The The Lonelist Time Of Year"と呼応するような冬の歌。
A3. That Would Only Happen In A Movie
8月号で発表。このシングルが発売された同じ年2022年7月にフィジカル化されたばかりだった『Locked Down And Stripped Back Volume Two』にも収録されている、2021年8月のオンライン・フェス「Still At The Edge Of The Sofa」内で初披露された当時の新曲のスタジオ・テイク。Locked Down版ではストリングスが入るのかもしれないと思わせたキーボードが入っていた後半部はエレクトリック・バンド主体のアレンジになったが、Locked Down版で感じられたこの曲本来の愛らしさは変わらない。いずれもCinerama以降のTWPの楽曲群に感じられる共通点と呼んだらいいのか、聴き始めるとどうにも止まらなくなる、このバンドでしか味わえない魅力、エッセンスが凝縮されている。
A4. We Interrupt Our Programme
7月号で発表。2022年1月22日に行なわれた『24 Songs』シリーズ開始を記念したライヴ中(本作のボーナスDVDにも収録)でも演奏されたナンバー。イントロからDavidのボトルネック・プレイが唸りを上げるアッパー・チューンで、David曰く"70年代のグラム・ロックマナー"の1曲とのことだが、かつての何かを想起させない、まさに現在進行形のTWPを見せつける逸品と言っていい。このアルバム・ヴァージョンではエンディングにかけ爆発的に盛り上がる場面までフルサイズで聴かせる。ライヴでの実演が楽しみすぎる1曲。
B1. We Should Be Together
本シリーズ幕開けを飾った1月号で発表。前述の通り、元々は2019年暮れから加入したギターリストJon Stewartのもう1つのバンドSleeperの未発表曲だったもの。デモをDavid Gedgeに聴かせたところ、気に入ったことから加入当時のツアーでMelanie Howardとのデュエットで初披露。その後、2020年のCOVID-19の世界的流行に伴う最初のイングランド内のロックダウンの最中、当時のバンドメンバー4人と盟友のTerry de Castroがそれぞれの自宅で録音・撮影したセミアクースティック編成によるヴァーチャル・セッション・シリーズ『Locked Down and Stripped Back』の中でも披露されたが、そのテイクでもフィーチャーされたSleeperのLouise Wenerが今回も客演し正規のスタジオ録音版として再録された。セッション・テイクよりほんの少しだけテンポアップされたが、個人的にはヴォーカルの出来が先のセッション・テイクの方がメンバー各自の自宅録音ならではのリラックスした雰囲気とポップな曲調との相乗効果もあって良かった気がするが、この辺は好みが分かれるところか。ちなみにSleeper版も2020年12月に『This Time Tomorrow(The Lost Album)』で陽の目を見たが、Louiseには申し訳ないが、もはやこのTWPのデュエット版の方が本家本元版と呼びたいくらいに、完璧なポップ・ソングとしての完成形を示しているように思う。それにしてもレコーディング当時お蔵入りさせたのがもったいないくらいの名曲。
ちなみにLouiseが公式Twitterで明かしたのだが歌詞には逸話があり、「元々は(アルバムのプロデューサーだった)Stephen Streetの40回目の誕生日パーティーの後に書かれたもので、歌詞の"Where do you belong, when the grey skies turn you on...."のラインはその時に交わした故Terry Hall(The Specials/Fun Boy Three etc...)との会話にインスパイアされたもの」とのこと。
B2. Strike!
5月号で発表。本シリーズでは最も古いレパートリーで実は2019年7月の来日公演でも当時の新曲として演奏され、同年のBBC 6 MusicのShaun Keavenyのプログラムでのレディオ・セッション音源『Shaun Keaveny Session』でも7インチ化されたナンバー"Don't Ask Me"の改題。ファンにはすっかりおなじみの1曲だったが、このスタジオ・テイクではライヴやセッション音源の時からバック・コーラスのアレンジが変わって、Davidのヴォーカルが前面に出て、さらに疾走感のある仕上がりになった。もしコロナ禍が無ければこの曲をトップにしたスタジオ・アルバムが実現していたのでは、と何度も夢想したのだが、アルバム中のこんな地味なポジションに収まるような曲ではないだろうに。まあ、それだけ本シリーズは野球で言うと4番バッター・クラスの粒選りの楽曲が揃ってしまったのだが。
B3. Science Fiction
シリーズ終盤11月号で登場。2022年4月の英国ツアーでは披露されていたもの。バンド史上でも最も美しいラインを持つ悲恋の歌。30年前の『The Hit Parade』シリーズでも本シリーズでも共通してSF的モチーフが歌われた楽曲があり、『The Hit Parade』では"Flying Saucer"、"The Queen Of Outer Space"、本シリーズでは10月号の"Astronomic"、そしてこの曲。この曲に至ってはタイトルからしてS.F.である。ある意味Davidお得意の作風とも言えるが、何と言っても悲恋のストーリーにあまりにもマッチし過ぎている狂おしくも切ないメロディが堪らない。「僕たちは別れたけど、かつてのように、今でも毎日君の名前を呼んでしまう/君のことを考えないようにするためなら、何だって、何だってするよ」にどうしたって胸が締め付けられる。この曲もコーダまで完全な形で聴けるようになったアルバム・ヴァージョン。ちなみに本アルバム発売に合わせて行なわれた2023年5月の英国ツアーでは、この曲のエンディングと同じコードで始まる、1989年の『Bizarro』収録曲の"No"とメドレーで演奏される場面も見られた。
B4. Summer
9月号で発表。本シリーズ展開中の2022年に3年ぶりの開催となった恒例のフェスティヴァル『At the Edge of the Sea』のステージで初披露され、好評を博した1曲。挑戦的なスタイルのカップリング"We All Came From The Sea"とは打って変わったオーセンティックなギター・ロック、と思わせておいて、終盤のブレイク後の展開はいかにもTWPならでは。『At the Edge of the Sea』の会場周辺の雰囲気(ブライトンの海沿いに面したヴェニューで開催されている)も想起させるような、夏の終わりを感じさせる切ない歌メロも耳を惹く逸品。
B5. Each Time You Open Your Eyes
8月号で発表。本作のボーナスDVDにも収録された2022年1月22日に行なわれた『24 Songs』シリーズ開始を記念したライヴ中でも演奏されたナンバー。真夏のプールの水面の揺らめきを思わせる様な冒頭の美しいギターのアルペイジオとメロディ。コーラスの重厚なギターリフで場面転換して盛り上げて行く展開。シングルではまさにこれからというところでフェードアウトしていたが、もちろんここではブレイク後の至高の大エンディングまで完奏するアルバム・ヴァージョン。TWPの真骨頂が表れた本シリーズでも屈指のナンバーと呼びたい。LP1の旅はここで終わりを迎える。
C1. We All Came From The Sea
LP2の幕開けは9月号で発表されたこの問題作。当時ライヴでも未発表だったナンバーで、Sleeperと掛け持ちする形で加入したJon Stewartが主導権を握った1曲。本シリーズ、いやTWP史上でもかなり異色な作風。曲の骨格はどちらかと言えばSleeper寄りで、1分強のイントロの長さも印象的なダンサブルなノリもあるトラックの上にDavid GedgeがNile Rodgersを引き合いに出したくなるのも分かるリズムギターが映える。しかし全体を通した聴後感はTWPの2022年の新曲、としか表現しようがない、何とも不思議な魅力に溢れている。ライヴでどう再現されるのかが楽しみだったが、さすがに4人のコンボ編成では生演奏での再現が難しかったのか、リズムは録音された音源をバックにギター、パーカッション類(ボンゴとカウベル)、ヴォーカルを生で演奏する、今までのTWPのライヴでは観られなかった編成での実演となった。なお、ラジオで紹介してもらうにはこのイントロでは長過ぎると思ったのか、本シリーズでは唯一のRadio Versionが登場。イントロもコンパクトに20秒強で編集されている。そのRedio Versionは本アルバムのボーナストラックで収録されたUtah Saintsリミックス版を収録した限定12インチのカップリングでフィジカル化。
C2. Monochrome
4月号で発表。『Seamonsters』全編再現となった2021年5月20日に配信された3回目となるオンライン有償ライヴで初披露された名曲。その配信ライヴは英ブライトンにあるSt Bartholomew's Churchというネオゴシック様式が特徴的な教会の中にセットを組んで撮影。天井の高い教会の独特な厳かな雰囲気も感じられるカメラワークも見事で、前半の『Seamonsters』再現パートは同作特有のザラザラとした感覚を表現したかのようなモノクロームの映像で、完全初披露の新曲3曲を含む後半は一転してフルカラーと意匠を凝らした構成も素晴らしいものだった。その後半部のフルカラーパートで「モノクローム」というタイトルのこの新曲が演奏されたのも心憎い演出だった。
本シリーズではいち早く録音されていたナンバーで、公式Twitterの2021年6月7日の投稿で一瞬だけ映ったレコーディング・スタジオの映像の中でも一部聴くことができた。ベースのMelanie Howardによると彼女が加入して初めてTWPとして本格的に共作した1曲とのことだ。2004年のTWP再始動以降の黄金律とも呼べる作風で、美しいメロディに静と動のコントラストが鮮烈。"Larry's"や"I Lost The Monkey"、"Santa Monica"の路線にまた新たな傑作が加わった。冒頭「君なしで過ごす毎日はモノクロームになっていく/色彩がなく、人生はただ退屈になる/だからお願いだから、帰ってきて」と始まり、最後に諦観の境地で「そして、もし君が永久に去ったのなら/僕の世界は二度と色を取り戻さないだろう」と締め括られる歌詞も狂おしいという他ない。本シングルは2022年4月22日付けの全英ヴァイナル・シングルズ・チャートでこのシリーズ唯一の1位を獲得。
C2. Kerplunk!
6月号で発表。ライヴでも演奏されていなかった、本シリーズでは初となる過去のストック外からの新曲。タイトルからは世代的にどうしてもGreen Day初期の名作を思い出してしまうが、60年代からある子供用の玩具から着想を得たのだろう。ビー玉を落さないように筒に刺されたスティックを引いていくシンプルなもの(60年代のアメリカのTV CMの映像を見るとルールが分かりやすい)で、実在するゲームからの発想自体は2012年作『Valentina』の(同名のボードゲームからタイトルが取られた)"Mystery Date"以来ということになるか。David曰く“『George Best』のジャングリーさとJohn Barry風のエンディング”とのことで、確かにその発言そのままの曲調に思わず頬がゆるむ。もう片方の"Once Bitten"に負けず劣らず歌メロの良さが光る逸品だと思う。
ちなみに本シリーズではMy Life StoryのChris Hardwickと現在のメンバーでもあり、Melanie HowardのパートナーでもあるNicholas Wellauerの2人がドラムを叩いているのだが、シリーズ前半のChris Hardwickのグルーヴィーなプレイが光るのが、こういったさりげない小品だったりする。
C3. Don’t Give Up Without A Fight
1月号で発表されたナンバーだが、2019年9月の欧州ツアーで演奏され始めた、本シリーズでは2番目に古いレパートリーということになる。サッカー・チャントの様な"2-4-6-8, Who Do We Appriciate!"というコーラスが印象的なアッパー・チューンで、テンポダウンした終盤は2012年作『Valentina』以降度々顔を見せるクラウト・ロック・アプローチが聴かせる。
C4. X Marks The Spot
C面ラストは5月号で発表のこれまた名曲。これも2022年1月22日に行なわれた『24 Songs』シリーズ開始を記念したライヴ中でも披露された。2016年作『Going, Going...』時のギターリストで、ギターリストJon StewartがSleeperのライヴで出演出来ない時のTWPのライヴに度々ピンチヒッターで出演していたSamuel Beer-PearceとDavid Gedgeの共作。『Going, Going...』でも顕著だったテンポチェンジの妙も見事で、後半にかけての白熱する展開にどうしたって身体が反応してしまう中毒性があるが、何と言ってもDavid節全開と言っていいパートナーとの別れの風景と悔恨に満ち満ちた心情を描いたストーリーがグサグサと心に刺さり、思わず涙がこぼれる。
D1. You’re Just A Habit That I’m Trying To Break
4月号で登場。本シリーズ第1弾の"We Should Be Together"同様、2020年のリモート・セッション・シリーズ『Locked Down And Stripped Back』の中で初披露されたナンバーで、SleeperのJon Stewart加入後初めて披露された新曲がこれだった。その後2020年10月10日に行なわれた初のオンライン有償ライヴでエレクトリック・バンド・アレンジに刷新されて演奏。このスタジオ・テイクはそのエレクトリック・アレンジを踏襲しており、後半でDavidの特徴的な音色のギターが入って来るパートにどうしても心奪われる。考えてみればDavidのアカペラ独唱から始まるパターンの楽曲はこれが初めてかもしれないが、本人もライヴの際にさすがに緊張する1曲とコメントしていた。
D2. Plot Twist
11月号で発表。2022年4月の英国ツアーでは披露されていたもの。David Gedge曰く「偶然にもJon Stewartの尖ったギターとMelanie Howardのクランチーなベースラインのコンビネーションが1983年3月のThe FallのJohn Peel Sessionで耳にしたCraig ScanlonとSteve Hanleyのコンビを完全に思い起こさせた」とのことで、そのコメントも頷ける出来。そのサウンドにインスパイアされるように1989年の"Take Me!"以来となるThe Fallを引用する一節も歌詞に歌われている。The Fallからの影響はかねてから言及したことはあったが、具体的なラインアップも含めて言及したのは異例で、とは言え完成した楽曲はそのエッセンスを吸収したTWPの現在進行形を示した、最高の“バンド・グルーヴ”が感じられるソリッドな逸品に仕上がった。
D3. Whodunnit
10月号で発表。これが初登場となったナンバー。ミステリアスなマーダー・バラッド的な歌詞(おそらく恋人の元パートナーを殺めてしまったカップルの逃避行的なストーリー)の世界観にも寄り添うような、本シリーズでも、いやTWP史上屈指とも言える狂おしいメロディが堪能できる。ベース&ヴォーカルのMelanie Howardがメインのパートを書いたとのことだが、それも頷ける出来で、彼女のソロユニットSuch Small Hands名義の作品で聴けるような切なさが、歌の端々から零れ落ちる。Davidのファルセット気味の歌唱も相まって、TWP史上でも最上級の胸掻きむしられる傑作となった。シングルではフェードアウトしていたエンディングまで聴かせるアルバム・ヴァージョンだが、個人的にはもう少し長くてもいいくらいの、絶品のコーダ。
D4. A Song From Under The Floorboards
2月号で発表。最初のリリースからしてカヴァー曲から始まった本シリーズだが、その"We Should Be Together"が実際には別のバンドの未発表曲を取り上げたものだったの対して、本シリーズで唯一、ある程度知られた既存のナンバーをカヴァーしたのがこの曲。Magazine 1980年発表の3rdアルバム『The Correct Use of Soap』収録の名曲カヴァー。キーボードの音色が印象的な原曲の雰囲気から離れ、換骨奪胎してTWP色に染め上げている出色のカヴァーで、2019年9月の欧州ツアーでライヴでのレパートリーとして演奏されていたもの。当時のドラマーだったCharlie Laytonが提案したとのことだが、「僕は大学時代、マガジンに憧れていたから、異論は無かった。時代から時代へ、ポップスのバトンを受け継ぐということだね。」というDavidのコメントが象徴的で、TWPとMagazineそれぞれのレガシーがこのカヴァーに凝縮されているように思える。ちなみに80年代には不本意ながら比較対象に挙げられていたThe SmithsのMorrisseyがソロ作品のシングルB面(2006年のシングル"The Youngest Was the Most Loved")とライヴでも何度か取り上げていた楽曲でもある。
D5. Telemark
7月号で発表。上記Magazineカヴァー同様2019年9月の欧州ツアーで初披露され、同年10月28日に放送されたBBC 6 MusicのMarc Rileyの番組のセッションでも演奏されていたもの。ライヴでは意表を突くハードなイントロから続く、いかにも初期TWPらしいジャングリー・ギターが特色で、一転してテンポを落としたエンディングにかけてのバンド・アンサンブルも素晴らしい1曲だったが、このスタジオ録音版での仕上がりは全くこちらの予想を覆すもので、1938年の実際のラジオ放送をサンプリングしたというポエット・リーディングの様なモノローグをフィーチャーしたややエレクトロな要素もある、ちょっと異色のトラックに仕上がった。個人的にはライヴやレディオ・セッションでのテイクも印象的だったので、正直に告白すると最初に聴いた時には違和感が勝っていたが、今となってはポエット・リーディングとバンド・サウンドとの融合が新しい世界観を提示することになった『Going, Going...』の"Wales"の手法をさらに発展させたものとも感じる。シングルではフェードアウトされていたエンディングのギターのウォール・オブ・サウンドも素晴らしく、LP2の最高の締め括りとなった。
E1. Astronomic
"Whodunnit"とのカップリングで10月号で当時初登場となったナンバー。前述の"Science Fiction"と同様にSF的モチーフが唄われたもの。Davidの事前のコメントでは“サイケデリック・ポップとTV音楽の中間を行くサウンドでテレミンとSF的なエフェクトが施された楽曲”とのことで、TWPお得意のサーフロック路線を期待したのだが、蓋を開けてみたら正攻法の、美しいコーラスに心奪われる。良い意味で予想を覆した新たなメロディアスな名曲。シリーズ終盤に来て、それぞれ独自のセンスを持ったソングライター3人を擁した現在のTWPの個性が完全に溶け合った感覚が増していったが、この曲はその際たるサンプルだと思う。
E2. Go Go Go
3月号で発表。2021年3月13日に配信された2回目となるオンライン有償ライヴ"Worldwide Livestream#2"内で初披露されたナンバーでDavid Gedgeが子供の頃に観ていたというTVアニメ"Wacky Races"=邦題『チキチキマシン猛レース』にインスパイアされたという好曲。それも頷けるユーモラスな歌詞(70年代の洋楽シングル風の邦題を付けるなら「恋のチキチキマシン猛レース」か)で、Melanie Howardとの掛け合いの構成も活きている。TWP史上でもポップサイドを代表する1曲になるのではないだろうか?ここからの3曲はChris Hardwickのドラム・プレイも特筆すべきもので、最高のバンドグルーヴを牽引している。
E3. Once Bitten
6月号で発表。2020年10月10日に行なわれた初のオンライン配信ライヴ内で初披露されたもので、その時のMCでは仮タイトルの"Mel 3"(Melanie Howardと共作した3曲目という意味でしょう)というタイトルで紹介されていた。その後のライヴでは演奏されたことが無かったが、キャッチーなメロディとタイトなバンド・アンサンブルが最上の形で溶け合った、今のTWPの魅力が凝縮された1曲と言っていい。それにしても、ギターロックの教科書のような完璧な出来だと思う。
E4. La La La
3月号で発表。カップリングの"Go Go Go"と共に本シリーズでも最上級のポップな開放感が抜群。初披露は『Seamonsters』全編再現となった2021年5月20日に配信された3回目となるオンライン有償ライヴ中盤。実は時系列ではこれがDavid GedgeとSleeperのJon Stewart加入後初の共作曲となったそうだ。David曰く「The FallのMark E. Smithを意識した」というヴォーカリゼーションも聴かせる。思わずライヴのモッシュ・ピットが目に浮かぶ後半部の爆発的な展開も出色で、思えば、Jon Stewartが加入した後に期待されていた新たなTWPのギター・ロック・サウンドとは、こんな楽曲ではなかっただろうか。言うなればSleeperの"Delicious"とTWPの"Flying Saucer"や"Birdsnest"の方向性を最上の形で融合させた様な、これもまた傑作。ライヴでの実演をぜひ目にしたい。
E5. The Loneliest Time Of Year
『24 Songs』オーラスは12月号で発表されたこの曲。タイトルからしてあからさまなクリスマス・ソングで、前回(1992年)の月刊シングル・シリーズ『The Hit Parade』の第12弾だった"No Christmas"、2008年の限定コンピレーション・ボックス『How the West Was Won』収録の"Holly Jolly Hollywood [Featuring Simone White]"に続く、TWP史上ではオリジナルのクリスマス・ソングとしては3曲目となる。本シリーズではどのA面曲(製品としてのマトリックス番号に準じると)もMVが作られたものの、過去の配信ライヴで演奏された時の映像にスタジオ録音版を被せたものだったり、ジャケット写真の一部がアニメーション的に動くだけのものだったり、正直なところ急場凌ぎの中途半端なものが定番となっていたが、今回本シリーズでは初めてCGも用いた、いかにもMV然とした映像が製作され、本作のボーナスDVDにも収録されている。昔からよくあるセンチメンタルな"クリスマス・ソング"マナーを踏襲した切ない曲調が特徴的とはいえ、本シリーズの10月分から顕著になったエモーショナルなメロディとハーモニーの融合が見事で、シリーズの大団円に相応しいドラマティックな名曲となった。個人的にはCinerama期から続くDavidのABBA好きがあからさまに顕された1曲でもあると思う。アルバムとしての幕開けが"I Am Not Going To Fall In Love With You"でなければならなかったように、締め括りはこの曲でしか有り得ないと改めて思う。最高のエンディングを飾るフルレングス・ヴァージョンである。
最後のF面は本シリーズ以前に発表されていたシングルのみの収録曲3曲に、チャリティー・シングルのみに収録されたリミックス版、今回初登場となったThe Ukrainiansのカヴァーの5曲がボーナストラックとして収録されている。
F1. White Riot
言うまでもないThe Clash 1977年3月のデビューシングル"White Riot"のカヴァー。ロンドンを拠点とするインディーズ・レーベルwiaiwya-7777777の7インチ・シングルズ・クラブの一環として2018年12月にリリースされたスプリット盤からの収録。スプリットとは言え、カップリングはCinerama名義"The Name of the Game"(邦題「きらめきの序曲」)のABBAカヴァーで、こちらもオリジナルは1977年の楽曲だった。
元々はTWP/CINERAMA両方で数多くのセッションを残してきた北米シアトルのFM局KEXPが2017年2月に企画したThe Clashへのトリビュート企画"International Clash Day 2017"のために録音されたカヴァー音源で、2017年4月リリースの『The Home Internatinals EP』のセッション時に録音されたもの。プロデュース、エンジニアリングは『Going, Going...』に引き続きAndrew Schepsということもあって、このアルバムの流れで聴くと音の立ち上がりや粒立ちが全然違う。予算やスケジュールの都合もあったのかもしれないが、『24 Songs』もAndrew Schepsが関与していれば最高の音像だったに違いない。それにしても、もろにTWP印のイントロのDavidのカッティングから疾走するギター・ロックっぷりに思わず口の端が緩みまくる。
F2. Panama
F3. Jump In, The Water’s Fine (Japanese Edit)
2019年8月にリリースされた両A面シングルからの収録。"Panama"はアメリカでは有名な古典的な回文のフレーズ(A Man, A Plan, A Canal - Panama!)やアートワークやMVにも登場する1968年12月21日に打ち上げられたアポロ8号ミッションにまつわるワード(歌詞の2番に"A Christmas Eve in 1968"というラインが出て来るが、この日がアポロ8号が月の軌道に乗った日であり、同日にアポロ8号船内からのテレビ中継も行なわれた。ちなみに歌詞では上のラインの後に「It's the greatest photo of Earth」と続くが、そのアポロ8号ミッション中に宇宙飛行士のビル・アンダースがこの日に撮影した有名な写真「Earthrise(邦訳では“地球の出”)」のことである)も織り交ぜたシュールな歌詞も特徴的で、考えてみれば代表的なヒット曲"Kennedy"での手法をさらに発展させたものとも言える。2019年7月10日の(現時点では最後の)東京公演でも演奏された。
"Jump In, The Water’s Fine"の方はその2019年7月9日・10日に行なわれた東京公演のライヴ会場で先行販売されたクリアー・ヴァイナル「大丈夫だよ、飛び込んでおいで」に収録された特別版が採用。イントロ前にデイヴィッド・ゲッジ自身による日本語での曲紹介が追加されたもので、本編そのものは通常版と同じ。昔のFMラジオではIDと呼ばれる、この手の海外のアーティストの日本語の曲紹介がよく流れていたが、今でもその慣習は残っているのだろうか?
イントロからデイヴィッドのファルセットを使った歌唱が耳を惹くが、ワルツ・タイプの曲調はこれまでも何度か試みられてきたものとは言え、本曲のレコーディング時に一時TWPのツアーメンバーとして復帰していたTerry de Castoroが今までに無いブーミーな音色のベースラインを繰り出しているのもこの曲を印象的なものにしている。『Valentina』での"Stop Theif!"やCinerama時代の『Torino』での"Get Smart"など、個人的にはデイヴィッドがファルセットを使う歌曲に抗し難い魅力を感じているので、この曲はその点でも虜になってしまうものがある。
F4. We All Came From The Sea (Utah Saints Remix)
TWP史上でも異色なダンサブルな1曲となった『24 Songs』シリーズ第9弾収録曲がTWPと同じ英リーズ出身のエレクトロ・ユニットUtah Saintsによりリミックスされ、200枚限定のチャリティー12インチとしてリリースされた。僅数でのリリースとなったこともあり、ものの数時間で完売したが、このアルバムで初CD化されることとなった。
今まで同郷というだけで全く接点が無かった両者だが、実はUtah Saintsの創始者であるJez WillisはTWPのDIY精神に満ち溢れた活動に大きなインスピレーションを得て、自身もその姿勢を真似するように活動してきたとコメントしており、今回のリミックスの依頼にも二つ返事で快諾したとのこと。
その仕上がりはいかにもなUtah Saintsらしいリミックスで、彼らがヒット・チャートを賑わせていた時代の頃から良い意味であまり変わっていない、ちょっと懐かしさも覚えるサウンドになっていて、Davidの声も思った以上にハマっている。TWP関連でいわゆるダンス系のリミックスは2008年作『El Rey』期の"The Thing I Like Best About Him is His Girlfriend"が前例としてはあったが、ここまでフロア仕様に寄せたリミックスは初めてとなった。
ちなみにそのシングルの利益はすべて、英ブライトンを拠点とし、若い難民をサポートするチャリティー団体「ハミングバード・プロジェクト」に寄付することを目的としており、最終的に本12インチの利益1,304英国ポンド(当時の日本円レートで約213,200円)が寄付されることとなった。
F5. Teper My Hovorymo (Featuring Peter Solowka)
最後は本アルバムで初登場となった新録曲。TWP初代ギターリストであるPeter Solowkaをフィーチャーし、オリジナルWeddoesの半分と現在のリズム隊の組み合わせで演奏されたこの曲はPeter SolowkaがTWP脱退後、現在も活動を続けているThe Ukrainiansのカヴァー(オリジナルは1992年作『Vorony』に収録)。PeterがあのギブソンSGを引き倒している姿も目に浮かぶアグレッシヴな展開に思わず血が騒ぐ。この曲は2023年8月にThe Ukrainiansの自主レーベルからリリースされたクライナ難民救済プロジェクトのオムニバスCD『Together For Ukraine』にも収録された。
簡単にボーナスDVDにも触れておきたい。本シリーズレコーディング中の模様を撮影したドキュメンタリー的な映像、上記した"The Loneliest Time Of Year"のMVに加え、目玉となったのは2022年1月22日に行なわれた『24 Songs』シリーズ開始を記念したライヴが全編収録されていること。ただ惜しいのは全編モノクロ処理されている点。確かに、過去の配信ライヴでこの演出が活きていた例はあったが、今回ばっかりは失敗だったのではないだろうか?ライヴ映像ならではのダイナミズムや臨場感がすっかり損なわれてしまっている。出来自体は悪くないので、ただただ惜しい。
外部リンク
(first published : 15th August, 2023)