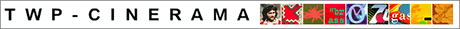| 作品概要 ザ・ウェディング・プレゼントがBBC Radio 1のプログラム「John Peel Show」のために行ったレディオ・セッション、通称“ジョン・ピール・セッション”(改めて申し上げるまでもなく、「John Peel Session」は番組名ではない)と同番組で中継されたライヴ音源など、関連する録音を全てまとめた完全版6枚組ボックス・セット。デビュー翌年の1986年2月のセッションから再生後の2004年までの18年間に録られた全12回分を年代順に最初のディスク3枚に、DISC 4からの3枚にはそのほとんどが公式には初登場となる同番組で中継されたライヴ音源を収録。収録される全91曲中、48曲(インタビュー・パートなどを含めれば95トラック中52トラック)が初登場という、過去に例を見ない膨大な未発表音源がここに発掘されている。
今回のプロジェクトのためにデイヴィッド・ゲッジ自ら全音源新たにリマスターを監修。Disc 1~3の過去の既発音源に関しては、リマスターの効果の程についてはあくまで個人的な印象にはなるが、ものによっては鮮明さが増したと感じたものはあるものの、全体的にガラッとイメージが変わるほどの差異は感じなかった。一方で、元々発売された年代によってCDの記録レベルにバラつきがあったため、かなり統一感は出ており、単純な事かもしれないがこれは嬉しい変化だった。また後述する様に一部、BBCにもマスターが残っていないものに関してはファンが所有していたエアチェック・テープから起こされているが、他の音源と比べても遜色ない仕上がりになっている。
ライナーノーツは名著『In Session Tonight:Complete Radio 1 Recordings』で知られるケン・ガーナー氏が担当。アートワークはCINERAMA後期作品から風景写真を用いた美麗なアートワークを手がけてきたEGELNICK AND WEBBのチームが引き続き担当。今回は海面の写真が共通したモチーフとして使用されている。
曲目解説 今回、DISC 1~3に全12回分のピール・セッション(旧TWP2回目となった'86年11月のセッションの5曲中4曲と新生TWP始動後唯一のPeel Sessionである'04年のセッションが今回初CD化)、DISC 4に1989年8月のジョン・ピール50回目の誕生日記念ライヴと'95年のPhoenix Festival(全て初CD化)、Disc 5が'96年のBBC Sound City Leeds (シングルB面に収録された1曲を除き、今回初CD化)、Disc 6が'96年のReading Festival (シングルB面に収録された1曲を除き、今回初CD化/オンエアされなかった曲を含む全長版)という内訳になっており、コンセプト上仕方がないこととはいえ、必ずしも時系列に並んでいない事もあるので、実際の録音順に並べて解説を加えていきたい。
なお、3/28付けのニュースでもお知らせした通り、付属ブックレットに致命的な欠陥があり、28ページ目のクレジット(Disc1~2収録分)部分に、30ページ目(DISC3~4#15収録分)のクレジットと同内容のものがまるまるダブって印刷されている。メーカー側はこのミスを認め、新たに刷られたブックレットの配布を行っている。ご希望の方は発売元である英Sanctuary社WEBサイト上からお問い合わせ下さい。
【注釈】
*曲名末尾*印が今回初CD化の曲目
*曲名末尾括弧内の曲名は放送当時のタイトル。ただし元々の副題が付いているDisc 3-#8は例外。
*「放送日」は全て初回放送時のもの DISC 1 #1~4:1st Peel Session- 収録日:1986年2月11日
- 放送日:1986年2月26日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、キース・グレゴリー(b.)、ピーター・ソロウカ(g.)、ショーン・チャーマン(dr.& back vo. on #4) - ゲスト・ミュージシャン:マイク・スタウト(g. on #4)
- 曲目:
1. You Should Always Keep in Touch with Your Friend
2. It's What You Want That Matters (What Becomes of the Broken Hearted?)
3. This Boy Can Wait
4. Felicity - 概要:
記念すべき初のジョン・ピール・セッション。デビュー時からバンドを高く評価してきたDJであり、デイヴィッド・ゲッジにとっては10代の頃から憧れの存在であったジョン・ピールのショーへの出演は念願だったもの。音源としては放送から8ヶ月後の同年10月、英Strange Fruitsからリリースされた12インチEPで初登場。後に"This Boy Can Wait"を除く3曲が1998年7月に発売された初のコンピレーション『Tommy(1985-1987)』に収録される。"This Boy Can Wait"は今回のボックスで初リマスターとなり、約19年ぶりに復刻された事になる。
#1は同年7月の両A面シングルから。#2は放送時と後のEPと『Tommy』収録時に"What Becomes of the Broken Hearted?"のタイトルだったが、今回はデビュー・アルバム『George Best』発表時の最終タイトルで収録されている。ちなみにこの曲はごく初期のライヴで演奏されていた時は"The Day That Letter Came"という歌詞の一節にもあるタイトルで紹介されており、都合2回名前が変わっている事になる。#3は1曲目の"You Should..."の両A面のもう片方。終盤の"Tonight, when I hold you in my arms"から始まるフレーズが歌われていないショート・ヴァージョンになっているが、これは同曲の7インチ・エディットとも構成が異なる。
最後の"Felicity"はオレンジ・ジュース1982年発表のデビュー・アルバム『You Can't Hide Your Love Forever』からのカヴァー・ソング。この原曲自体はメジャー・レーベルからの作品に収録されていたものだが、この時代のTWPは初期のOrange Juiceをはじめ、Josef KやFire Enginesといった1980年代初期のポスト・カード・レコーズ作品の強い影響下にあった事をデイヴィッドは告白している。同時期にRadio 1の別の番組のセッションでGang of Fourの"I Found That Essences Rare"(今回のボックスでフォローしていないためファン必須作品となった『Evening Sessions 1986-1994』所収)もカヴァーしているが、実際の所初期のTWPは紛れもなくポスト・パンクの流れを汲むものであったと今となっては思う。なお、この"Felicity"のイントロ前にデイヴィッドが"This is William Shatner's number"とつぶやいているのは、この曲の作者がジェームズ・ カークで、有名なSF TVドラマ『スター・トレック』のカーク船長役の俳優がウィリアム・シャトナーだったという、まあ何とも他愛の無いギャグ。後に『George Best』にはそのウィリアム・シャトナーの名前が歌い込まれたそのものずばりの"Shatner"という自作曲が登場する事になるが、デイヴィッド・ゲッジ自身は特にスター・トレックのファンであった事は無いとのことだ。
この曲で3本目のギターで参加しているMike Stoutはライヴ時のサウンド・マンとして働いていたスタッフで、正式なメンバーではないものの、初期TWPのBBCセッション時に度々参加している。彼はTWPでの仕事を離れた後、ミュージシャンとして元Spacemen 3のSonic Boomが結成したSpectrumの一員としても活動している。
DISC 1 #5~9:2nd Peel Session- 収録日:1986年10月26日
- 放送日:1986年11月25日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、ピーター・ソロウカ(g.)、ショーン・チャーマン(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:マイク・スタウト(b.)
- 曲目:
5. All About Eve*
6. Don't Laugh (Room With A View)*
7. Never Said*
8. Don't be So Hard*
9. Hopak (Cossachok) - 概要:
2回目のジョン・ピール・セッションはその最初のピール・セッションを収めた12インチEPの発売に合わせて行われたもの。このセッションはウクレイニアン・フォークの"Hopak"を除いてこの21年間全く陽の目を見なかった音源であったのだが、長らくCD化されなかった理由は大きく2つあると思う。第一に、本来のベーシストであるキース・グレゴリーが参加していない(理由は風邪だったとも寝坊だったとも言われており、定かではない)。替わりに演奏しているのが前述のMike Stoutなのだが、その出来はお聞き頂ければ直ぐにお分かりになると思う。悪くはないが、キース・グレゴリーの穴を埋められるほどではなく、完全にウェドーズならではのソリッドさと精彩を欠いている。第二に、選曲が地味。シングルのA面曲が1つもなく、後にシングルのB面に収録されるものが3曲もある。その他にも今回のライナーノーツでケン・ガーナー氏が触れている様々な悪条件が重なり、残念ながら氏の言葉を借りれば「最も印象に残らないセッション」となってしまった。
#5は『George Best』のCD版にも収録されているが元々は1987年7月のシングル"Anyone Can Make A Mistake"のB面曲だった。ちなみに、デイヴィッド・ゲッジが幼少時にほんのわずかの期間だが暮らしたことがある南アフリカでの印象を歌った歌詞、という説がある。"Room With A View"は後に'88年2月リリースのシングル"Nobody's Twisting Your Arm"のカップリング曲"Don't Laugh"として発表。今回はその最終タイトルで収録。#7は1987年2月のシングル"My Favorite Dress"カップリング。#8は『George Best』収録曲。ウクレイニアン・フォークのインストゥルメンタル"Cossachok"は"Hopak"として2000年のリイシュー版『Ukrainan John Peel Sessions』に収録。今回明らかになったのだが、実はウォーム・アップ用に録ったリハーサル・テイクがそのまま採用されているが、皮肉な事に本セッションの中で一番のハイライトとなっている。徐々にテンポアップしていく熱気溢れる展開はなかなかの聞き物だ。もちろん後にシリーズ化するウクレイニアン・フォーク・セッションの布石となった演奏で、その発案者であったピーターにとって、この曲の旋律は幼少時から聞き覚えのあったものだったが、当初は曲名さえ知らなかったそうだ。
DISC 1 #10~13:3rd Peel Session- 収録日:1987年3月3日
- 放送日:1987年3月18日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、キース・グレゴリー(b.)、ピーター・ソロウカ(g.)、ショーン・チャーマン(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:マイク・スタウト(g. on #13)
- 曲目:
10. Give My Love to Kevin
11. Something and Nothing
12. A Million Miles
13. Getting Nowhere Fast - 概要:
いよいよバンドの本領が発揮されはじめたと言っていい1987年3月、通算3回目のピール・セッションは傑作。後に『George Best』(今回のライナーノーツ内で同じSanctuary社から発売20周年記念エディションがリリースされる予定である事が触れられている)で発表される事になる新曲がお披露目されている。この音源はかつてStrange Fruitsから発売された『John Peel Sessions 1987-1990』(日本でも帯と日本語解説を付けた状態で『BBCセッションズ』のタイトルでリリースされた事もあった)に収録されていたが、同作品は長らく廃盤状態にあったので久々の復刻となった。『George Best』からこぼれ落ちてしまった初期衝動を上手くトレース出来たこのセッションは文字通りの意味で「レコード=記録」の名にふさわしい熱演・名演だと思う。#13は同郷リーズのバンド、Girls at Our Bestのカヴァーで、ジョン・ピールお気に入りのバンドでもあった。ちなみに名曲#12では最後の一行"At least not yet"が省かれている。ストーリーを考えれば、思わず深読みしたくなる省略ではある。
DISC 1 #14~18:4th Peel Session - The Ukrainian Set 1- 収録日:1987年10月6日
- 放送日:1987年10月14日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&back vo.)、キース・グレゴリー(b.)、ピーター・ソロウカ(マンドリン&back vo.)、ショーン・チャーマン(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:レン・リギンズ(フィドル&リードvo.)、Ron Rom (ハンド・クラップ&back vo.)
- 曲目:
14. Katrusya
15. Svitit Misyats (Katyusha Moon Shines{Medley})
16. Tiuitiunyk (Freedom Fighter)
17. Yikhav Kozak Za Dunai (You Deceived Me)
18. Hude Dnipro Hude (Awakening) - 概要:
そして『George Best』発売月に行われた通算4回目のセッションは、初のウクレイニアン・フォーク・セット。改めて説明すると、ウクライナ人の血をひく父を持つピーター・ソロウカのアイデアで、英国北部のウクレイニアン・コミュニティで愛される愛唱歌や伝承歌(ウクライナ由来のものばかりではなく、伝統的なブリティッシュ・フォークやロシア民謡を含む)をバンド・アレンジでカヴァーするという企画。ライナーノーツ内でケン・ガーナー氏も同意しているが、『George Best』発売5日前に放送されるという、記念すべきデビュー作の宣伝には最もふさわしくないタイミングでの企画ではあったが、後にアルバムとしてもまとめられ大評判となった。
今回のボックスで良かった点の1つがウクレイニアン・フォーク編成のセッションが録音時期毎にまとめられた事にあると思う。『Ukrainski Vistupi V Johna Peela』をはじめとする過去の編集盤では曲順がかなり入れ替えられ、そのせいでバラつきが感じられる瞬間が多々あった。
#14と#15はそもそもが独立した曲ではあったが、当日の放送で「どうしても4曲しか放送できない」という番組プロデューサーからの指示で強引にメドレーとしてまとめられた、という経緯が今回のライナー内で明かされている。ちなみにそのロシア民謡の"カチューシャ"は頭に付けるあれではなく、女性の名前。ロシアでは古風な名前で、日本で言う花子さんとかアメリカで言うベティさんとか、イギリスでいうディアドリーさんとか、さしずめそういう感じだと思う。
レン・リギンズ(現在の名前はThe Legendary Len)はTWP加入前にドラマーのサイモン・スミスが活動していたThe Sinister Cleanersのメンバーでもあった。彼は後にピーター・ソロウカと共にザ・ウクレイニアンズを結成する事になる。Ron Romは実はミュージシャンではない。英音楽誌Soundsの記者で、この収録スタジオにインタビューのために来ていた。彼は数曲で手拍子と「Hey! Hey! Hey!」の掛け声を担当している。
なお、これがオリジナル・ドラマーのショーン在籍時最後のセッションとなった。
DISC 2 #1~4:5th Peel Session - The Ukrainian Set 2- 収録日:1988年3月15日
- 放送日:1988年4月5日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&back vo.)、キース・グレゴリー(b.)、ピーター・ソロウカ(アコーディオン、マンドリン&back vo.)、サイモン・スミス(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:レン・リギンズ(リードvo.、フィドル、バラライカ etc...)、Roman Remeynes (マンドリン&back vo.)
- 曲目:
1. Davni Chasy (Minnooly Dnee)
2. Vasya Vasylok
3. Zadumav Didochok
4. Verkhovyba - 概要:
そして5ヶ月後には早くも2回目のウクレイニアン・セットを収録。全盛時代のTWPを支えたサイモン・スミスをドラマーに迎えた最初のセッションでもあった。ウクレイニアン編成のピーター・ソロウカと言えばアコーディオンのイメージが強いのだが、実はこの2回目のセッションから弾き始めている。ここでの4曲も翌年『Ukrainski Vistupi V Johna Peela』(特殊な企画作にも関わらず、4万枚以上のセールスを売り上げ、全英アルバム・チャートで最高位22位を記録。バンド初のメジャー・ヒットをもたらした)で発表。このシリーズで最も有名になった「悲しき天使(Those Were The Days)」のカヴァー#1や盛り上がりすぎてフェードアウトせざるを得なかったという#4など、一連のウクレイニアン・セットの中でも特に記憶に残る名演揃いの一夜となった。ジョン・ピールも放送時、この回のセッションを興奮気味に大絶賛したという。
ここで新たにゲストに加わったRoman Remeynesも後にザ・ウクレイニアンズの結成メンバーとなる。
DISC 2 #5~8:6th Peel Session- 収録日:1988年5月24日
- 放送日:1988年5月30日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、キース・グレゴリー(b.& back vo. on #8)、ピーター・ソロウカ(g.& back vo. on #8)、サイモン・スミス(dr.& back vo. on #8) - 曲目:
5. Why are You being so Reasonable Now?
6. Unfaithful
7. Take Me! (Take Me, I'm Yours)
8. Happy Birthday - 概要:
前のセッションからわずか1ヶ月半という短いブランクでの出演、ノーマル・ヴァージョンのTWPとしては1年2ヶ月ぶり通算6回目となるセッション。何と言っても当時出来たばかりの新曲#7(放送当時のタイトルは"Take Me, I'm Yours")、ライヴでも数えるほどしか演奏されていないAltered Imagesの代表曲#8のパンキッシュなカヴァーが出色。後者はデイヴィッド・ゲッジのオールタイム・フェイヴァリット・ポップ・グループというだけではなく、ジョン・ピールも頻繁にオンエアしていたお気に入りでもあった(ピールは後に同バンドのベスト盤のライナーも手がけている)。ちなみに1992年の『The Hit Parade』シリーズでは彼女たちのスタジオ・アルバムにしか収められていない"Think That It Might"という地味なレパートリーまでカヴァー。この様に、TWP初期からシネラマに至るまで、デイヴィッド・ゲッジはジョン・ピールが番組で紹介していた作品やアーティストを好んで取り上げる傾向があるが、番組の熱心なリスナーであったのだから、それも当然だろう。ちなみに、音楽的な好みが似通っている事もあって一時期「彼が引退したらぜひ後継者に立候補したい」と半ば本気で宣言していた。
#5は同年9月のシングル、#6は後に1989年10月のシングル"Kennedy"のカップリングで発表される事になる。なお、このセッション・テイクの#6を収録した英音楽誌House of Dollsの付録7インチも制作されている。
いずれも『Bizarro』前夜の、ノリに乗っていたバンドの姿を伝える充実した内容だ。それにしても、最初のピール・セッションからわずか2年で、とてつもないロック・バンドへと成長した事が分かる。
DISC 2 #9~11:7th Peel Session - The Ukrainian Set 3- 収録日:1989年5月2日
- 放送日:1989年5月15日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&back vo.)、キース・グレゴリー(b.)、ピーター・ソロウカ(アコーディオン、マンドリン&back vo.)、サイモン・スミス(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:レン・リギンズ(リードvo.、フィドル、バラライカ etc...)、Roman Remeynes (マンドリン&back vo.)
- 曲目:
9. Zavtra (Zavtra Ya Budu Pid Nebom Chuzhim)
6. Sertsem I Dusheyu (Sertsem I Dusheyev)
11. Cherez Richku, Cherez Hai - 概要:
ほぼ1年ぶり通算7回目となるセッションは最後のウクレイニアン・セッションとなった。この前月に発売された『Ukrainski Vistupi V Johna Peela』発売記念ツアーの全日程終了後に録音されている。過去2回のセッションは既存のトラディッショナルをデイヴィッド・ゲッジがアレンジしたものだったが、ここではSolowka/Liggins/Remeynesの3人、つまりは後のザ・ウクレイニアンズの中核メンバーのオリジナル・ソングを演奏している。そこに注意して聴いてみると、もはやここではTWPというよりはウクレイニアンズそのものと言っていいテイストになっている。全曲2000年のリイシュー版『Ukrainan John Peel Sessions』にて復刻済み。
DISC 4 #1~6:live set recorded for John Peel's 50th Birthday- 収録日:1989年8月29日
- 放送日:1989年8月30日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、キース・グレゴリー(b.)、ピーター・ソロウカ(g.)、サイモン・スミス(dr.) - 曲目:
1. What Have I Said Now?*
2. Crushed*
3. Kennedy*
4. Thanks*
5. Bewicthed*
6. Granadaland* - 概要:
時系列上ディスクは4枚目へと飛ぶ。上記ウクレイニアン・セッションから3ヶ月後に行われたライヴ・レコーディング。ジョン・ピール50回目の誕生日記念のライヴからのもので、当日はThe FallやThe House of Loveも出演している。今回初CD化となった音源だが、マスターは残念ながらBBCに残っていなかった為、ファン所有のエアチェック・カセットから起こされたもの。だが、テープの保存状態が良かった事もあるのだろう、パッと聴いても録音状態の善し悪しが気にならないくらい、十分な補正が施されている(細かく聞くとさすがにシンバルやハイハットの高音域がヘタっているのは仕方ない)。個人的にはこれでようやく10年以上密かに愛聴してきたカセットテープに別れを告げる事ができる。
しかしこの際、音質は二の次である。何しろ発表前の『Bizarro』の新曲が、まさにその傑作を作り上げたメンバーによってライヴ演奏されているのだ。その事実だけでも永久保存に値するし、改めて聴いてもこの時のTWPは1つのピークを迎えつつあったと感じる。爆発するようなバンド・グルーヴが躍る"Kennedy"やイントロから火を吹くような"Thanks"は一体何なのだろう!?ワンダー・スタッフでは無いが、まさに“Eight Legged Groove Machine”と化した壮絶なる一夜の記録である。ただ惜しむらくは、1曲目の"What Have I Said Now?"で終始アクースティック・ギターのチューニングが狂っていること。この曲だけは昔も今も最後まで聴き通すのはつらい。また、まだここでの新曲群が発表前で一般のファンには馴染みが無かったという事もあるが、"Kennedy"の様な今ならイントロが始まるだけで興奮の坩堝と化すだろう曲でも、曲が終わってからようやくワーッ!っと歓声が上がるような観客の反応が今聴くと奇妙だ。
本ボックスのDISC 6では1996年のラインナップによるライヴも聴ける"Bewitched"はテンポの速いキャッチーなナンバーが並んだ『Bizarro』の中ではこの日本では昔からわりと地味な曲として軽視されているようだ。ではその地味な曲が2001年のリイシュー盤におけるMark Beaumount氏のライナーノーツでなぜアルバムのハイライトと捉えられているのか?CINERAMAがステージ上で旧TWP時代のラインアップを解禁した際になぜこの曲が真っ先に取り上げられ、その後も今日に至るまで頻繁にステージで演奏されているのか?理由は、実は海外では昔から殊その歌詞においてバンドのキャリア上でも屈指の人気曲であるからに他ならない。この事実はぜひとも記憶に留めて頂きたい。個人的にも、失恋の傷みや後悔の念を青年期特有の物憂げな心情と共に切り取ったこの歌詞はデイヴィッド・ゲッジのリリシストとしての代表作の1つであると思うし、そのストーリーに沿った曲想とサウンドの調和は見事としか言いようがない。その"Bewitched"からなだれ込むように始まる締めくくりの"Granadaland"はぜひとも1999年に発表された2枚組編集盤『Singles 1989-1991』で聴ける1990年夏、リーズでのライヴ・テイクもお聞き頂きたい。ウルトラ・ファストな上にさらに破壊力と鋭さを増した、気絶しそうなほどのカタルシスが味わえる。
とにかく、もはや『Bizarro』でさえ物足りなくなるこのPeel's 50th Birthdayの模様はこの時代のTWPに興味のある方は絶対聴いておいた方がいい。
ちなみに"Kennedy"の曲中でデイヴィッドが叫んでいる台詞"Status Quo, 25 years in business!"は1988年から90年にかけて、TWPがライヴ中によく叫んでいたもの。Status Quoとはもちろん英国の国民的人気を誇る大物、ステイタス・クオの事で、結成30年以上一芸必殺のブギー・サウンドでおなじみの彼らを揶揄した洒落であると同時に、ジャカジャカと延々カッティング・ギターを応酬する曲が多かった当時の自分たちに対する自嘲的なジョークでもあった。実際、1988年頃のライヴにおいて、"Take Me!"や"This Boy Can Wait"の後半のインスト・パートでデイヴィッドとギターのピーター・ソロウカがStatus Quoのステージ・アクションを茶目っ気たっぷりに真似するシーンもあった。なお、この台詞はDisc 2収録の1988年5月のセッション"Happy Birthday"でも聞ける。
DISC 2 #12~15:8th Peel Session- 収録日:1990年10月14日
- 放送日:1990年10月28日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、キース・グレゴリー(b.)、ピーター・ソロウカ(g.)、サイモン・スミス(dr.) - 曲目:
12. Dalliance
13. Heather
14. Blonde
15. Niagara - 概要:
再びディスク2に戻る。通算8回目のピール・セッションは翌年5月リリースの金字塔『Seamonsters』期の楽曲で構成。あのピール50回目の誕生日記念の伝説的な一夜からさらなる高みへと到達したのがありありと分かる、TWPのピール・セッション史上の最高傑作。このセッションを初めて聴かれた方なら、果たして『Seamonsters』が高名なエンジニアの力だけが傑作たらしめた要素だったのか疑問に思えてしまうはずだ。改めて、このバンド・グルーヴがうねりまくる奇跡的な名演と呼びたい"Dalliance"や"Blonde"を超えるバンドは現れないだろうと思うし、もはや本人達でさえも再現不可能な瞬間がここには刻まれている。#13は『Seamonsters』期のレパートリーの中でも最も早い段階からライヴで演奏されていた楽曲で、アレンジもいくつかの変遷を経てきており、このセッション・テイクではだいぶアルバム・テイクのアレンジに近づいてきているのだが、その歌唱についてはまだアルバム・テイクでの完成度の高さには及ばない。やはりこのストーリーにおいては"And I know I said I wouldn't be the one/But an empty bed, your clothes all gone"はありったけの怨念を込めて歌われなければならないし、このセッション・テイクは淡泊すぎる。後にシングルB面名曲となった#15はギター・ストロークのみで始まる初期アレンジ。当時のライヴではエンディングを飾るナンバーとしておなじみとなったが、その後は再生後の2006年7月のU.K.ツアーまで16年以上、ステージで演奏される事は無かった。
DISC 3 #1~4:9th Peel Session- 収録日:1992年3月17日
- 放送日:1992年5月2日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、キース・グレゴリー(b.)、ポール・ドリントン(g.)、サイモン・スミス(dr.) - 曲目:
1. California
2. Flying Saucer
3. Softly Softly
4. Come Play with Me - 概要:
セールス面ではバンド史上最高到達点となった1992年の月間シングル・シリーズ『The Hit Parade』期に行われた、通算9回目のピール・セッション。ここでの注目は有名なお蔵入り楽曲#3。1998年に英Cooking Vinylからリリースされた『John Peel Sessions 1992-1995』で復刻されるまで長い間幻の1曲と化していたが、お蔵入りさせたのは間違いだったんじゃないか、と思えるくらい、他の『The Hit Parade』A面曲に全く引けを取らない。のちにこの曲のサビのみが1994年9月のシングル"Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah"にてリサイクルされる。今回のライナーによると結局この状態ではスタジオ録音は残されていないとの事だ。ちなみに一度某音楽誌でこの曲が実際に発売されるという記事が掲載された事があったが、その際シリーズ恒例であったB面カヴァーとして予定されていたのがQueenの「輝ける七つの海」だったという!(こちらも録音は残っていない。)他にも、『The Hit Parade』期のグイグイと盛り上がっていく様なウェドーズ・グルーヴの真骨頂が楽しめる#2も名演。なお、このセッションが前身のThe Lost Pandas時代からのメンバーだったオリジナル・ベーシスト、キース・グレゴリー在籍時最後のセッションとなった。
DISC 3 #5~8:10th Peel Session- 収録日:1994年3月22日
- 放送日:1994年4月16日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、ダレン・ベルク(b.)、ポール・ドリントン(g.)、サイモン・スミス(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:ジョン・パークス(g. on #6&8)
- 曲目:
5. Gazebo [Electric Version]
6. So Long, Baby
7. Spangle [Electric Version]
8. Him or Me (What's It Gonna Be?) - 概要:
共に黄金時代を築いたRCAとの契約を終了し、バンドはIslandへと移籍する。通算10回目となるこのセッションではそのIslandからの唯一のアルバムとなった『Watusi』発売に5ヶ月先駆ける形で放送された。ここでの音源はPaul Revere & The Raidersのカヴァー#8を除いて"Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah"の2種あるCDシングル盤のCD2のカップリングで初登場し、後に#8も含めて『John Peel Sessions 1992-1995』に収録された。当時の事を思い出すと、そのCDシングル盤で聴いた時に『The Hit Parade』期のギター・バンド・サウンドの延長線上にある雰囲気に来る新作への期待に胸躍らせたものだったが、まさか#5と7があの様な意外性のあるアレンジに刷新されると思ってもみなかった(今となっては『Watusi』アレンジの方が好みだったりもするのだが…)。リアルタイムで放送を聴いていただろう英国のファンならなおさらだっただろう。
#6と8にギターで参加しているJohn ParkesはTWP初期からローディーとして携わっていた人物だが、元々地元リーズでは名の知れたミュージシャンで、初代ギターリストのピーター・ソロウカがTWPデビュー前に参加していたThe Chorusのリーダーでもあり、同じくThe Chorusのメンバーで後にTWPに加わるドラマー、サイモン・スミスと前述のLen Ligginsと共にThe Sinister Cleanersでも活動していた。現在でもソロ・アーティストとしてアルバムを発表するなど、音楽活動を続けている。
DISC 4 #7~18:The 1995 Phoenix Festival- 収録日:1995年7月14日
- 放送日:1995年7月15日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、ジェイン・ロッキー(b.&back vo.)、ダレン・ベルク(g.)、サイモン・スミス(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:ヒュー・ケリーJr. (dr. on #16&17 &kyd. on #8, 13&14)
- 曲目:
7. interview 1*
8. Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah*
9. Kennedy*
10. Swimming Pools, Movie Stars*
11. Click Click*
12. It's A Gas*
13. Spangle [Acoustic Version]*
14. Gazebo [Acoustic Version]*
15. Fleshworld*
16. Sucker*
17. The Queen Of Outer Space*
18. interview 2* - 概要:
再びディスク替わって、全曲初CD化のライヴ音源。先の1994年のラインナップからポール・ドリントンが脱退し、バンド史上初のパーマネントな女性メンバーとなったジェーン・ロッキーを迎えた第五期メンバーによるライヴ。番組内で中継されたフェニックス・フェスからのもので、この頃から何度か試されるダブル・ドラム編成がお披露目されたライヴであった。そのサポート・メンバーであるヒューは3曲でキーボードも担当している。
放送当時、ピールも絶賛したという録音の鮮明さは本ボックスの4つあるライヴ・パートの中でも群を抜いているが、演奏面でも今回のボックスで最も発見が多かったのがこのブロックだった。当時ギターにスイッチしたばかりとは思えないダレンの熱演も光る(後年、本人自らベスト・パフォーマンスであったと告白している)。同じディスク4内で'89年版が聴ける"Kennedy"は通常のヴァージョンに比べて途中ドラムのみのインストパートが長くなっているが、過去のサイモン・スミスのインタビューから推察すると、もしかしたらこれはステージ上のモニタリングがままならない状態だった為に、リズムを一旦合わせる目的でアドリブ的に設けられたものだったのではないかと想像する。結果、この後の後半部の盛り上がりが凄まじいものがある。他にもこの年唯一のリリースであったシングル曲#16のダブル・ドラムの醍醐味が味わえる圧巻のドライヴ感、これがライヴで演奏された最初で最後の機会となったという『Seamonsters』期のシングルB面名曲の1つ#15(ファンからの人気が高い曲にもかかわらず、作った本人は嫌いだったというから意外だ)、上の10回目のセッションとは対称的に『Watusi』ヴァージョンに忠実に演奏されている#13、14、同作への低評価を覆すのに十分なソリッドかつヘヴィーなライヴ・ヴァージョン#8、#10、#12などなど、非常に聴きどころが多い。
余談ながら、このフェスにはTVの撮影クルーも入っており、当時日本でもCX系列の深夜に放送されていた『Beat U.K.』という番組でもこのTWPのライヴが一部放送されていた事がある。現在YouTubeには"It's A Gas"の映像がアップされているが、おそらくその時のソースだと思われる。
DISC 3 #9~12:11th Peel Session- 収録日:1995年12月3日
- 放送日:1995年12月16日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、ジェイン・ロッキー(b.&back vo.)、ダレン・ベルク(g.)、サイモン・スミス(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:ヒュー・ケリーJr. (dr.)
- 曲目:
9. Drive
10. Love Machine
11. Sports Car
12. Go, Man, Go - 概要:
再びディスク3に戻って、旧TWP最後となった1995年12月、通算11回目のセッション。翌年1月にリリースされる『Mini』からの新曲で構成されている。全曲Cooking Vinylからリリースされた『John Peel Sessions 1992-1995』に収録済み。上記フェニックス・フェスティヴァル時と同じダブル・ドラム編成ながら、この編成ならではの妙味は感じられない。しかし唯一褒められるべき点は、先の編集盤『John Peel Sessions 1992-1995』収録分の3回のセッションはリマスターの音質向上が目覚ましく、特にこの回のセッションはスタジオの空気が鮮明に伝わってくる様な感触があるが、Maida Vale 3という、元々ビックバンドの収録用に作られたという大型スタジオで録音している事も大きいと思う。
このセッションの最後には興味深い仕掛けがある。#12のエンディングのフィードバックがそのままこの下の2004年の再生後のセッション#13の"Blue Eyes"のイントロのフィードバックとミックスされているのだ。本ボックス中で唯一、録音時期が異なる2つのセッション、しかも9年間も隔たりのある録音がわざわざクロス・フェードされているこの編集にデイヴィッド・ゲッジがどういう意志を反映させたかったのか?TWPが辿ってきた歴史を理解している方ならば、お分かり頂けるだろう。
DISC 5:BBC Sound City Leeds 1996- 収録日:1996年4月12日
- 放送日:同日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、ジェイン・ロッキー(b.&back vo.)、ダレン・ベルク(g.)、サイモン・スミス(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:クリス・クーパー (dr.)
- 曲目:
1. John Peel Introduction*
2. Silver Shorts*
3. Love Machine*
4. Snake Eyes*
5. Sports Car*
6. Convertible*
7. Click Click*
8. My Favourite Dress
9. Real Thing*
10. It's A Gas*
11. Skin Diving*
12. Sucker*
13. Corduroy*
14. Mini Prize Draw* - 概要:
1996年4月地元リーズでのライヴはBBC Sound Cityという企画の一環で放送されたもの。"My Favorite Dress"のみ1997年1月のシングル"Montreal"のCD版のカップリングに収められ、編集盤『Singles 1995-'97』でも聞くことができるが、残りは初CD化となる。ラインナップはセカンド・ドラムにPale Saintsのクリス・クーパーを迎えた5人編成。そのダブル・ドラム・ソロから始まる"Silver Shorts"のアレンジはおそらくこの時だけのもので珍しい。"Click Click"は電源トラブルにより中断した箇所も収録されている。最後の"Mini Prize Draw"は曲ではなく、『Mini』CD封入のハガキで応募するとミニ・クーパー(アルバム・ジャケットのパーツに使われている他、"Drive"の冒頭でそのエンジン音が聞ける)が1名様に当たるキャンペーンをやっており、その当選発表を番組内で行ったもの。なお、当時のギターリスト、ダレン・ベルクはこのステージを最後に脱退し、前年のツアーとレディオ・セッションに参加していたHugh Kerry Jr.と共にBeachbuggyを結成している。ダレンが脱退間近だったという事もあり、バンドのノリやヴァイブがあまり良くないな、と感じられる瞬間がままある。一方で、初期代表曲の#8は"Uneaten Meals..."から始まる終盤の印象的なヴァースを会場全体でシングアロングしているのが確認できる。このライヴに於ける最も幸福な瞬間がここに。
DISC 6:The 1996 Reading Festival- 収録日:1996年8月25日
- 放送日:同日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、ジェイン・ロッキー(b.&back vo.)、サイモン・クリーヴ(g.)、サイモン・スミス(dr.) - 曲目:
1. Go-Go Dancer*
2. Sports Car*
3. Kansas*
4. 2, 3, Go*
5. Bewitched*
6. Venus*
7. Loveslave*
8. Real Thing*
9. Drive*
10. Montreal*
11. Come Play With Me*
12. Brassneck
13. Crawl* - 概要:
6thアルバム『Saturnalia』発売前月、1996年8月に行われたレディング・フェスティヴァルの模様も1曲を除き今回初CD化。"Brassneck"もやはり1997年1月のシングル"Montreal"のCD版のカップリングで初登場し、編集盤『Singles 1995-'97』にも収録されていた。今回、放送当時時間の都合でカットされた曲("Go-Go Dancer"、"Sports Car"、"Bewitched"、"Crawl")も含む当日のステージ全曲が復元された。またブックレットのクレジットには既発の"Brassneck"も放送されていない曲として記載されている。ただ実際には放送されていたという説もあり、真相を確かめたいところだ。
後にシネラマ~新生TWPでも活動を共にするギターのサイモン・クリーヴ参加後の4人編成によるライヴ。イントロのアレンジがガラッと変わった"Go-Go Dancer"に意表をつかれるが、"Drive"からの後半の流れも聞き所。この第六期TWPを代表する名曲である#10は現在のTWPのステージでも演奏されてはいるが、近年のライヴに足を運んだ方ならば、この様な一見シンプルなミッドテンポのポップソングでさえもサイモン・スミスのドラミングが重要な鍵を握っていた事に否が応でも気がついてしまうだろう。彼のプレイはこのステージでも正確なリズムを保ちつつも、手数の多い独特なスタイルでグルーヴを牽引している。今回のボックスが本当に罪作りなのは、現在のTWPにおけるサイモン・スミスという稀代のプレイヤーの不在を再認識させてしまう事だと思う。名前は引き継ぐ事ができても、その独創的なリズム・パターンは今もって誰も継承できていないからだ。
DISC 3 #13~17:12th Peel Session- 収録日:2004年7月22日
- 放送日:2004年9月21日
- パーソネル:
デイヴィッド・ゲッジ(g.&vo.)、テリー・ディ・カストロ(b.&back vo.)、サイモン・クリーヴ(g.)、カリ・パーヴォラ(dr.) - ゲスト・ミュージシャン:キャサリン・コンズ (kyd.)
- 曲目:
13. Blue Eyes*
14. Ringway To SeaTac*
15. Shivers*
16. Queen Anne*
17. White Horses* - 概要:
まだまだ記憶に新しい、TWP名義では通算12回目のピール・セッションは2004年9月21日、CINERAMA後期4人のメンバーのままTWPとして活動していく事を正式表明した9月3日から18日後に放送された。このオンエアから約1ヶ月後にジョン・ピールは他界し、これが結果的にデイヴィッド・ゲッジにとって最後のピール・セッションとなってしまった。全曲初CD化。1992年の『The Hit Parade』シリーズからの#13は過去に他の番組でのセッションは残されているが、ジョン・ピール・ショーのためのセッションでは初披露となった。前述した様に、同じディスクの1995年のセッション#12"Go, Man, Go"のエンディングのフィードバック・ノイズとこの曲のイントロのフィードバック・ノイズがクロス・フェードされているため、9年の時間を一気にタイムスリップする様な感覚が味わえる。
#14、16は後のアルバム『Take Fountain』で発表される当時の新曲。サイモンのギターがさらにラウドに唸り、より躍動感の感じられるこちらのテイクは達人カリ・パーヴォラ(唯一、サイモン・スミスのオリジナル・フォームに肉薄できた個性的なドラマーだった)在籍時の後期CINERAMAのライヴの素晴らしさを直ぐに思い出させる。テリーとのデュエット#15は#14がシングル・カットされた際にカップリングとして発表されている。そのスタジオ・テイクと同様に、プロデューサーのスティーヴ・フィスクによるループをバックにカラオケ状態で歌われている。#17はアイリッシュの女性シンガーJackie(Jackie Lee)が放った1968年の大ヒットのカヴァーでTWP版はこのセッションでしか演奏されていない。原曲は元々、同名の子供向けTV番組の主題歌だった。放送ではジョン・ピールが自分の世代にとっては懐かしい曲、と紹介していたが、実は自分にとってもある種の懐かしさを覚えるものだった。The Trash Can Sinatras(以下TCS)が1990年にリリースしたシングル"Circling the Circumference" [Go! Discs catalogue no.:godcd 46]のカップリングで取り上げていたから。当時はTCSのオリジナルだと信じて疑わなかったくらい全く違和感のないものだったし、個人的にはより洗練されたTCSのアレンジの方が好みではある。なおTCS版は現行の再発盤『Cake』のボーナス・トラックで聞ける。
サポート・メンバーであるキャサリン・コンズはセッション・ミュージシャンで、新生TWPとしては2回目のRadio 1セッションとなった2006年8月29日放送の"One Music"でのオール・カヴァー・セッション(名演揃いのこのセッションも早期のCD化が待たれている)にも再び客演している。
個人的な想い出として、当時ピールの番組は火曜日から木曜日の深夜に放送されており、この12回目のウェドーズのセッションは火曜の放送だったのだが、その前週木曜日の放送のエンディングでジョンが言った台詞が忘れられない。「来週火曜は久しぶりのウェディング・プレゼントのセッションがあるよ。」それはいつもと変わらない、ただの次週放送の告知だったが、これ程感慨深い瞬間はなかった。リアルタイムでウェドーズのピール・セッションが聴ける日が来るなんて、夢にも思わなかったからだ。
余談ながら、この再生後のTWPのセッション以前に『Take Fountain』への直接的な布石となった楽曲が多数披露された後期CINERAMAの2003年以降のセッションとライヴがここに収められていないのが残念で仕方なかったのだが、今回のライナーノーツ内で同じSanctuary社からCINERAMAに関してもピール・セッションの完全版ボックスが計画されている事が明らかにされている。これは朗報。
ライナーノーツ日本語訳(抄訳) 今回のブックレットの大半を占めるのは、BBCセッションの歴史をまとめた著書としては唯一のものと言っていい名著、『In Session Tonight:Complete Radio 1 Recordings』を手がけたケン・ガーナー氏によるライナーノーツ。その文章量は作品の膨大なヴォリュームに見合うもので、もちろんTWP/CINERAMA関連作品に付けられたライナーノーツとしては過去最長のものとなった。ただ全文訳してみて、番組のジョン・ピール・ショーとBBC Radio 1の歴史に精通している方なら楽しめても、この作品単体の解説としてはさほど重要とは思えない、サイド・ストーリーの記述にかなりのスペースが割かれてしまっている箇所も多く、話の流れが散漫になってしまっている事もあったので、思い切って大筋に影響ないエピソードや詳細は割愛し、抄訳版として掲載する事にした。これを読めば、デイヴィッド・ゲッジとジョン・ピールがミュージシャンと一介のDJとしての関係を超えた特別なつながりがあった事、そしてBBCレディオ・セッションがどういう経緯で始まったのか、またなぜ厳密には「スタジオ・ライヴ」でも「ライヴ」でもないのか(この点が過去の多くのBBCセッション関連の日本盤ライナーや各媒体でBBCセッションの説明をする際に大きく誤解・誤認されている)がお分かり頂けると思う。なお、氏は現在ジョン・ピール・セッションの歴史に特化した著書を執筆中である事が、本ライナーノーツ末尾のプロフィール紹介の欄で触れられている。 >> ケン・ガーナー氏ライナーノーツ日本語訳(抄訳) [2007/4/10掲載]
ブックレットの写真解説 今回のブックレットには、先に述べた致命的な欠陥があったものの、美麗な写真が多数使用されている。ただし、バンドの写真について全くキャプションが無いため、ここでいつの時代の写真なのかを解説していきたい。なお、多くの写真が自らのレーベルScopitonesがFlickr内に開設したフォトギャラリーで閲覧できるので、ご覧頂きたい(下記文中からも個別の写真にリンクしています)。
>> 19ページ目「滝のそばに立ったオリジナル・メンバー写真」
第一期のオリジナル・ラインアップで1987年の撮影(リンク先で1988年となっているのは誤り)。左からキース・グレゴリー(b.)、ピーター・ソロウカ(g.)、ショーン・チャーマン(dr.)、デイヴィッド・ルイス・ゲッジ(g.&vo.)。
>> 20ページ目「ウクレイニアン編成のメンバー写真」
1988年のサイモン・スミス(dr.)加入後に行われた2回目のウクレイニアン・フォーク・セッションのメンバーたち。左からキース・グレゴリー(b.)、ゲストのRoman Remeynes、デイヴィッド・ルイス・ゲッジ、アコーディオンを持っているのがピーター・ソロウカ、ゲストでメイン・ヴォーカルだったレン・リギンズ(フィドルも担当)、右端がサイモン・スミス(dr.)。
>> 21ページ目「第二期のメンバー写真」
RCA移籍後に撮影された宣伝用写真。おそらく1990年頃、"Brassneck"EP前後のもの。左からキース・グレゴリー(b.)、サイモン・スミス(dr.)、デイヴィッド・ルイス・ゲッジ、ピーター・ソロウカ(g.)。
>> 22ページ目「第三期のメンバー写真」
ピーター・ソロウカ脱退後ポール・ドリントンが加入した第三期、1991年後半のもの。左からサイモン・スミス(dr.)、ポール・ドリントン(g.)、デイヴィッド・ルイス・ゲッジ、キース・グレゴリー(b.)。
>> 23ページ目「第四期のメンバー写真」
Island移籍後に撮影された宣伝用写真で1994年の撮影。左からデイヴィッド・ルイス・ゲッジ、サイモン・スミス(dr.)、ポール・ドリントン(g.)、当時新加入のダレン・ベルク(b.)。
>> 24ページ目「第五期のメンバー写真」
Cooking Vinyl移籍後に撮影された宣伝用写真で、見ての通りアルバム『Mini』に合わせて撮影されたもの(1995年後半撮影)。左からデイヴィッド・ルイス・ゲッジ、ジェイン・ロッキー(b.&back vo.)、彼女の加入でギターにスイッチしたダレン・ベルク、サイモン・スミス(dr.)。
>> 25ページ目「第五期+1のメンバー写真」
同じく第五期のものながら、今回のボックスセットでも聞けるHugh Kerry Jnr.がツアー時のセカンド・ドラムとして加わった五人編成時のもの(1995年後半撮影)。左から時計回りにそのゲスト・メンバー、ヒュー・ケリーJr.、ダレン・ベルク(g.)、デイヴィッド・ルイス・ゲッジ、サイモン・スミス(dr.)、ジェイン・ロッキー(b.&back vo.)。
>> 26ページ目左「第六期のメンバー写真」
旧TWP最後となった第六期、後にシネラマ~新生TWPでも活動するサイモン・クリーヴ加入後のもの(1996年撮影)。左からサイモン・スミス(dr.)、ジェイン・ロッキー(b.&back vo.)、サイモン・クリーヴ(g.)、デイヴィッド・ルイス・ゲッジ。
>> 26ページ目右「CINERAMA第五期=TWP第七期のメンバー写真」
2003年に撮影されたCINERAMAの最後のラインアップ、即ち新生TWP始動時のメンバー写真。左からテリー・ディ・カストロ(b.&back vo.)、サイモン・クリーヴ(g.)、カリ・パーヴォラ(dr.)、デイヴィッド・ルイス・ゲッジ。
>> 35~36ページ目「デイヴィッド・ゲッジと故ジョン・ピールとの2ショット写真」
1996年頃に撮影されたもので、オフィシャル・ファンジンOrange Slices Issue 2 "Special John Peel Edition"の対談用に撮影されたもの。
関連文章 >> エラー・ブックレットの交換について [2007/3/28初出]
>> ニュース詳報 [2007/1/24初出]
外部リンク
(last modified : 10th April, 2007 / first published : 30th March, 2007) |