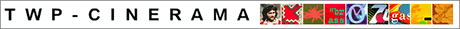
|
| >> HOME >> DISCOGRAPHY >> THE COMPLETE PEEL SESSIONS >> excerpts from liner notes by Ken Garner >> |
| ケン・ガーナー氏ライナーノーツ日本語訳(抄訳) スタジオの「録音中」の赤いランプが点灯しているのに気づいたのだろう。「テープ回ってるよ!」バンドの誰かが叫ぶ。 1986年2月11日、BBCのスタジオ、Maida Vale 5*0におけるこの12秒の即興のバカ騒ぎと、それに続くその曲の演奏は、当日バンドが録音した他の曲も同様にだが、この6枚組ものCDボックス・セットに何が収められ、そしてなぜそれを所有する価値があるのかを物語っている。 ザ・ウェディング・プレゼントはBBC Radio 1 「John Peel Show」でのデビュー・セッションをオレンジ・ジュースのカヴァー・ヴァージョン"Felicity"(作者はジェームス・カーク、先のウィリアム・シャトナーのジョークはその名前から来ている)で締めくくろうと決めた。理由はデイヴィッド・ゲッジがこの曲を好きだったからという事もあるが、一方でオリジナル・ヴァージョンのアレンジと録音の出来があまり良くないな、と感じていたからだった。バンドはこのボックスで聞ける12回分のうち3回のセッションを除いては少なくとも1曲のカヴァー・ヴァージョンをジョン・ピールのために録音している。ゲッジは言う「僕らなら何か違う解釈を加える事が出来る、と思った曲をカヴァーするのに、ピール・セッションの場を利用するのは好きだったんだ。」 "Felicity"を、そしてもちろん本セッションの他の傑出したオリジナル作"You Should Always Keep In Touch With Your Friend"、"This Boy Can Wait"を特色づけた、あの気違いじみた、あり得ないくらいに速くかき鳴らされるエレクトリック・ギターのサウンドは、リスナーたちにザ・ウェディング・プレゼントのサウンドとは何なのかをすぐに認識させる事になった。 わずか20ヶ月後に、全く異なるスタイルへと挑戦して周囲を驚かせた時でさえも、演奏にはまだ彼らだと分かる要素があった。あのハイ・スピードのギター・プレイは常にどこかしらにあったのだ。 からかってるのかい、だって?まあ、明らかに彼ら自身が楽しんでいたし、それを誰が責められるっていうんだい? でも、全ては最初のセッションにあったのだ…ライヴで演奏する事に対する愛情、それも驚くべきスピードでプレイする事、ソングライティングにおける一風変わったアプローチ、おざなりにされたポップ・ミュージックの過去の遺産に対する情熱、そしてそのセッションをラジオでオンエアするために、ちょっと並はずれたものにする挑戦をすること。 ジョン・ピールは確実にそう思っていた。最初のセッションは2月26日初回放送があってから数週間の間に2回再放送された。最初の再放送はわずか13日後である。The Stars of Heavenが1ヶ月前にデビュー・セッションを行い、2週間後にはWe've Got A Fuzzbox And We're Gonna Use Itが収録した。あの冬、そのセッションは早急に、そして立て続けに放送された。 しかし、これが彼らにとって本当に最初のBBCセッションでは無かった。実際には前年11月に ストックポートのYellow 2スタジオでアンディ・カーショウのショーのために録音を行っていた。BBCマンチェスター出身で1985年7月にRadio 1での番組をスタートさせたアンディ自身は、その時までにはロンドンのピール・ショーのプロデューサーであったジョン・ウォルターズに異動させられていた。デイヴィッド・ゲッジ自身カーショウとは70年代の終わりに共にリーズ大学の学生であったので何となく知った顔ではあった。彼はBBCでのキャリアの始まりとしては奇妙だったものの、これ以降に続くピール/ウォルターズ人脈につながったのだと考えている。後にピール・セッションへと連なる重要なショーではあったが、結局これ以降はカーショウのためにセッションは録音していない。 ゲッジは言う「ピールは番組出演者のブッキングに関しては身内びいきであるとは見られたくなかったと思うよ。水曜日のピールの番組でカーショウの番組の宣伝が流れていたんだけど、次の日の夜に僕らのセッションがアンディの番組で流れるっていう内容で、そのCMが流れた後、ピールはこんな風に言ったんだって『そうだ、そうこなくっちゃ!』。」 実際の所、ゲッジとピールは知り合いであった。1985年には現実に関わりがあったわけではないし、ピールの近親者とまではいかないものの、ゲッジは既におなじみの番組の投稿者になっていたし、1977年以来の常連リスナーであった。後に、この両者は友情を育んでいくことになる。2004年11月12日にジョンの告別式の後にレブンズクロフト家(ジョンの本名)の身内だけで行われた集まりにはポップ・スターたちはほとんどいなかったが、デイヴィッド・ゲッジはその中の1人であった。 しかし、ゲッジに番組のリスナーだったから最初の放送の機会を与えたとは見られたくない、という理由以上のものがその背景にはあった。ゲッジは何年もの間いくつかのバンドをやってきていて、以前のバンド、ザ・ロスト・パンダスのテープの事ではピールをしつこく悩ませていた。彼は北からピールのロードショー・ギグをやっていたスカンソープのScunthorpe Bathsホールにデモ・テープを渡すためにわざわざ旅してきた事もあった。また彼の昔の学友がいたバンド、ザ・カメレオンズがロンドンのRadio 1スタジオの前の階段に一日中座って彼を待ち伏せしてデビュー・セッションを勝ち取ったという逸話に倣って、声を掛けてテープを渡そうとジョンが来るのを待ちわびたこともあった。 でも、それは無駄骨だった。せっかくのチャンスをつかんだ時には、ザ・ロスト・パンダスの2人のメンバーが脱退し、残されたのはゲッジとバンドの音楽的な方向性の形成に一役買ったベーシストのキース・グレゴリーだけだった。ゲッジは学生時代の旧友、ピーター・ソロウカを誘った。新しいドラマーのショーン・チャーマンはバンドのサウンドをさらに加速させ、よりハードに、よりパンキッシュなものにし、彼らの古いレパートリーのいくつかは新しいアレンジで変化を加えられた。そしてバンドは改名する。ロマンティックで、より際立った名前に。同時に自身のレーベル、リセプション・レコーズも立ち上げ、新しいスタートを切った。 デビュー・シングル"GO OUT AND GET 'EM BOY!"は1985年5月に発表。ついにピールを認めさせ、彼はその春何度かその曲をオンエアした。それはギグの契約やカーショウの番組のセッションへと結びつき、曲自体もその年のフェスティヴ・フィフティで15位にランクインしている。そしてピールとの関係はあの最初のセッションによってようやく成就する事になった。1995年のフェニックス・フェスティヴァルが収録されたディスクの終盤では放送に乗った二人の肩肘張らない会話がお聞き頂けるだろう。またゲッジはフェスティヴ・フィフティの歴史のエキスパートとしても知られており、2000年12月19日にMaida Valeスタジオから放送された「フェスティヴ・フィフティ25周年記念スペシャル」では問題出題者と審判として出演できるほどであった。 いずれにせよ、ザ・ウェディング・プレゼントはピール・セッションの典型的なお気に入りバンドとなった。ザ・フォールは24回のセッションを収録(その全ては現在ではSanctuaryから発売された必須の6枚組CDボックスで聴ける)、アイヴァ・カトラーは22回、アシュリー・‘タイガー'・ハッチングスは様々なバンドで15回、そしてロバート・ロイドが14回。ザ・ウェディング・プレゼントの12回はそれに次ぐ回数という事になる。もしそこにゲッジがザ・ウェディング・プレゼントの再始動前の6年間、1998年から2004年にやっていたシネラマ(現在Sanctuaryは今回のものに似たコンプリート・ボックスを今年の後半に発売するべく計画中)の10回分*1を足せば、ゲッジはピールに最も重用されたブリティッシュ・ミュージシャンの1人という事になる。しかしそれでも、ピールのRadio 1での1967年から2004年までの放送…約6,000回にも及ぶ放送回数、12,000時間を超える放送時間、そして4,000ものライヴ・セッションの中では微々たるものである。 レディオ・セッションはジョン・ピールが発明したものではなかった。彼は自分の名前を冠したもののプロデュースをしたり企んだりする事はなかった。そのビジネスから彼はびた一文受け取る事はなかった。後年で特に顕著なのだが、木曜夜の放送でサフォークの田舎にある彼の自宅からバンドがライヴ演奏をしたり、Maida Valeからライヴを放送する様な素晴らしい例外が無ければ、彼はその場に居合わせる事さえ無かったのだ。 1970年代まで、BBCラジオ局でかけられていたポップとクラシック音楽の大半はレコードを使ったものではなく、雇われたミュージシャンやバンドが「ライヴで」演奏したもの…コンサートをそのまま生放送または収録したものか、またはBBCのスタジオで予めセッションを録音したものだった。ミュージシャンたちの組合の支持で、BBCにはレコード会社からレコードを放送でかける回数が限定される「ニードルタイム」*2の制限があったからだ。1967年にRadio 1が開局した時、トニー・ブラックバーンの朝の番組しかなかったが、100%ニードルタイムの制限がかかっていた。同局の他の番組もその放送時間の60%から80%は局独自のBBCセッションで構成されていた。ピールの最初のRadio 1での3時間番組、『トップ・ギア』ではそういう理由で各回最低でも6つのセッションが放送されていたのだ。 ピールと彼の初期のプロデューサーたち、特にバーニー・アンドリュースの功績は、このBBCのシステムをその時代で最も新しい、エクスペリメンタルなバンドたちに合わせた形に変えた事だ。バーニーはバンドにダビング、テーク・バックを聞く事、そして出来る限りデカい音で演奏することを許可したBBC初のプロデューサーだった。この決定により、ピールの番組でプロデューサーを始めてたった18ヶ月しか経っていなかったこの人物は、75もの最初の放送を勝ち取ったのだ。その中にはピンク・フロイド、トラフィック、ザ・ナイス、フリートウッド・マック、ファミリー、ザ・プリティ・シングス、フェアポート・コンヴェンション、デイヴィッド・ボウイ、そしてソフト・マシーンが含まれていた。それらはRadio 1の放送開始12週間、1967年のクリスマスまでに全て放送された。 ニードルタイムの制限は1988年には廃れていったが、その頃までには、ピールと彼の次のプロデューサー、ジョン・ウォルターズのエナジーはパンクやレゲエ、ニュー・ウェイヴの録音と放送に注がれていた。70年代の終わりからどの媒体よりもいち早く取り上げ、おそらくはほとんどのレコード会社よりも早くバンドと契約し、Radio 1セッションはBBCからもはや必要悪なものではなく、好意的に捉えられるようになった。 1986年に話を戻して、ピールはザ・ウェディング・プレゼントをもう1度Maida Valeに迎える事を決める。最初のセッションからわずか6ヶ月後の事である。残念ながらベーシストのキース・グレゴリーは参加できず、その為ライヴのサウンド・マンであるマイク・スタウトが代理を務めた。またこのセッションは気難しいフリーランスのプロデューサーとして有名なデイル・グリフィンとの初遭遇であり、緑の、巨大な洞窟のような、古めかしいビッグ・バンド用のスタジオ、Maida Vale 3での初レコーディングでもあった。おそらくはこういう悪い偶然が重なったせいでもあるだろうが、グループにとっては最も印象に残らないピール・セッションになってしまった。80年代中期のジャングリーなインディー・ポップの基準からしても、これは少し場違いなものでもあった。結局このセッションは正式にはリリースされず、演奏された曲のうち3曲がシングルのB面にとどまっている。 しかし、このセッションには唯一貴重な録音がある。最後におまけとして、リハーサルのウォーム・アップ用に、ピーター・ソロウカが幼少時から慣れ親しんでいたというウクレイニアン・フォーク"Hopak"をレコーディングしているからだ。このアイデアは後に大輪の花を咲かせる事になる。 その4ヶ月後には3回目のセッションが行われる。このセッションでは半年後の1987年10月に発売される素晴らしいデビュー・アルバム『ジョージ・ベスト』(2007年にはSanctuaryから20周年記念の再発が計画されている)からの新曲が3曲披露された。マイク・ロビンソンとマーティン・コリーがエンジニアリングを担当し、彼らがやってきたことがようやく実を結びつつあったこの魅力的な時期のライヴ・サウンドがうまく捉えられた、スリリングなパフォーマンスが収められている。猛烈な最後の曲はリーズのバンド、ガールズ・アット・アワ・ベスト!のパンキーな"GETTING NOWHERE FAST"のカヴァー。後にピールはこう語った。「彼らはこのセッションで本当に良い選曲をしたね。」 しかし、次に起こる事にしてみたら、大した事ではなかった。 これはピ-ター・ソロウカのアイデアだった。「全てウクレイニアン・フォーク・ソングをやるっていう、何かラディカルな事をやりたいって提案してて、他のメンバーを説得したんだ。」ピーターの友人で、スラブ言語の愛好家だったレン・リギンズが加わり、この拡張されたラインアップでMaida Valeに向かった。彼らは5曲を準備したが、「よく目立つズボらな格好していたデイル・グリフィンが言ったんだけどね」ゲッジは述懐する。「君らは今回4曲しかできないよって。だから僕らはこっそり"Katyusya"と"Moon Shines"を合体させたんだよ。であたかも1つの曲名であるかの様に呼んでね。"Katyusya Moon Shines"ってね!」 その放送は楽しく聞こえるもので、実際のリスナーたちにも同様に受け取られた。しかしその放送が流れた時にはメンバーたちは次にはもっと上手く出来る事を再認識した。そこで2度目となるウクレイニアン・セッションは1988年の3月に早々と行われている(新しいドラマー、サイモン・スミス加入後、初のセッションであった)。今回は(彼のウクライナ語の名前は発音出来ないため)自らRoman Remeynesと名乗るウクライナの曲を知っているミュージシャンが加わった。初回放送の4月5日、セッションを締め括った驚くべき7分もの大曲"Verkhovyno"がフェード・アウトした時、ピールはこう結んだ「何て素晴らしいんだ!私には他のバンドがこういう2つの全く異なる次元の事を、ここまで上手くやり通せるとは思えないよ。最高のセッションだったと思うね。」放送を聴いた多くのウクライナ人たちはバンドに、ウクライナの曲がこんなに激しく演奏されたのを聴いた事が無いと言った。ソロウカは当時を振り返って「デイルとマイクは"Verkhovyno"のミックスにはずいぶん骨を折ったんだ。午前2時45分になってもまだスタジオに居残っていたからね。その結果は、本当に良かったよ。」 1年後、バンドがRCAレコーズと契約を交わした後、これらのセッションをまとめた『Ukrainski Vistupi V Johna Peela』は(おかしな事に)彼らにとって最初のメジャー・レーベル作品になり、40,000枚以上のセールスを売り上げ、アルバム・チャートで最高位22位を記録した。しかし決して忘れてはならないのは、この陽気なパフォーマンスがラジオ無しには、そしてピール・セッションが体現してきた自由とクリエイティヴィティ、リスク無しには存在しなかった事だ。20年経ってもこの音源にまだ魅力と感動があるのだとすれば、それは古き良きラジオのロマンスがかすかな光を宿しているからに他ならない。 1989年5月、これら2度のウクレイニアン・セッションが発売された1ヶ月後には3度目のウクレイニアン・セッション(このボックスでも聴ける)が行われたが、1991年にピーター・ソロウカがバンドを脱退した後、彼とレンとローマンは永久的にザ・ウクレイニアンズとなり、彼ら自身の曲を収録したアルバムを発表すると同時に、当然の成り行きながら、11月にはザ・ウクレイニアンズ名義でのピール・セッションも収録している。今回のボックス・セットのために、ゲッジとソロウカはウェディング・プレゼントのウクレイニアン・セッションのナンバーが放送された時のBBCのキュー・シートにあったいわゆる曲名間違いを正してくれたが、これには混乱を来したし、恥ずかしさも覚えた。 1988年春、2度目のウクレイニアン・セッションが1回目と2回目の再放送をされている間の週に、バンドは通常編成で新曲の録音と放送を行う。今回もエンジニアのマイク・ロビンソンが、当時における最強の3曲の新曲を、バンドのライヴさながらの激烈なサウンドを写し取った。4ヶ月後にリリースされたシングル"Why Are You Being So Reasonable Now?"、1989年9月*3のシングル"Kennedy"のB面曲となった"Unfaithful"、そして当時のライヴではハイライトとなっていた長尺曲"Take Me!"は16ヶ月後の1989年10月にRCAからのセカンド・アルバム『Bizarro』で陽の目を見ることになる。そこにゲッジのフェイヴァリット・バンドの1つであるオルタード・イメージズの"Happy Birthday"のエネルギッシュなカヴァーが加わえられた。ピールの皮肉っぽいコメントが全てを物語る。「ザ・ウェディング・プレゼントには容赦なく打ちのめされるね」。この回のセッションは愉快だった。"Take Me!"ではステイタス・クオ・スタイルのリフに合わせて頭を動かしたくなり、そして"Happy Birthday"ではゲッジが「25年前と変わらぬ味、ステイタス・クオでございます!(Status Quo - 25 Years in The Business!)」*4 と叫び、みんなが同意の声を挙げている。 1989年8月29日火曜日にはロンドンのSubteraniaクラブでさらなる祝宴が待っていた。ピールの50歳誕生日記念のサプライズ・パーティーのためのライヴが行われ、ザ・フォールやザ・ハウス・オブ・ラブと共に出演した。ライヴは録音され、ピールの実際の誕生日である翌日の夜に放送された。しかしBBCの全プログラムが保管されたテープ・アーカイヴには、スタジオで事前収録したものは残っていたが、バンドのセットを収めたテープは消失してしまっていた。よってこのボックスで聴けるライヴはウェディング・プレゼントのファンがFM放送から録音したカセットから使われている。ゲッジは言う「これはマスタリング・エンジニアのアンディ・ピアースの技術が試されるものだったね。彼は出来る限りオリジナル音源に近いサウンドに仕上げたよ。」おそらく前年のセッションの時よりは宣伝のためにこの場を使おうという知恵が働いたのだろう、バンドは数週間後にリリースされる『Bizarro』から6曲をぶっ放した。 パーティーが終わり、ピールとバンドとの関係も第一章の終わりを告げた。 バンドが次にピールのためのセッションを録音したのは1990年10月の事。その内容は1988年5月のセッションを遙かに凌駕するものであった。カヴァー・ヴァージョンは無し、スタジオ内のふざけ騒ぎも無し、やたらと速いエレクトリック・ギターの演奏も無し。それでもなお、そのサウンドはウェディング・プレゼントそのものでしかなかった。ここでは数ヶ月後に発売されるスティーヴ・アルビニ録音の『SEAMONSTERS』で発表される新曲4曲が録音され、抑制され過剰に電気増幅されたエレクトリック・ギターによる憂鬱な4分間の叙事詩がそこに並んだ。グループの音は完成され、自信に満ちあふれ、統制が取れたものになっていた。そこには1本か2本のオーヴァー・ダブも施された。今聴いてみても、なぜこのセッションがゲッジにとって最もお気に入りの、そしてバンドの最高の瞬間を捉えたものと考えているのか分かるはずだ。「(2回目のセッションで使用した)オーケストラルなレコーディングのために作られた巨大なスタジオMaida Vale 3と、(今回は)思いやりのある技術スタッフが見事に調和して、ジャングリーなインディー・ポップから暗く、より陰気なノイズを奏でるようになっていったバンドのサウンドを捉える事が出来たんだ。」 ベーシストのキース・グレゴリーのアイデアで、毎月限定の7インチ・ヴァイナル・シングルをリリースする事を決定した1992年は、今度はバンドが自身の伝説を作り上げる事になった。12枚のシングル全てがチャートのトップ40入りを果たし、1年間でのチャートイン曲数の公式記録であのエルヴィス・プレスリーとザ・ウェディング・プレゼントが肩を並べる事になったからである。ピールは各月のリリースを積極的に番組で紹介し続け、もはや彼のセッションに招かない訳にいかなくなった。バンドは抜け目なく、全てのA面12曲をBBC Radio Leeds、BBC World Service、そしてRadio 1のマーク・グッディヤーと、BBCの様々な番組のセッションで録音している。ピール・セッションは3月に行われ(新ギターリスト、ポール・ドリントン加入後初のセッションだった)、この年の5月、6月、7月に発売される事になるシングルを演奏。詩的にも動的にもハイライトとなった"Come Play With Me"、そして悪名高い“失われた"曲"Softly Softly"もあった。 「これが現存する、この曲の唯一残された録音だよ。」とゲッジは説明する。「僕らは元々はこの曲をHit Paradeシリーズの12曲のA面曲の1つに考えていたんだけども、このセッションのすぐ後になって、あんまりこの曲良いと思わないなあ、と考えてね。でも不思議な事に、今聴くと僕には大丈夫だと思えるんだけどね。ピール・セッションで新しい曲を試すときのメリットでもあったんだよ。ピール言うところの“未完成品"というやつでね。曲はお蔵入りしたけれども、僕はサビの部分を別の曲で救済する事に決めた。最終的にIslandレコーズから発売されたシングル"Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah"でね。この曲のライヴ・ヴァージョンがCD4で聴けるよ。2曲の、同じサビを共有する曲という事だね!」 それから2年後の、新しいレーベル(Island)と契約を結び、新しいベーシスト(ダレン・ベルク)と共に、Hit Paradeシリーズよりも驚くほど明るく、ポップさの増したサウンドを披露した1994年3月のセッションで注目すべきは、後のアルバム『Watusi』での録音とライヴ(ここではCD 4の1995年フェニックス・フェスティヴァルでのものが聴ける)ではもっぱらアクースティック・アレンジで演奏されていた"Gazebo"と"Spangle"という2曲のエレクトリック・アレンジでのレコーディングである。ウェディング・プレゼントの専門家として知られるレイ・ハント氏はこう発言する。「何人かのファンからセッション・ヴァージョンの"Gazebo"と"Spangle"の方が高く評価されているね。実際多くの人に『Watusi』での華奢なヴァージョンよりもこのロック・ヴァージョンの方が好まれている様だしね。」 次のピール・ショーへの出演となった1995年フェニックス・フェスティヴァルでのライヴ・セットはこれらアクースティック・アレンジでの演奏を含む『Watusi』からの楽曲が大半を占め、またジェイン・ロッキーがベースにフィーチャーされた初めての機会(これにより、ダレン・ベルクはギターに転向)でもあり、最後の2曲では1996年まで続けられるダブル・ドラム編成が初披露されたものでもあった。ピール自身の発言通り、ミティ・アディカリと彼のエンジニア・チームは素晴らしいライヴ放送のサウンドを作り上げ、このライヴ・セットと翌年の生放送となったリーズでのRadio One Sound Cityフェスティヴァルは轟くようなサウンドで幕が切って落とされる…ライヴの現場に携わる関係者全員にとってこれは容易な事ではない。特に1つのステージをいくつかのバンドがシェアする様な場合には、幕間にかなりのセットチェンジを余儀なくされてしまうからだ。またラジオのライヴ放送には急に出力バッファがダウンしてしまう危険が付きまとうが、リーズのパフォーマンスではものの見事に、"Click Click"の最初の数秒で全ての音が消えてしまった。しかし全員が冷静沈着に対処し、程なくしてシステムが復旧している。ゲッジは指摘する。「多くの“ライヴ"・アルバムに収められている、リリース前に(言ってみれば)“手心加えた"パフォーマンスとは違って、このボックスで聴けるライヴ・パフォーマンスは長所も短所も含めありのままをミックスしたもので、ものによってはライヴ放送時そのままだから、その時以来音は一切いじっていないんだ。あの"Click Click"の中断箇所や、歌詞を飛ばしちゃっているシーンが聴けるのがその証拠だよ。」 Sound Cityの4ヶ月前には、このダブル・ドラム編成で来るミニ・アルバム『Mini』からの新曲を、バンドの最初のキャリアにおいては最後となったピール・セッションでお披露目している。大部分はドライブをテーマにしたここでの楽曲は所々軽やかで、ほとんどはちょっと風変わりで、おそらくゲッジの中ではまだそのアイデアははっきりと浮かんでいない頃ではあったが、その後のシネラマを思わせる要素も感じられるものであった。 ミュージシャンたちに特定のピール・セッションを収録した際のことで思い出す事は何か?と質問する事は、ほどんど実りの無いものであった。例えば学校の先生に受け持ったクラスで起こった出来事を訊くとか、もしくは画家にその絵を描いた時になぜその絵の具を選んだのか訊く様なものだろう。 残された目標は、その時どう感じたかを聞き出す事である。 ピール・セッションはライヴ・ギグとも、レコード制作とも違っていた。しかし、両方の要素がそこにはあった。その音楽の大半、楽器が奏でるバックトラックは通常演奏するように、ライヴで一緒に演奏していた所を録音していたからギグの様ではあった。しかしゲッジが説明するにはレコード制作にも似ているところがあったという。「“ライヴさながらに"セッションは録音されていたけど、演奏をミスったら止める事もできた。もしくは間違いを修正するために後で“パンチ・イン"したりね。」 こう考えてみたらどうだろう。ある男が午後に4人のミュージシャンに演奏させ、録音するために部屋に招く。彼と彼のスタッフはミュージシャンが望むものは全て提供する。しかしバンドには主導権がある。録音のプレイバックも聴ける、希望するならその日の終わりにちょっとした追加録音だって出来る。そして、その数日後か数週間後、その男は別の部屋に腰掛け、その録音を再生し、ラジオの魔法を介して、それぞれの家の部屋にいる、何万人という人々の元に届ける。 「まあ、このセッションは彼らがここ数年やってきたどんなセッションよりも良いものだったと思うね。」2004年9月21日に放送された、新生ウェディング・プレゼントが行った12回目のセッションの最後にピールが言った言葉である。彼がペルーでの休暇中に、心臓発作で急逝する5週間前のことであった。 彼の言葉は正しかった。バンドにとってもこれは特別な機会だった。ベーシストのテリー・ディ・カストロは収録したあの日、デイヴィッド・ゲッジを迎えるためにMaida Valeに集まってきたエンジニアとプロデューサーたちの多さに驚いたという。彼がそこにいるほぼ全員を知っていた事に、彼女は気がついたという。彼、そしてそのバンドは、ここからやって来たのだと。 あの日彼らが生み出した音楽にその全てが表されている。セッションがスタートするまでの空き時間に録られた、懐かしい"Blue Eyes"で聴ける確信に満ちたエレクトリック・ノイズから、古くさいロマンティックな"White Horses"のTVテーマのカヴァーまで、このセッションは古典となった。シネラマのセカンド・アルバム以来からの付き合いとなったギターリストのサイモン・クリーヴとディ・カストロの二人に、ドラマーのカリ・パーヴォラを伴ったバンドのサウンドはその特有の響きと共に、ヒリヒリする様なエッジを再活性化させた新しいウェディング・プレゼントへと変化を遂げた。ここには3曲の新曲があり、うち2曲は5ヶ月後に発表される、高評価を受けた復活作『Take Fountain』でお目見えする事になる。その新曲はかつての"My Favorite Dress"や"Heather"にも匹敵する、詞作における感情に訴えかける全体性を表している。"Ringway to Seatac"はゲッジの最高の瞬間を捉えたものの1つであり、この放送を聴いたものみんなに彼がどれほど力強いソングライターなのかを印象づけた。 我々皆それぞれが人生の中で、道や衣装や橋などの日常のありふれた出来事や場所と関連付けられて忘れられない想い出と共にある、ターニング・ポイント迎える事があると思う。僕の場合で言えば、クリスマスにグラスゴーの端にあった新しい家から400マイルも遠く離れたハンプシャーの姉を訪ねるために、日が暮れた野原をひたすら車でぶっ飛ばしていた時の事だ。日付は1986年12月22日月曜日。ヘッドライトの中にウサギが飛び出してきたその瞬間、ピールがその年のお気に入りのセッションを流していたラジオから"You Should Always Keep In Touch With Your Friend"が流れてきた。その歌詞は僕が出くわした状況には全く似つかわしくないものではあったけれど、その時抱いた気持ちにはぴったりだった。ピールとウェディング・プレゼントに感謝を。僕は絶対にこの時の事を忘れないよ。 ケン・ガーナー(2007年記)
(last modified : 10th April, 2007 / Japanese translation by YOSHI@TWP-CINERAMA) |
| △TOP |
TWP-CINERAMA[dbjp] is not responsible for the content of external sites.
© TWP-CINERAMA[dbjp] All rights reserved by Yoshiaki Nonaka except where noted.