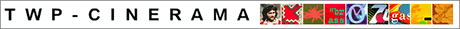Side 1 -- Everyone Thinks He Looks Daft
- What Did Your Last Servant Die Of?
- Don't Be So Hard
- A Million Miles
- All This And More
- My Favourite Dress
Side-2 - Shatner
- Something And Nothing
- It's What You Want That Matters
- Give My Love To Kevin
- Anyone Can Make A Mistake
- You Can't Moan Can You?
*bonus tracks for Japanese edition (VJR-3205)
Recorded Live At The Edge Of The Sea 2017- A Million Miles
- Shatner
- Something And Nothing
- Give My Love To Kevin
作品概要/解説 事の発端は2007年10月のこと。ザ・ウェディング・プレゼント(以下TWP)の1987年10月12日にリリースされた記念すべきデビュー・スタジオ・アルバム『George Best 』の発売20周年を記念して、同作を曲順通りに演奏するツアーが行われた。元々は1987年10月当時の同作発売に合わせたイングランド・ツアー(10都市10公演)と同じ都市を回るコンセプトだったのだが、イベンター、プロモーターからの反響が余りに大きく、結果的にこの『George Best
』の発売20周年を記念して、同作を曲順通りに演奏するツアーが行われた。元々は1987年10月当時の同作発売に合わせたイングランド・ツアー(10都市10公演)と同じ都市を回るコンセプトだったのだが、イベンター、プロモーターからの反響が余りに大きく、結果的にこの『George Best 』発売20周年記念ツアー(以下GB20ツアー)は9ヶ国35公演にも及ぶ大規模なツアーに発展することとなった。
』発売20周年記念ツアー(以下GB20ツアー)は9ヶ国35公演にも及ぶ大規模なツアーに発展することとなった。
それも当然の反応ではあった。デイヴィッド・ゲッジは旧TWP、CINERAMA、そして新生TWPに至るまで、常に新作スタジオ・アルバムの楽曲の実演を主軸としたライヴを行なうことを信条としていたからだ。確かにCINERAMAでの商業的な実りはあまりに少なかった6年間の冒険を経た2004年9月の再始動後、『Take Fountain』リリースに合わせてスタートした長期間に及ぶツアーでの旧TWP時代の名曲をふんだんに織り交ぜたセットリストはかつてのTWPのファン達を再び振り向かせることにはなったが、かと言ってデイヴィッド自身はこういう懐古的なコンセプトには明確に拒否反応を示していたタイプのアーティストでもあったから、この様な企画が新旧のファンに歓迎されるのは目に見えていた。結果この「全曲再現ツアー」は興行的に大成功を収め、またデイヴィッド自身も考えを新たにすることにもなった。「現在の作品と同じ様に、過去の作品も大事にしなければならないと気がついたんだ」と。
以降、このレトロスペクティヴな企画は新作スタジオ・アルバムをメインとするツアーを挟みながら断続的に繰り返されて来たのは皆さんご存知の通りだ。東京でも1989年作『Bizarro』の発売21周年となった2010年5月に全曲再現ライヴが行なわれ、その模様は日本限定の2枚組ライヴ・アルバムとしてまとめられたし、『Valentina』発売年となった2012年4月には2日公演のうち1日が1991年作『Seamonsters 』の全曲再現、2013年3月には自身2度目となる『George Best
』の全曲再現、2013年3月には自身2度目となる『George Best 』再現ツアー、そして1992年の月刊シングル・シリーズ『 The Hit Parade
』再現ツアー、そして1992年の月刊シングル・シリーズ『 The Hit Parade  』A面曲全曲再現ツアーの一環として2日間公演が行なわれ、それぞれに強烈な印象を残すことになった。
』A面曲全曲再現ツアーの一環として2日間公演が行なわれ、それぞれに強烈な印象を残すことになった。
そんな全曲再現ツアーの企画も1997年の活動休止以前の旧TWP時代のスタジオ作は一巡したが、2017年はちょうど『George Best 』発売30周年にあたることもあり、今度はGB20ツアーの時とは異なり、様々な音楽フェスティヴァルからの引き合いや各国のプロモーターからのオファーもあり、自身3度目となる『George Best
』発売30周年にあたることもあり、今度はGB20ツアーの時とは異なり、様々な音楽フェスティヴァルからの引き合いや各国のプロモーターからのオファーもあり、自身3度目となる『George Best 』全曲再現ツアー(以下GB30ツアー)が開催されることになった。しかしこのGB30ツアーで『George Best
』全曲再現ツアー(以下GB30ツアー)が開催されることになった。しかしこのGB30ツアーで『George Best 』の全曲再現は最後にすることをデイヴィッドは明言している。「もう潮時だと思ったから」というのが理由とのことだが、新曲作りに自身のアーティスト生命を懸けて挑み続けているかの様なデイヴィッドの姿勢からするといつまでも同じ手法や懐古的なツアーを繰り返したくない、というのが正直なところだろう。ただ、一方では『Bizarro』の発売30周年にはオファーがあれば喜んで全曲再現ツアーをやることも公言しているから、ニーズがあれば今後も(ややジレンマを抱えながらも)応え続けてくれるのだろうなとも、ファンサービス精神旺盛なデイヴィッドの性格からすると頷けるのだけども。
』の全曲再現は最後にすることをデイヴィッドは明言している。「もう潮時だと思ったから」というのが理由とのことだが、新曲作りに自身のアーティスト生命を懸けて挑み続けているかの様なデイヴィッドの姿勢からするといつまでも同じ手法や懐古的なツアーを繰り返したくない、というのが正直なところだろう。ただ、一方では『Bizarro』の発売30周年にはオファーがあれば喜んで全曲再現ツアーをやることも公言しているから、ニーズがあれば今後も(ややジレンマを抱えながらも)応え続けてくれるのだろうなとも、ファンサービス精神旺盛なデイヴィッドの性格からすると頷けるのだけども。
前置きが長くなったが、本作『George Best 30』は文字通り、そんなGB30ツアーに合わせてリリースされたカタログであり、またTWP名義では初めて同一アルバムを全曲再録音することになった企画色の濃い作品でもある。
その録音自体は実は9年前に行なわれたものになる。先のGB20ツアー終了後、2008年1月に、通算8作目となるスタジオ作『El Rey』に収められるマテリアルをレコーディングした米シカゴのElectrical Audioスタジオで同作を録音、共同プロデュースすることになったSteve Albiniによって、ほぼスタジオ・ライヴの様な形(デイヴィッド曰くの初期のThe Beatlesのスタイル)で録音されている。しかも『El Rey』本編を全て録り終えた後の空き時間を利用して、である。
まるで都市伝説の様な話でもあった。何しろ『El Rey』セッションではアルバムに収められた楽曲を含め1週間で17曲がレコーディングされている。ほぼ一発録音とは言え、そんなモチベーションと体力がどこに残っていたのだろうか?『El Rey』の新曲の充実ぶりと完成度の高さもまたそんな噂話レベルのエピソードに半信半疑になる所以でもあったのだ。
その噂のテープの存在が俄然信憑性を帯びることになったのが、デイヴィッド・ゲッジが公式Twitterで公開した1枚の写真だった。2014年1月26日の投稿で「'George Best', re-recorded by Steve Albini in 2008. It's about I got this baby mixed.」(『George Best 』スティーヴ・アルビニ2008年再録音版。そろそろこの子をミックスダウンしないとね。)というコメントと共にアップロードされたのは、確かにElectrical Audioのキューシートと共に「TWP'S」とマジックで書き込まれたテープリールの写真。そして箱のラベルには2テイク録られた"Shatner"を含む13曲の曲名がしっかり確認できる。
』スティーヴ・アルビニ2008年再録音版。そろそろこの子をミックスダウンしないとね。)というコメントと共にアップロードされたのは、確かにElectrical Audioのキューシートと共に「TWP'S」とマジックで書き込まれたテープリールの写真。そして箱のラベルには2テイク録られた"Shatner"を含む13曲の曲名がしっかり確認できる。
レコーディングから6年目にして遂に明らかにされた『George Best 』Steve Albini再録音版。しかしここでコメントされていた通り、あくまでそのテープはミックスダウン前のものであり、ミックスダウンは別のエンジニアに任せるつもりだということもデイヴィッドは明かしていたが、結局2014年にはその作業は行なわれず、さらに3年の月日が流れることになった。
』Steve Albini再録音版。しかしここでコメントされていた通り、あくまでそのテープはミックスダウン前のものであり、ミックスダウンは別のエンジニアに任せるつもりだということもデイヴィッドは明かしていたが、結局2014年にはその作業は行なわれず、さらに3年の月日が流れることになった。
ミックスダウンを最終的に手がけたのが2012年作『Valentina』のミックスダウン、そこでの手腕を買われ続く2016年作『Going, Going... 』では録音、ミックスダウン、共同プロデュースと全面的に関わることになったAndrew Scheps。『Valentina』のミックスダウン作業の際にオリジナルの『George Best
』では録音、ミックスダウン、共同プロデュースと全面的に関わることになったAndrew Scheps。『Valentina』のミックスダウン作業の際にオリジナルの『George Best 』を聴きながら再録音版のミックスダウンをオファーし、Andrewが快諾して実現することになったという逸話がこの『George Best 30』の当時のメンバー、Terry de Castroによるライナーにも記されている。
』を聴きながら再録音版のミックスダウンをオファーし、Andrewが快諾して実現することになったという逸話がこの『George Best 30』の当時のメンバー、Terry de Castroによるライナーにも記されている。
つまり構造としてはGB20ツアー時のラインナップにより録音されたテープを、発売30周年を記念してGB30ツアーに合わせ、パッケージにまとめられたのが本作ということになる。またElectrical AudioでSteve Albiniが録音した音源を別のエンジニアがミックスダウンしたという制作プロセスは、Cinerama名義の2000年作『Disco Volante』と2002年作『Torino』と実は全く同じでもある。
デイヴィッドは本作を「デビュー・アルバムのre-imagining版」と表現している。文字通り「新たに創造したもの」ということになるが、GB20ツアーでは同作LPの曲順通り、アレンジもほぼそのままで再現し、1987年当時から1度もライヴ演奏されていない楽曲(ラストの"You Can Moan, Can You?")も演奏されることになった。そのGB20ツアーからの初音源となった今年リリースされたライヴCD+DVD作『LIVE 2007 』を聴いてもよく分かるが、『George Best
』を聴いてもよく分かるが、『George Best 』の歌詞にあったナイーブさにアンサンブルの華奢さ、あまりにスタジオでの手を加えすぎたサウンドのオーヴァー・プロデュース感を払拭する骨太なアンサンブルが印象的で、このツアーこそが文字通りの意味での同作のre-imaginingの機会になったのだと思う。そのre-imagining版を音源として記録して残すのに最適だったのがツアーの勢いのまま突入した『El Rey』セッションで使用したElectrical Audioと4度目のタッグとなったSteve Albiniという、屈指のアナログ・レコーディング対応のスタジオとエンジニアだったわけで、当のSteve Albiniは気乗りしなかったとのことだが、手早くプロフェッショナルとしての仕事で応えた。当時のデイヴィッドはこの様な全曲再現のツアーは最初で最後の企画と考えていたから、この機会を逃すと、先に同じ様なことは出来ないと確信して、Steveを説き伏せてこの録音を敢行したのだろう。
』の歌詞にあったナイーブさにアンサンブルの華奢さ、あまりにスタジオでの手を加えすぎたサウンドのオーヴァー・プロデュース感を払拭する骨太なアンサンブルが印象的で、このツアーこそが文字通りの意味での同作のre-imaginingの機会になったのだと思う。そのre-imagining版を音源として記録して残すのに最適だったのがツアーの勢いのまま突入した『El Rey』セッションで使用したElectrical Audioと4度目のタッグとなったSteve Albiniという、屈指のアナログ・レコーディング対応のスタジオとエンジニアだったわけで、当のSteve Albiniは気乗りしなかったとのことだが、手早くプロフェッショナルとしての仕事で応えた。当時のデイヴィッドはこの様な全曲再現のツアーは最初で最後の企画と考えていたから、この機会を逃すと、先に同じ様なことは出来ないと確信して、Steveを説き伏せてこの録音を敢行したのだろう。
ただ個人的には、いくらデイヴィッドがデビュー作に対し、特にサウンド面での不満を長年募らせていたのだとしても(2014年の欧州Edselからの4枚組エクスパンディッド・エディション はリマスタリング効果もあって、だいぶマシには聴こえる)、この再録音版は違和感を残すものになるのではないかと心配してもいた。別にTWPに限ったことではないが、ロック・バンドのデビュー作は多くの場合、まだバンドを始めて間もない若いバンドマン達が、必死にもがきながらも、懸命に自身の演奏をレコードにまとめるために奮闘している様子が伝わるからこそ胸を打つものになっていることが多く、殊この『George Best
はリマスタリング効果もあって、だいぶマシには聴こえる)、この再録音版は違和感を残すものになるのではないかと心配してもいた。別にTWPに限ったことではないが、ロック・バンドのデビュー作は多くの場合、まだバンドを始めて間もない若いバンドマン達が、必死にもがきながらも、懸命に自身の演奏をレコードにまとめるために奮闘している様子が伝わるからこそ胸を打つものになっていることが多く、殊この『George Best 』はそれらに加えて10代後半から20代前半にかけての、どちらかというと冴えない男性諸氏の多くが抱くだろう何とも情けない恋愛感情、または恋愛関係にも至らない横恋慕、片思いの様子が、身に覚えのある独特な傷みと共に綴られているから、余計に厄介な、非常に厄介な共感を産む要因になっている。演奏が上手くなくても、サウンドがオーヴァーダビングのやり過ぎでやたらとリヴァーブがかった貧弱な印象を残すものだとしても、この歌詞の世界とは決して相容れないものではなかった。"A Million Miles"の主人公のように、恋焦がれてどこまでもどこまでも歩いて行けるような何とも言えない気分や、"Don't Be So Hard"の今となっては笑うしかないライミングと共に綴られる物語は、あの時代のTWPだからこそ、そしてこの華奢な音像だから表現できた希有なものだし、ライヴの実演の場ならまだしも、それをスタジオ作品としてセルフカヴァーやリメイクされてもね、という不安は実際大きかったのだ。
』はそれらに加えて10代後半から20代前半にかけての、どちらかというと冴えない男性諸氏の多くが抱くだろう何とも情けない恋愛感情、または恋愛関係にも至らない横恋慕、片思いの様子が、身に覚えのある独特な傷みと共に綴られているから、余計に厄介な、非常に厄介な共感を産む要因になっている。演奏が上手くなくても、サウンドがオーヴァーダビングのやり過ぎでやたらとリヴァーブがかった貧弱な印象を残すものだとしても、この歌詞の世界とは決して相容れないものではなかった。"A Million Miles"の主人公のように、恋焦がれてどこまでもどこまでも歩いて行けるような何とも言えない気分や、"Don't Be So Hard"の今となっては笑うしかないライミングと共に綴られる物語は、あの時代のTWPだからこそ、そしてこの華奢な音像だから表現できた希有なものだし、ライヴの実演の場ならまだしも、それをスタジオ作品としてセルフカヴァーやリメイクされてもね、という不安は実際大きかったのだ。
『George Best 30』を聴いた今思うのは、確かに当時のラインナップによるライヴの延長線上にあるサウンドは迫力満点だし、音楽的にも、人間的にも長年の経験を経てストーリーに寄り添った歌唱表現に磨きがかかったデイヴィッドのヴォーカリストとしてのスキルやそこに込められるエモーションも上がったが、それが決してオリジナルの『George Best 』を凌駕するものでも、魅力を損ねる結果にもならなかったということ。単純な優劣を付けられるものではないし、原作に封じ込められたあの時代の空気感を含め、レコード=記録としての価値は些かも揺らぐことはない。一方原作に感じた新鮮さや何とも言えない迸りはここにもある。GB20ツアー当時のドラマーのグラエム・ラムゼイ、ギターのクリストファー・マッコンヴィルという、オリジナルの『George Best
』を凌駕するものでも、魅力を損ねる結果にもならなかったということ。単純な優劣を付けられるものではないし、原作に封じ込められたあの時代の空気感を含め、レコード=記録としての価値は些かも揺らぐことはない。一方原作に感じた新鮮さや何とも言えない迸りはここにもある。GB20ツアー当時のドラマーのグラエム・ラムゼイ、ギターのクリストファー・マッコンヴィルという、オリジナルの『George Best 』当時のTWPのメンバーたちと同様にまだ20代も半ばで、バンド経験も浅いスコットランド出身のメンバー2人の溌剌としたプレイもそんな作品全体のフレッシュな印象に大きく寄与している。クリスに至ってはこのTWPが人生で初めての本格的なバンドだったというのだから改めて驚くしかないが、その2人が解釈した『George Best
』当時のTWPのメンバーたちと同様にまだ20代も半ばで、バンド経験も浅いスコットランド出身のメンバー2人の溌剌としたプレイもそんな作品全体のフレッシュな印象に大きく寄与している。クリスに至ってはこのTWPが人生で初めての本格的なバンドだったというのだから改めて驚くしかないが、その2人が解釈した『George Best 』像もここには間違いなく反映されている。ただ"My Favourite Dress"のオリジナルのリズム・パターンから単純化し過ぎているプレイや(リズムキープだけがTWPのドラマーの仕事ではない)、"A Million Miles"の2番の後の間奏の省略は、「今日は百万マイルも歩ける気がするよ」という主人公の恋に浮かれた気分をその間奏の時間が際立たせているのは間違いなく、個人的に許しがたいし無粋にもほどがあると糾弾したくなるのだが、その単純化されたシンプルなアレンジもまた、この再録音版の新鮮な魅力に繋がっているように思えてくる。
』像もここには間違いなく反映されている。ただ"My Favourite Dress"のオリジナルのリズム・パターンから単純化し過ぎているプレイや(リズムキープだけがTWPのドラマーの仕事ではない)、"A Million Miles"の2番の後の間奏の省略は、「今日は百万マイルも歩ける気がするよ」という主人公の恋に浮かれた気分をその間奏の時間が際立たせているのは間違いなく、個人的に許しがたいし無粋にもほどがあると糾弾したくなるのだが、その単純化されたシンプルなアレンジもまた、この再録音版の新鮮な魅力に繋がっているように思えてくる。
そう、「Steve Albini録音」という言葉の印象だけから受けるかもしれない重々しい、ノイズィーな印象はここにはあまり感じられない。オリジナル作での後から音を被せ過ぎたり、元々フェアライトのプログラミングが専門だったオリジナル作のプロデューサー、Chris Allisonによる、このバンドの本質とはかけ離れているとしか思えない音像処理とは異なり(特にドラムに関しては、当時の最先端とは言え、シモンズの電子ドラムでリズムを作り込んでいることもあって、今聴くと安っぽく聴こえる)、デイヴィッドとクリスの2本のエレクトリック・ギターを前面に打ち出し、Steve Albini仕事ならではの生々しいドラムの録音も特色的なバンド・アンサンブルと共に、ライヴさながらに録られた本作は、アレンジがシンプルだからこそ余計にスピード感溢れるパンクネスや楽曲が元来持ち合わせいるポップネスをオリジナル作以上に浮かび上がらせることにも成功している。もちろん、そこには『Valentina』の録音テープに“魔法の粉をかけた”とデイヴィッドに言わしめたミックスダウン・エンジニア、もう1人の巨匠Andrew Schepsの貢献もあまりに大きい。
時間はかかり過ぎたが、長年噂されてきた秘蔵の録音がついに陽の目を見たという事実以上に、改めて当代随一のロックバンドThe Wedding Presentが30年前に残した出発点をre-visited(再訪問)し、その時点での解釈でre-imagining(再創造)したこの『George Best 30』は単なる記念品的な企画ものでは片付けられない、TWPのライヴ・バンドとしての強みを通常のスタジオ・アルバム以上に露にすることになった重要なカタログになった。久々に日本盤もリリースされる(2017年版At the Edge of the Seaフェスからの『George Best』再現ライヴから4曲を追加収録)ことにもなったし、それに伴う来日公演も実現することになったが、これは素直に、多くのオーディエンスに聴いてみて欲しい作品だ。直前に『Going, Going... 』の様に全神経を集中して聴き入るしかない稀代の傑作もあったが、このアルバムはとにかく大音量で鳴らしていて気持ち良いこと他無い。単純に気持ちが昂るし、ただただぶち上がる。これを聴きながら、来年4月の再会を楽しみにしたい。
』の様に全神経を集中して聴き入るしかない稀代の傑作もあったが、このアルバムはとにかく大音量で鳴らしていて気持ち良いこと他無い。単純に気持ちが昂るし、ただただぶち上がる。これを聴きながら、来年4月の再会を楽しみにしたい。
外部リンク
(first published : 3rd October, 2017)